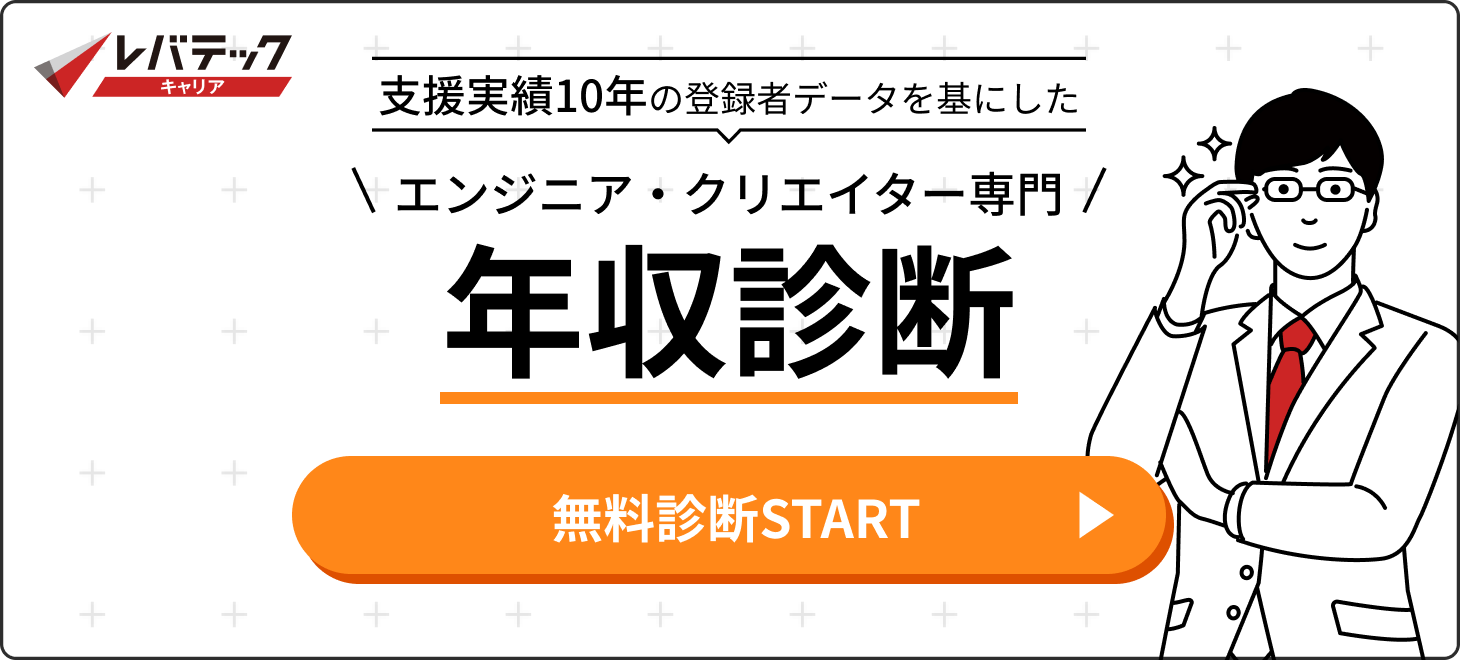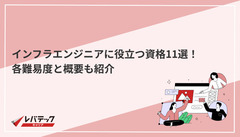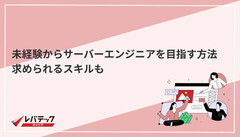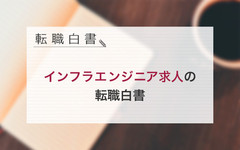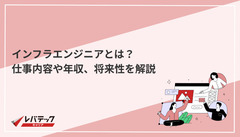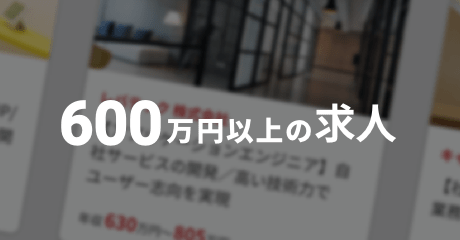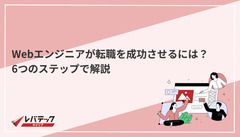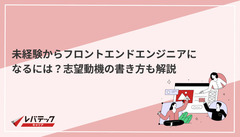- インフラエンジニアとは
- インフラエンジニアになるために最低限勉強すべき基礎知識
- キャリアアップを目指すインフラエンジニアが勉強すべきこと
- インフラエンジニア未経験でも実践できる独学での勉強方法6選
- インフラエンジニア未経験者が勉強に挫折しないために
- インフラエンジニアの勉強に繋がる資格
- インフラエンジニアの勉強に関するよくある質問
- まとめ
インフラエンジニアとは

インフラエンジニアとは、ネットワーク、ハードウェア、OS、ミドルウェアなどを扱い、システム開発におけるITインフラの企画・構築・運用に携わるエンジニアです。近年では技術的な選択肢の1つとして、クラウド技術や仮想化技術の利用もインフラエンジニアの業務に含まれます。
インフラエンジニアの行う「構築」とは、アプリケーションが動作するための環境を作成・整備し、開発チームなどに提供することを指します。その環境は大きく「オンプレミス」と「クラウド」に分類できます。
オンプレミスは、自社内にサーバーやネットワークなどの機器を用いて環境を構築、運用していく形態です。クラウドはネットワークを介してクラウドベンダーから提供される仮想サーバーや仮想ネットワークなどを運用をしていく形態です。近年では大企業でもオンプレミスからクラウドに徐々に移行し、導入も以前より増えてきました。
企画、設計、構築、テスト、運用などの工程全てをインフラエンジニアが担当するわけではありません。場合によってはベンダーやコンサルタントと折衝した上で分担したり、端末の操作を専門とするオペレーターに一部作業を担当してもらったりしています。したがって、インフラチーム以外との連携をすることも業務の1つとされています。
インフラエンジニアの種類
インフラエンジニアは専門とする領域により、種類を分けられます。その種類について、代表的なものを紹介します。
ただし、これらのエンジニア職種の領域は関連性を持っており、複数領域を担当するケースもあるため、必ずしも職種が分かれているとは限りません。所属企業やチーム、プロジェクトの体制によっても変わってくるため注意が必要です。
サーバーエンジニア
インフラの中でもサーバーの設計や構築を主とするエンジニアです。物理的なサーバー機種、構成機器、OS、ミドルウェアのインストールや設定など、サーバーに関わるあらゆる設定を行います。
近年のサーバー構築では、クラウドの活用や仮想サーバー、コンテナなどの仮想化技術を使った環境も、サーバーエンジニアの業務範囲に含まれます。
ネットワークエンジニア
ネットワークの設計や構築を主な業務とするエンジニアです。サーバーやネットワーク用の機器に対し設定を行い、ネットワークを構築します。構築するネットワークは、社内向けネットワークだけでなく、外部インターネットとやり取りする部分も含まれます。
ネットワークに関するスキルはもちろん、外部ネットワークからの攻撃についても考慮する必要があるため、セキュリティのスキルも必要です。また、ネットワークの分野でもクラウド活用への対応や仮想化技術の普及が進んでおり、これらのスキルも必要となります。
データベースエンジニア
データベースサーバーの設計や構築を主な業務とするエンジニアです。データベースは主流のRDBMS(リレーショナルデータベース管理システム)のほか、NoSQLなどもあります。データベース管理システムの設計・構築のほか、データを適切に管理するためにデータを格納するテーブルや索引などの論理設計も行います。
昨今では機械学習やデータ分析が注目されているため、SQLなどのデータベース関連スキルは需要が高いです。
クラウドエンジニア
インフラエンジニアの中でも、近年クラウド環境上でサーバーやデータベース、ネットワークの構築を専門とするエンジニアをクラウドエンジニアと呼ぶことがあります。クラウドにもプライベートクラウド、パブリッククラウドといった環境の違い、クラウドベンダーと提供サービスによる内容の違いなどが存在し、専門的知識が必要となります。クラウドエンジニアはクラウドの導入や活用の専門家として期待される職種です。
インフラエンジニアになるために最低限勉強すべき基礎知識
最初に必要となるのは、ITの基礎知識です。コンピュータの大まかな構成やプログラムの動く仕組みなどを身につけます。インフラエンジニアに限らず、ITエンジニア全般で最低限必要です。
さらに、インフラを構成する要素の基礎として、サーバー、プロトコルとは何かといった知識は勿論、現場で使われる独自ツールや機器の設定に関する知識も身につけていく必要があります。また、知識だけでは無く、実際にインフラの設定を行うための設定作業にも触れておく必要があるでしょう。
優先して習得しておきたいスキルは担当する業務によって変わってきますが、汎用的に使えるスキルとしてCUI(コマンド)操作や、バッチファイル、シェルスクリプト作成のスキルが挙げられます。また、独学での習得は難しいとされていますが、システム障害への対応スキルや経験もあるとなお良いです。
ネットワーク系の知識
コンピュータ間を繋ぐ、ネットワークはインフラの中でも重要分野の1つです。どのような仕組みでコンピュータ間の連携が行われているかを理解し、ネットワークの設計や構築を行うための知識とスキルが必要です。
ネットワークの構築に利用されるルーターやスイッチなどの機器についても知識を持つ必要があります。基本的な役割から、ネットワーク機器のメーカーごとの設定・管理方法などが求められます。
また、不正アクセスなどの防止のためセキュリティに関する知識や、サービスや業務を停止させないための可用性に関する知識の習得も必要です。
サーバー系の知識
インフラの基盤となるサーバーについて、構成するハードウェア、OS(WindowsやLinuxなど)、ストレージ、ミドルウェアなどに関する知識が必要になります。これらの製品、ソフトウェアの選択基準や、各種の設定を行う意味を理解し、適切にサーバーを構築するためです。
また、近年ではサーバーの構築には仮想化やクラウドサービスの利用が普及しているため、サーバー構築の選択肢の一つとして環境構築や運用に関する知識も求められます。
ネットワーク系とサーバー系、両方学ぶべき理由
さらにインフラエンジニアはネットワーク系とサーバー系両方の知識とスキルを備えておく必要があります。その理由は下記の2つが挙げられます。
まず1つ目は、実際の現場において「サーバーに関する業務のみ」「ネットワークに関する業務のみ」と、完全に分業することが少ないからです。
インフラエンジニア は「サーバエンジニア」と「ネットワークエンジニア」という分類をされることがありますが、この二者の定義や作業範囲は現場によって異なります。
たとえば、作業端末に必要な機器を接続してIPアドレスやポートを設定、別の拠点からその端末への疎通確認をするなど、どちらともいえないような業務が多数存在します。
2つ目の理由は、両方の知識がなければシステム全体の仕組みを把握できないからです。具体的な事例として、2020年10月1日に起きた東京証券取引所のシステム障害があります。
記者会見での説明や後日の正式な発表によると、障害は注文売買系と運用系の2種類のネットワークのうち、運用系のネットワークにて「共有ディスク装置のメモリ故障」が発生したことに起因しています。本来であれば、異常検知時にサーバー切り替えを実行するはずだが、「制御機構の設定値が適切でなかった」ため障害に至ったとのことです。
つまり、システム障害が起きたのは
-
・ハードウェア(メモリ)の故障・設計と異なった、ファームウェア(ソフトウェア)設定
の2点が原因だと言えます。
機器の故障が発端ではありますが、その機器(制御機構を搭載したストレージ機器)のファームウェア設定がシステム、ネットワーク全体へ影響しているため、どちらかの知識だけではこの障害対応はできませんでした。
インフラエンジニアがネットワーク系とサーバー系両方の知識を備える必要があるのは、こういった場面でも迅速かつ的確に障害対応をしなければならないからです。分野を横断したインフラに関する知識が無ければ障害やトラブルの原因特定には至れません。
関連記事:インフラエンジニアに必要なスキルは?知識、資格まで徹底解説
シェルスクリプトの知識
LinuxなどのUnixベースの言語では「シェルスクリプト」という文字ベースでの管理方法が用意されています。
インフラエンジニアはシステムの規模によっては複数台のサーバを構築する必要があります。1台1台画面をマウスで操作していくと膨大な時間がかかり、人為的なミスも発生します。そこで、シェルスクリプトというOSへの命令を集めたプログラムを使用することで、効率的かつ正確なサーバの構築作業が可能です。
なお、Windows系のOSでもバッチファイルやPowerShellがLinuxにおけるシェルと同様の役割を果たします。主に業務でWindows系のOSを利用する場合は、こちらを学習するとよいでしょう。
関連記事:shell(シェル)とは?概要や特徴、使用例、できることを解説
セキュリティの知識
システムには機密情報や個人情報など重要な情報が格納されているため、セキュリティ対策は不可欠です。特に外部との接続を持つサーバーやネットワークは、セキュリティ上の危険にさらされているため、十分な対策を行わなければいけません。
インフラにセキュリティソフトの導入、ファイアウォールやWAF、DMZなどの対策の実施、外部からの侵入検知などのセキュリティ対策を行うことで、多くの被害を防ぐことが可能です。セキュリティ分野は今後のインフラエンジニアにとっても重要視すべき知識・スキルとなります。
プログラミングスキル
インフラエンジニアはシステムを作るよりも、運用に合わせて環境を構築、提供することがメインのミッションです。このため、プログラミングスキルは必須ではありませんが、習得をおすすめします。
プログラミングスキルを習得できると、インフラ設定作業を効率化でき、業務の幅を広げることに繋がります。また、効率的に作業ができ業務範囲が広いエンジニアは収入も向上するでしょう。
さらに、近年のインフラ業務で重要視されるようになってきた考え方としてIaC(Infrastructure as Code)があります。インフラの設定内容をコード(プログラム)としてファイルに記載することで、再現性を高め、人為的なミスを減らすなどのメリットがあります。特にクラウドサービスの設定では重要となるため、インフラエンジニアにもプログラミングスキルの重要性が高まっています。
関連記事:インフラエンジニアもプログラミングスキルが必要な理由を解説
キャリアアップを目指すインフラエンジニアが勉強すべきこと
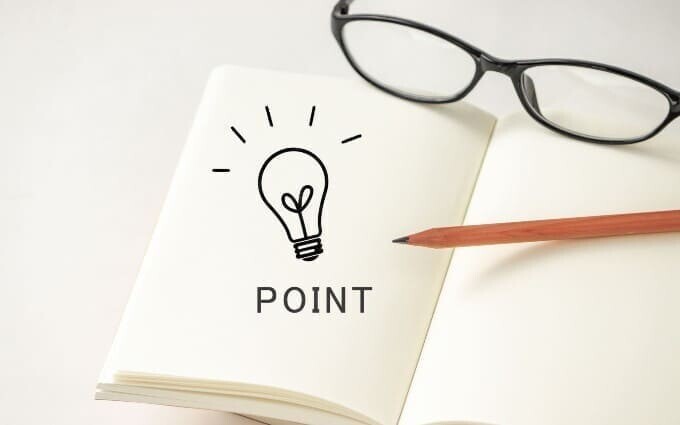
すでにインフラエンジニアとして活躍中の方が、今後キャリアの向上を図る際に勉強すべきことについて紹介します。ここにあげるスキルは、業界のトレンドを押さえたものや、今後のキャリアアップを見据えて習得しておくべきスキルです。ぜひ参考にしてください。
関連記事:インフラエンジニアになるには?必要なスキルや資格とは
クラウドの知識
近年、クラウドサービスの機能性の向上とコストダウンを追い風に、保守費や修繕費、人件費などを含めたトータルの維持コスト削減や業務効率アップを期待して、オンプレミス環境からクラウド環境に移行する企業が増えてきています(一度クラウドにしてからオンプレミスに戻す「オンプレミス回帰」と呼ばれるケースもありますが、ここでの説明は割愛します)。このようにクラウド化への需要が高まった中で、クラウド移行やクラウド運用に対する経験・知識のニーズは非常に高いです。
クラウドサービスの中でも人気があるのが、Amazonが提供するAWSやMicrosoftが提供するAzure、Googleの提供するGoogle Cloudです。これらの製品に対する知識、利用方法などは、いずれも公式で使い方に関するレクチャーが公開されているので、活用すると良いでしょう。
マネジメントスキル
インフラエンジニアが構築するインフラ環境では、業務上の機密情報や個人情報などの重要性が高い情報を扱う場合があります。扱うデータの重要性が高い場合、セキュリティへの対策は不可欠です。高度なセキュリティ対策が必要なインフラ構築では、求められる技術水準が高くなるため、高収入にも繋がります。
どのような対策を取ればセキュリティを強化、維持できるのか、インフラ上でのセキュリティ脆弱性、最新のセキュリティ対策のトレンドなどの知識はインフラエンジニアとしてのキャリア向上に役立ちます。
プレゼンスキル
顧客にインフラ導入や更新での提案を説明をする際には、プレゼンテーションをするスキルが必要です。顧客のITリテラシーは必ずしも高いわけではなく、分かりやすくインフラを説明することでインフラの有用性や必要性を理解してもらえれば、スムーズに設計、構築、運用、保守が進むため、エンジニアとしても多くの成果を出せるようになるでしょう。
英語
インフラエンジニアの扱う製品は、アメリカや英語圏で開発されているものも多く、マニュアルが英語版しか存在しないものも少なくありません。インフラ構築においては、マニュアルを読み込み正確な設定を行うことが重要です。
このため、英語のスキルがあれば製品の理解に繋がりやすくなり、最新情報も獲得しやすいためキャリア向上に役立ちます。
関連記事:インフラエンジニアが英語を使えることで得られるメリット
インフラエンジニア未経験でも実践できる独学での勉強方法6選
エンジニアは未経験からの挑戦を受け付ける求人が存在する職種ですが、前提として一定の知識とスキルを事前に習得することが求められることがほとんどです。まずはインフラエンジニアとなる前に、独学でも良いので学習しておきましょう。転職活動でのアピールポイントとなり、転職後もスムーズに業務につけるようになります。
ただし独学とはいえ、とりあえず適当に調べてやってみようでは、効率の良い勉強はできません。学習する内容を絞り自分に合った方法を見つけて進めることが重要です。以下では6つの方法のメリット・デメリットを解説した上で、おすすめするコンテンツをご紹介します。さらに、コンテンツを利用した学習とあわせて行いたい学習についても説明します。
関連記事:インフラエンジニアの転職で知っておきたいポイントや需要状況を解説
1.本・書籍での学習
独学を行う際のスタンダードな方法の1つとして、書籍を利用した学習が挙げられます。
メリット
書籍学習のメリットは、自分のレベルや学びたい知識を選んで学べること、そしてスクール学習と比べて費用を抑えられることです。
また、書籍を持ち運ぶことで、スキマ時間を有効に活用して学習できる点もメリットとなります。書籍の重さやサイズのせいで持ち運びに苦労したり、通勤電車では読みづらいといった事情も、電子書籍の活用で多くの問題は解消できます。
多少古い本であっても最近は電子書籍版が販売されていることも多く、文字検索に対応している書籍であれば読みたい箇所を見つけるのも簡単です。紙媒体より価格が若干安いことも多く、電子書籍のメリットは多数あります。
デメリット
書籍での学習のデメリットとして、必ずしも求めている内容が得られないことがある点です。
たとえば書籍を購入する際に品揃えの良さやサンプル、多数のレビューがあることからオンラインショップで選びがちですが、既に身につけている知識や学びたい内容は人によって異なります。学習を始めても「内容が難しすぎる/易しすぎる」「わかりにくい」などの書籍のミスマッチは極力避けなければいけません。
そのため、技術書を購入するときは書店に足を運び自分に合うか実際に目を通して確認することをおすすめします。
2.学習サイトや企業のサービスを利用してトレーニングする
学習のためのコンテンツを掲載しているWebサイトを利用することも学習方法の1つです。クラウドなどのサービスを提供している企業により用意されている無料の学習コンテンツもあるため活用しましょう。
注意点として、無料で使えるサービスには「無期限無料」「XXヶ月間無料」「トライアル」などの種類があります。望まないコストがかからないように、不要になったら登録を解除するなどコントロールしましょう。
メリット
学習サイトや企業の提供する学習コンテンツの大きなメリットは、学習環境が整えやすく取り組みへのハードルが低いことでしょう。Webブラウザだけで利用できるコンテンツや環境は、PCとインターネットへの接続環境があればすぐにでも利用を始められます。
さらに、コスト面でのメリットも存在します。無料コンテンツが多いこと、新たに専用の端末を用意しなくても良いことなどから、学習にかかるコストも抑えやすいです。
デメリット
Webサイトなどでの学習でデメリットとなるのは、学習上の問題が発生した場合に解決が難しいということです。Webサイト上に記載されていない点で問題が発生すると、原因の追究が難しく、相談相手もいないため学習が行き詰ってしまうケースもあります。
たとえば、コンテンツの記載通りに行ってもエラーが発生し想定通りに行かなかったり、無料で利用できる環境で問題が発生した場合でもベンダーに対応してもらえないケースです。このようなケースは稀ですが、実際に発生してしまうと自力で対応しなければいけません。
3.勉強会に通う
インフラについて独学でスキルを身につけるといっても、視野が狭まり、テキストを丸暗記する形では実践的ではありません。他者と交流しながら学習する方法の1つとして、勉強会を利用する方法があります。
メリット
勉強会でほかの人と学習することにはさまざまなメリットがあります。1つは、他者と問題や学習を共有することで、自分だけでは理解・解決できない問題も解消しやすいことです。仲間を通じて人脈を広げられるという点も大きいです。
また、学習をともにする仲間がいることで刺激を受けて、学習モチベーションを維持しやすい点もメリットです。一人だけで学習するよりも、競争や協力をすることにより学習の継続がしやすくなります。
デメリット
勉強会を利用する場合、デメリットも存在します。勉強会そのものが悪いわけではないのですが、勉強会に参加していることで分かった気になってしまう、学習意欲が満たされてしまう、といったケースがあることです。勉強会に参加する場合には、成果の確認も行い、自分の役に立っているかを確認しておきましょう。
4.動画サイトを活用する
学習サイトの動画コンテンツのほか、Youtubeなどの動画サイトにも多くの有識者が動画をあげているので、それを活用するという方法もあります。特に海外のエンジニアが投稿している動画では最新の情報について解説しているものもあり、英語がわかれば最新の情報をキャッチアップしやすいというメリットもあります。
初心者向けの動画もあるため、どんな技術かまず知ってみたい、触れてみたいという方におすすめです。
5.まずは実際に手を動かしてみよう
必要な知識を身につけても、実際に使われているインフラ環境に触ってみるとうまく使えないということがあります。業務で実際に行う環境は、書籍やコンテンツで紹介されているものと全く同じとは限りません。また、得た知識を実際に活用して初めて技術として身に付きます。クラウド、仮想環境などを積極的に利用して環境を用意し、使ってみることもインフラエンジニアの勉強になります。
Mac、Linux(Linux系含む)の場合
Mac、Linux(Linux系含む)の場合は、「コンソール」「ターミナル」を使用します。(※)
※Linuxの場合、設定によっては「端末」という名称の場合もあります。
使用できるのはLinux (Unix)コマンドおよび、「.sh」という拡張子のファイルを実行できます。この「.sh」は「.bat」同様、コマンドを組み合わせたファイルです。
拡張子.shファイル(シェルスクリプト)について
Unixシェルと呼ばれることもあります。サーバーに限らずLinux系OSは多くの現場で使われているので、学習しておくとインフラ系以外の実務でも非常に役立ちます。
見出しでOSの分類を「Linux系」と記述しましたがLinuxは「ディストリビューション」という形でパッケージ化されており、同じLinuxと言っても多数の種類が存在するため、これら全体を指すためにLinux系という言葉が用いられます。
細かな差異はありますが、実行できる基本的なコマンドラインは同じです。業務で使われていることの多いディストリビューションとして次のものが挙げられます。
-
・Cent OS
・Red Hat
・Debian
・ubuntu
ディストリビューション全てを覚える必要はありませんが、この4種類は多くのシステムで使われているので、使用経験があればアピールできる機会が多いです。
エディターについて
バッチファイルやシェルスクリプトなどのファイルを開いたり作成するときに良く使われるツールとして「vi(viエディタ、vimなど)」というものがあります。
メモ帳や一般的なテキストエディタと比べて操作方法に癖がありますが、GUI操作でファイル参照や編集ができない場合に非常に役立ちます。実務でこの操作が必要な場合もあるのでこちらも合わせて覚えておきましょう。
Mac、Linux系OSの場合は「nano」というエディターがあり、こちらは比較的使いやすいです。日常の用途ではほとんど必要ありませんが、インフラエンジニアであればエディターを用いたコマンド操作は必須のスキルです。
まずは仕様頻度の高いコマンドから覚えていき、業務で使うシェルスクリプトやバッチファイルの動きも理解できるようになればスキルアップに繋げられます。
インフラエンジニア未経験者が勉強に挫折しないために
インフラ関連の知識領域は幅広く、覚えることが非常に多いので、インフラエンジニアを目指す未経験者にとって、勉強の道は険しいかもしれません。未経験者が勉強に挫折しないための工夫について解説します。
資格取得などの目標を定める
まず、自身の学習を促進するために資格取得を目指すことは有益な方法の1つです。
資格は体系的に知識を身につけることができ、資格取得という明確なゴール設定ができるのでおすすめです。
とはいえ難易度の高い資格にいきなり挑戦してしまうと、資格の勉強の過程で挫折してしまう可能性があるため、このあとの章で紹介する、インフラエンジニアの勉強に役立つ資格から取り組むのが良いでしょう。
一人では覚えにくい場合は勉強会やスクールなど対人がおすすめ
インフラエンジニアの知識を習得する際、一人では理解が難しいこともあります。特に独学で勉強して理解が追い付かない場合、質問する相手がいないと勉強が行き詰ってしまいます。これが原因で挫折してしまう人も少なくありません。
そのため、勉強会や専門スクールなど、他の学習者や専門家との交流がおすすめです。勉強会では、同じ目標を持つ仲間たちと知識を共有し合い、理解が深まるでしょう。
また、専門スクールでは、経験豊富な講師から直接指導を受けられ、複雑なトピックも体系的に学べます。人との交流を通じて、学習の楽しさや成果を実感し、挫折を乗り越える力を養えます。
時間が足りない場合はオンライン講座などを活用
忙しい日々の中で勉強する時間を確保することは難しいかもしれません。しかし、オンライン講座などの学習リソースを活用することで、効果的な時間管理が可能です。
多くのオンラインプラットフォームでは、自分のペースで学習できるため、仕事や家庭との両立が容易になります。また、コースごとに学習計画が用意されていることもあり、無駄なく効率的に学習を進められます。時間に制約がある場合でも、自分のペースで学ぶことで、継続的な学習が可能です。
インフラエンジニアの勉強に繋がる資格

資格の取得は知識の保有をアピールできる点と、資格に向けた学習をすることで実務への理解を深める点がメリットです。以下では、インフラエンジニアに関連する代表的な資格をいくつか紹介していきます。
関連記事:
インフラエンジニアに役立つ資格11選!各難易度と概要も紹介
インフラエンジニアのキャリアパスは?将来性や役立つスキルと資格も解説
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営し、経済産業省が認定するITエンジニア向けの国家資格です。ITエンジニアとしてエントリレベルのスキルを示すことができる資格ですが、ハードウェア、ソフトウェア、プログラミング、システム開発技法など総合的な知識が必要となります。
午前は選択式、午後は記述式でわかれており、午前の問題ではITパスポート以上の知識が必要です。午後はインフラエンジニアでは扱うことの少ないプログラミングやアルゴリズムに関する問題を1種類選択するため、その内容に特化した学習が必要となります。
ITエンジニアの登竜門とも位置づけられる資格であり、IT未経験や初心者の方は、ITパスポートと同様にこの資格の取得を最初に目指すと良いでしょう。
CCNA
CCNAはシスコシステムズが実施している試験で、ネットワークエンジニアに向けたベンダー資格です。シスコシステムズはネットワーク機器で世界シェアトップを誇り、多くの企業で採用されています。そのためネットワークエンジニアがシスコシステムズ関連の機器を扱えるということは大きなアピールポイントに繋がります。
CCNAはネットワークに関する基礎的な知識だけでなく、シスコ製品の専門的な知識を問われる内容となっているため、取得することでシスコ製品の知識があることをアピールできます。
シスコの資格試験も複数のグレード、試験分野があるため、示したいスキル、レベルにあわせて選択しましょう。
LPIC/LinuC
LPIC、LinuCはどちらもLinuxに関するスキルをもっていることを認定する「Linux技術者認定資格」です。LPICは世界標準の資格であり知名度が高く、LinuCはクラウド分野も一部取り込み日本向けに最適化されています。どちらの試験勉強でもLinuxに関する知識を身につけられます。
インフラエンジニアの業務としてサーバーの設計・構築がありますが、LinuxはサーバーOSで高いシェアを持っているため、扱うことが多いです。そのため、LPIC/LinuCの資格を取得しておくと、Linuxを扱う業務で役に立ちます。
LPIC/LinuCどちらもレベルが1~3まであり、レベル3が最も難易度が高い資格です。海外向けの案件に携わる場合はLPIC、国内企業向けの案件に携わる場合はLinuCを取得すると良いでしょう。
関連記事:Linuxのおすすめ資格LinuC・LPICとは?難易度や勉強方法を解説
ITパスポート試験
ITパスポート試験は全てのIT利用者に向けた試験で、インターネット、コンピュータに関する基礎的な知識が問われます。難易度は比較的低いため、全くの未経験であっても取得しやすい資格です。
試験範囲には、コンピュータの基本操作、ネットワークの基礎、セキュリティに関する基本知識などが含まれています。これらの知識は、インフラエンジニアにとっても必要不可欠であり、今後のステップに活かすことができます。
IT未経験や初心者からインフラエンジニアを目指すのであれば、まずこの資格を取得することから目指すと良いでしょう。
ORACLE MASTER
ORACLE MASTERは、商用データベースとして大きなシェアを持つオラクル社のデータベースソフトウェア「Oracle Database」に関する知識とスキルを示すことのできるベンダー試験です。2024年3月18日時点ではORACLE MASTER2019が最新の資格体系で、Bronze、Silver、Gold、Plutinumの4段階のグレードに分かれています。
また、オラクル社はクラウドサービス「Oracle Cloud」を提供しています。ORACLE MASTERはOracle Cloudの中でもインフラのサービスである「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」に関連する資格も存在します。
データベース、そしてクラウド両方のスキルを得るうえで、Oracleを扱う機会があるエンジニアにとって役立つ資格といえます。
AWS認定試験
AWS(Amazon Web Service)は、クラウド分野で最も世界的にシェアを集めているクラウドサービスです。そのため、AWS認定試験はインフラエンジニアにとって非常に有用な資格です。
AWS認定はAWSに関するスキルと知識を認定するベンダー資格です。クラウドに関するスキルを示すことができ、AWSを利用するプロジェクトでは大きなアピールポイントとなります。「FOUNDATIONAL」「ASSOCIATE」「PROFESSIONAL」の3段階のグレードと、専門分野でのスキルを示す「SPECIALTY」に分かれています。
インフラエンジニアの勉強に関するよくある質問
最後に、インフラエンジニアの勉強に関するよくある質問に回答していきます。インフラエンジニアの一日の流れや仕事内容について参考にしていただき、インフラエンジニアがどういう職種であるか、理解を深めてください。
Q1. ITのインフラは何から勉強すれば良いですか?
まず最初はITの基礎知識から勉強すると良いでしょう。コンピュータの大まかな構成やプログラムの動く仕組みなどは、インフラエンジニアに限らず、ITエンジニア全般で最低限必要です。
ある程度コンピュータの仕組みが理解できるようになってきたら、インフラを構成する要素であるサーバー、ネットワーク、現場で使われる独自ツールや機器の設定に関する知識も身につけましょう。また、知識だけでは無く、実際にインフラの設定などを行うとさらにスキルが得られます。
今では無料でサーバーやネットワークを構築できるクラウドサービスもあるので、実際に手を動かしてスキルアップしていくことをお勧めします。
Q2. インフラエンジニアに将来性はありますか?
近年、クラウド移行や新たな仕組みの採用によりインフラエンジニアの役割が変化してきています。しかし、クラウドやネットワークなどの基盤は依然として必要で、インターネットサービスや新技術領域での需要も増加傾向にあります。そのため、インフラエンジニアの需要は今後も高水準が続く見込みですが、クラウドに関する知識も求められるようになってきています。
Q3. インフラエンジニアの一日の流れは?
顧客現場での作業のない日は、インフラエンジニアのスケジュールは通常の社員とほぼ同様です。
一方、構築作業時は場所によって直行直帰となるパターンもあります。たとえば、8時にベンダーと合流し、データセンターで昼休憩をはさみながら作業し、18時に退社などの例が挙げられます。
また、顧客業務を妨げず、適切な時間帯に作業するため早朝や深夜勤務を行うこともあります。たとえば、OSやミドルウェアに対するパッチ適用、ネットワークの構成変更では、システムを一時的に停止する必要があります。その場合にシステムが利用されない時間帯である、休日や深夜に勤務する場合があります。
Q4. インフラエンジニアとはどのような仕事ですか?
インフラエンジニアとは、ネットワーク、ハードウェア、OS、ミドルウェアなどを扱い、システム開発におけるITインフラの企画・構築・運用に携わるエンジニアです。近年では技術的な選択肢の一つとして、クラウド技術や仮想化技術の利用もインフラエンジニアの業務に含まれます。
まとめ
この記事では、インフラエンジニアの習得すべきスキルや、スキル習得に役立つ勉強方法を解説しました。キャリアプランをたて、計画的にスキルを習得していくことがキャリア向上に役立ちます。
インフラエンジニアはネットワーク、サーバー、クラウドなど幅広い技術領域に関する知識とスキルが必要とされます。幅広い知識を要求されますが、インフラ関連の知識は習得後には異なる現場でも活かせるものが多いため積極的にスキル習得したいところです。
効率よくスキルアップをしていくためにも、まずは土台となる基礎知識を身につけることが重要です。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。
「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。
「個別相談会」に申し込む
転職支援サービスに申し込む
※転職活動を強制することはございません。
レバテックキャリアのサービスについて