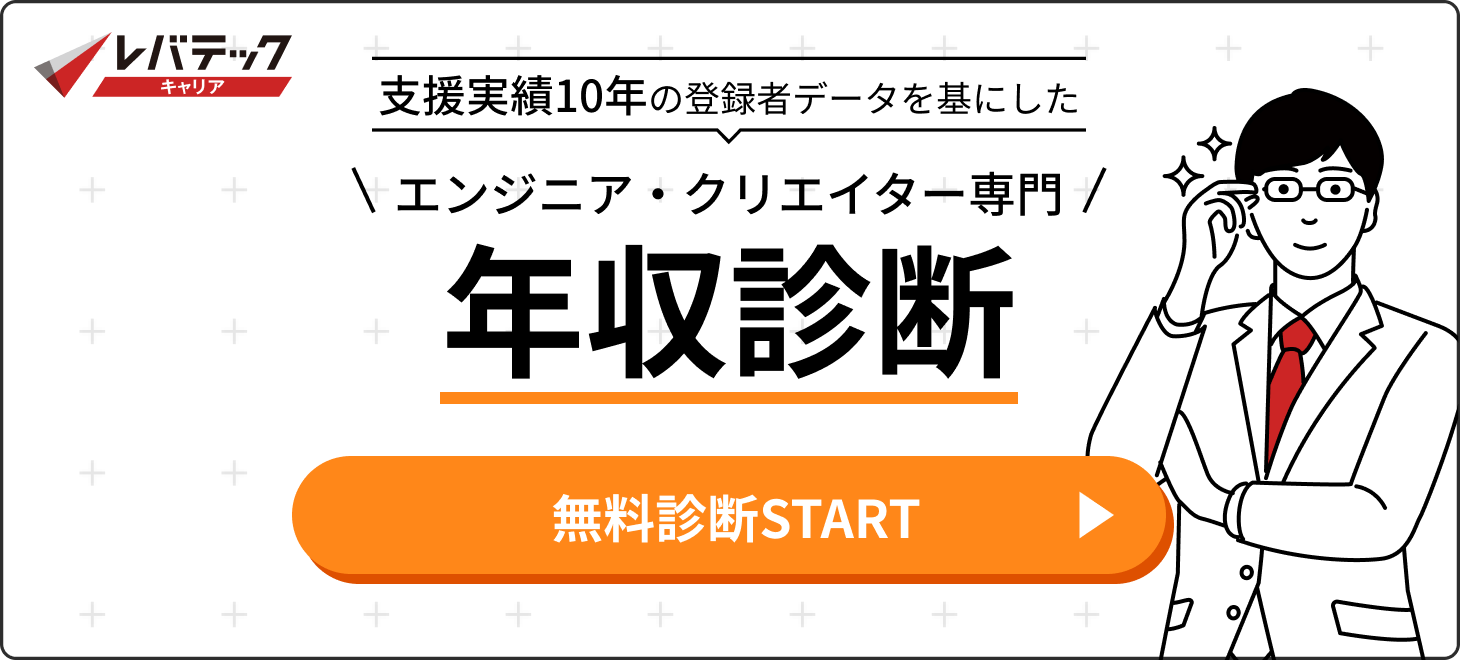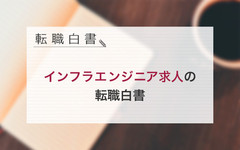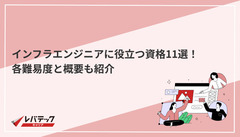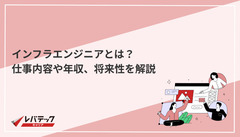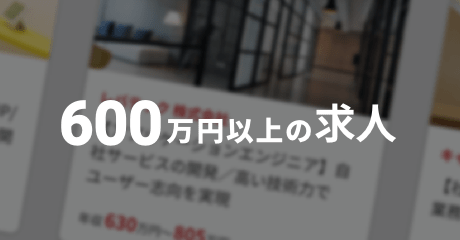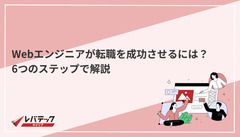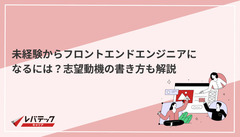インフラエンジニアとは
インフラエンジニアとは、サーバーやネットワーク、データベースなどのITシステムの基盤を設計・構築する仕事を行うエンジニアをいいます。
システムは、システムエンジニアやプログラマーが開発するプログラムやアプリケーションだけで動くものではありません。プログラムを動かすサーバーや、サーバー同士を接続するネットワーク、データを蓄積するデータベースなどの基盤と合わさって、初めてシステムとして成り立ちます。インフラエンジニアは、そのシステム基盤を構築するエンジニアです。
インフラエンジニアは「サーバーエンジニア」「ネットワークエンジニア」のように、それぞれの専門分野によりさらに細分化されます。最近ではクラウドサービスの普及により、クラウド上でITインフラ基盤を構築する「クラウドエンジニア」がありますが、これもインフラエンジニアの一種です。
インフラエンジニアの具体的な仕事内容や年収については、以下の記事で解説しています。こちらもあわせて御覧ください。
関連記事:インフラエンジニアとは?仕事内容や年収、将来性を解説
インフラエンジニアの転職需要
DXやアフターコロナへの対応で企業はIT環境の重要性を再認識し、IT人材の需要は上昇している状況です。労働人口減少によるIT人材の不足も影響しており、IT業界全体で需要が高まっているといえます。
一方、インフラエンジニアについては、クラウドサービスの普及により企業がオンプレミス型でサーバーを自社やデータセンターに置く数が減り、設計、構築、運用とも業務が減少するといわれた時期もありました。
しかし、クラウドサービスの普及によりインフラエンジニアの業務が減少するという言説は正確ではありません。企業がオンプレミスでサーバーを自社やデータセンターに置く数が減少しても、ITシステムそのものや必要なシステム環境の数が減るわけではありません。
自社サーバールームやデータセンターにあったサーバー環境から、クラウドサービス上に環境がおかれるように変化していくだけといえるでしょう。インフラエンジニアの需要も同様で、クラウド環境に対応できる業種・業界に需要が集中してきています。それぞれの業種や業界について、その状況を紹介します。
業種ごとに需要状況は異なる
インフラエンジニアは、専門とする分野により職種が分かれており、それぞれ需要の変化があります。業種ごとの需要状況について解説します。
サーバーエンジニア
サーバーはオンプレミスからクラウドへ環境を移している状況です。また、仮想化技術の利用による集約化も進められています。仕事の内容はクラウド環境の構築に移ってきてはいるものの、サーバー環境の構築そのものは存在しているため、サーバーエンジニアの需要は引き続き高い状況です。
また、クラウド移行がトレンドでも、移行するためのリソースや既存のレガシーシステムに業務のコアな部分を支えられているなどの理由から、クラウド移行を躊躇している会社がまだ多いのも事実です。そのような会社では、旧来のサーバーエンジニアの需要は今後も根強く残ると考えられるでしょう。
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアの必要性は引き続き高い状況です。特にテレワークの普及により、ネットワーク上のセキュリティといった観点が重要視されるようになり、セキュリティ分野における需要が今後も高まることが予想されます。
社内インフラにおいて、ネットワークはIT基盤を支えているといっても差し支えない存在です。BCP観点からも、さまざまなリスクに備え続ける可能性があり、ネットワークエンジニアの需要がなくなることは考えにくいでしょう。
クラウドエンジニア
クラウドエンジニアはクラウド環境の構築、利用の推進を行う職種です。クラウドサービスは柔軟にリソース量を変えられ、ハードウェアメンテナンスからも解放されるなど企業が得られるメリットは豊富です。今後もオンプレミスからクラウドへの移行が進められる傾向は続くことが想定され、クラウドエンジニアの需要は引き続き高いと考えられます。
ただし、クラウドネイティブ技術の活用やPaaSを利用したシステム再構成など、システム再構成・再構築を必要とする移行には消極的な会社もまだ多い点には留意しておくべきでしょう。
データベースエンジニア
データベースのパッケージングが進み、専門職でなくてもデータベースを扱いやすくなってきました。一般のエンジニアにデータベースに関する業務を任せることが増え、データベース設計、構築を専門とするデータベースエンジニアの活躍の場は減少傾向にあります。
一方で他の専門分野を持ちながら、データベースのスキルも持ったエンジニアとして成長できれば活躍できる場面があるでしょう。また、大規模プロジェクトにも需要があります。
運用保守系エンジニア
クラウドサービスや仮想化環境の利用により、サーバーや環境の集約が進んでいます。運用保守という観点で見れば、集約された環境によって必要な手間が減るため、需要は減少することが想定されます。また、今後必要とされる運用保守業務にはクラウド、仮想化した環境を扱うためのスキルが求められるようになるでしょう。
さらに、運用管理業務負担の軽減・省力化に課題を持つ企業が多いことから、運用保守の業務における課題抽出から改善まで行った経験のあるエンジニアのニーズが高いことが予想されます。
例えばアプリ開発と運用の両方を兼ね備えたDevOpsのスキルがあれば、開発スピードを高め、ビジネスの価値を高めることが可能です。またRPAなど自動化の仕組みを活用して運用保守を改善できるエンジニアはニーズが高いです。
業界によっても需要状況は違う
職種だけでなく、インフラエンジニアが所属する業界によっても需要には偏りがあります。知っておくと転職の際に役立つでしょう。インフラエンジニアが関わる代表的な業界の需要状況について詳しく解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
ソフトウェア・通信
ソフトウェア開発、通信業といった業界においては、新しい技術への対応が必要なため、インフラ環境の刷新も継続的に行われています。技術的な素地はあるため、仮想化による環境の集約、クラウドの利用によるリソースの最適化なども積極的に行われる傾向があります。インフラエンジニアについても需要は高い傾向です。
この業界でインフラエンジニアとして働く場合は、仮想化技術(Docker)やクラウドサービス(AWS、Azure)などの技術に対する知見が必要となってきます。
メーカー
メーカーにおける工場などの生産拠点では、システムは可用性の高さが求められるため、オンプレミス環境も残ります。IoTなど導入も進められており、クラウド環境との併用が想定されるため、幅広くインフラの知識、スキルを持つインフラエンジニアが求められています。
小売、流通
小売、流通業においてもECサイト、物流システム、アナリティクスなどITシステムの活用の必要性は非常に高いです。インフラも可用性、スケール、セキュリティなどを考慮しながら構築する必要があり、インフラエンジニアへの需要も存在しています。高いスキルを持ったインフラエンジニアが求められる業界です。
金融
金融業界は、fintech(フィンテック)としてIT技術を取り込んだ新しいビジネスの形を作りつつあります。fintechはITベンチャーから生まれるケースが多く、その下地としてインフラエンジニアの必要性も高いです。自分で学びながら、変わり続ける要求に対応できるインフラエンジニアが必要とされています。
インフラエンジニアは未経験者の転職需要も高い
未経験からインフラエンジニアになれる主な理由は2点あります。1点目は需要の高さに対して供給が追いついていないことです。2点目はクラウドに関する技術を身につけて、即戦力になれる可能性があることです。詳しく順番に見ていきましょう。
ITインフラは常時稼働させる必要があるため人手が必要
社会を支えるITインフラは、365日・24時間体制で稼働しなければなりません。コンピュータネットワークはあらゆる業種でなくてはならず、インフラエンジニアを求める企業は多いため、需要が高いです。
特に運用や保守の仕事は、ITインフラを支えていく上で常時稼働する必要があるため、人手不足に陥りやすいです。厚生労働省が発表している、令和5年10月分の一般職業紹介状況によると情報処理・通信技術者の有効求人倍率は1.51倍となっています。新規求人倍率は3.23倍と人手が足りないことがデータで示されています。
システムのクラウド化に伴いクラウドエンジニア・スキルが必要とされている
多くの企業でシステム基盤にクラウド化が採用されており、クラウドエンジニアを必要としています。クラウドスキルを身につければ、未経験でも即戦力として活躍できるチャンスは十分あります。
インフラエンジニアには技術の進化によって新しいスキルが求められることから、未経験でも参入のチャンスがあるでしょう。
関連記事:未経験からインフラエンジニアになれる?転職方法や求人例を紹介
インフラエンジニアの転職に必要なスキル・経験
未経験からでもインフラエンジニアになることは可能です。しかし、必要なスキルや勉強方法、仕事の探し方などが分からなければ挫折してしまいます。また、専門的なスキルが求められるため、十分なスキルを身につけていないと、現場で活躍することは難しいでしょう。ここでは、未経験からインフラエンジニアを目指す際に必要な情報を一通りお伝えします。
ネットワークやサーバーに関するスキル
インフラエンジニアになるために必須のスキルとしてまず挙げられるのが、ネットワークやサーバーに関するスキルです。IPアドレスやTCP/IPなどのプロトコル、LAN/WANに関する知識など、サーバー同士で通信できるネットワーク設定を行えるスキルが必要です。
また、サーバーを設計・構築し、正しく運用するための知識も必要になります。システムを安定稼働させるには、プログラムが正常に動作すると同時に、システム基盤が正常であることが必須です。サーバーやネットワークでトラブルが発生した場合は、インフラエンジニアが対応します。
たとえば、何らかの原因でサーバーがダウンしたりネットワークの遅延が発生したりした場合、インフラエンジニアはOSからの情報やログなどを確認し、原因を突き止め、問題を取り除かなければなりません。そのためにも、ネットワークやサーバーに関する深い知識と、問題解決能力が求められます。
これらのスキルを身につけるには、ただ書籍やドキュメントを読んで知識を高めるだけでは不十分です。実際にインフラを設計・構築し、トラブル対応などを経験することが大切です。サーバーOSとして代表的なLinuxや仮想ソフトウェアは無償で利用できるため、それらを利用してスキルを高めていきましょう。
クラウドサービスのスキル
ITインフラのクラウド化が進んでいるため、インフラエンジニアはクラウドサービスに関するスキルも必要です。
ネットワークやサーバーに関するスキルをベースに、クラウド固有のコンソールから仮想サーバーや仮想ネットワークの構築、クラウド上で提供されているサービスを上手に組み合わせて、クライアントが求めるシステムを構築するためのスキルが求められます。
自分たちでサーバーやネットワークを構築してシステムを運用するオンプレミスの場合と異なり、クラウドでは仮想環境固有の仕組みや、提供されているサービス内でできること、できないことを把握しておく必要があります。
主要なクラウドサービスとして、AWSや、Microsoft Azure、Google Cloudなどがあります。これらのクラウドサービスでは、無料利用枠が用意されているものもあります。実際にクラウドサービスに触れてみることをお勧めします。少なくともいずれかのクラウドサービスのスキルは身につけておくとよいでしょう。
コミュニケーションスキル
システムの規模にもよりますが、ITインフラ基盤の構築は基本的に一人で行うことはなく、多くのエンジニアと協力します。サーバーやネットワークを設計するにはクライアントとのコミュニケーションが必要であり、稼働するシステムに関してはシステムエンジニアとの連携が必要です。ほかにも、サーバーエンジニアやネットワークエンジニアなど、各専門分野のエンジニアが協力してITインフラを構築することもあります。
多くのエンジニアと協力してシステムを構築するためには、コミュニケーションが欠かせません。正しく意思疎通を行い、伝達ミスをなくすために、十分なコミュニケーションスキルが求められます。
マネジメント経験
システム開発の規模によっては、長期にわたってプロジェクトを進めることもあります。それぞれの作業をスケジュールどおり進めるためには、マネジメント経験が求められます。
マネジメントの例としては、いつまでにどのタスクを終わらせないといけないかを正しく管理するためのタスク管理、今後発生しうるリスクを列挙し対策を策定するための課題管理、全体の進捗を確認するための進捗管理などがあります。
これらの管理を1つひとつ確実に行いながら、決められたスケジュールどおりプロジェクトを進行するためにも、マネジメント経験が必要です。
インフラエンジニアの転職におすすめの資格
インフラエンジニアの転職において、資格を持っていることは第三者的な立場から一定のスキルを持っていることを示せるため、有効な手段の一つです。特に未経験の場合は、ある程度のスキルを持っていることの証明につなげるためにも、自分が得意とする分野の資格をもつことをおすすめします。ここでは、インフラエンジニアの代表的な資格を紹介するので、ぜひ転職活動の参考にして下さい。
AWS認定
AWS認定(AWS Certification)はamazonが運営するクラウドについての専門知識を効果的に証明できる資格認定試験です。基礎コース、アソシエイト、プロフェッショナルの3段階の包括的なスキルと知識を示せる資格と、AWSの特定のサービスに関する専門知識を対象とする6つの資格があります。
インフラエンジニアとして転職を考える場合、クラウドサービスのスキルが必要となることが多く、その中でも大きなシェアをもつAWSの認定資格はアピールポイントとなります。特におすすめの資格は「AWS認定ソリューションアーキテクト」です。AWSサービスの基本かつ広範囲のサービスについて出題されるため、難易度はやや高いですが未経験でも取得は可能です。クラウドエンジニアを目指すのであれば、ぜひ取得しておきたい資格です。
Microsoft Azure認定資格
Microsoft Azure認定資格とは、Azureに関する専門知識やスキルを証明できる資格です。Microsoft社が認定している資格で、次の9種類の分野に分かれています。
-
・基礎
・開発者
・管理者
・ソリューションアーキテクト
・データエンジニア
・データサイエンティスト
・AIエンジニア
・DevOpsエンジニア
・セキュリティエンジニア
さらに、それぞれに4段階のレベル別カテゴリが存在し、上述した分野とレベルカテゴリに応じて初級、中級、上級の3つの難易度に分かれます。
管理者や開発者などで分かれているため、自分の習熟度や強みを持つ分野に合わせて資格を取得すると良いでしょう。
Azureの知識があることでニーズのあるクラウドエンジニアとして活躍できるでしょう。MicrosoftはAzureで生成AI基盤を大幅に強化していることもあり、オンプレミス環境からクラウド環境に移行している企業が増加しています。クラウドの浸透はまずます広がっていくと予想されるため、資格の取得をすることで安定して仕事ができるといえます。
シスコ認定試験
シスコ認定試験とは米国企業のシスコシステムズが認定している資格です。ネットワーク系の資格として有名な資格で、試験は「エントリー」「アソシエイト」「スペシャリスト」「プロフェッショナル」「エキスパート」の5つに分かれています。アソシエイトレベルのCCNA以上を取得できれば、インフラエンジニアに必要なネットワーク関連の知識やスキルを証明できます。
ネットワークエンジニアに必要な知識が詰め込まれ、業務で役立つネットワークの知識やシスコ機器の扱い方を学べるため、転職で活かせるでしょう。
ORACLE MASTER
ORACLE MASTERとは米国企業のオラクル社が認定している資格です。オラクル社の製品である「Oracle Database」はデータベース分野で最も高いシェアを誇っており、データベース系の資格として有名です。試験は「Bronze」「Silver」「Gold」「Platinum」の4つのレベルに分かれています。
加えて、オラクル社はクラウドサービス「Oracle Cloud」も提供しており、ORACLE MASTERの中にはOracle Cloud関連の資格も用意されています。Oracle Databaseを利用している企業がクラウドサービスに移行する場合、Oracle Cloudが候補の1つとして上がるため、Oracle Database関連とともにOracle Cloud関連の資格もあわせて取得しておくとよいでしょう。
他にも、オラクル社はアプリケーションサーバーで有名なWeblogic、プログラミング言語Javaも提供しており、それらの資格も提供しています。
情報処理技術者試験(基本、応用)
情報処理技術者試験は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の運営する国家資格です。元となる資格を含めると昭和44年から運営されており、IT業界でも信頼されている資格となっています。
その試験区分の中でも基本情報技術者試験はエンジニアとして幅広く実務レベルの基礎的なスキルと知識を保有することを示す資格試験です。ITエンジニアの登竜門とも言われている資格であるため、必ず押さえておきたい資格です。
一方で応用情報技術者試験は、基本情報技術者試験の上位の資格で、実務レベルで活躍できるスキルと知識を示せます。
情報処理技術者試験(スペシャリスト)
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の運営する情報処理技術者試験の中には、特定技術分野のスペシャリストのための試験があります。インフラエンジニアとして特に技術力を示せる資格として、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリストが該当します。専門分野の高度な知識とスキルの保有を示す資格です。
情報処理安全確保支援士
情報処理安全確保支援士は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の運営する情報処理技術者試験で、2016年に追加された資格です。ITシステムおよびその利用者の情報セキュリティ確保は重要な課題です。インフラの構築においても、セキュリティは重視される項目であり、情報処理安全確保支援士の資格を持つことで情報セキュリティに関する知識とスキルを示せるでしょう。
LinuC
LinuCはNPO法人LPI-Japanにより企画、開発、運営されるLinux技術者の認定資格です。クラウド環境までを含めた技術を示すことができる資格で、中立、公正な立場からLinux技術者の技術力を証明できます。3段階のレベルに分けられており、クラウド、仮想環境、システムアーキテクチャなどインフラエンジニアとして必要なスキル、知識を示すことができ、転職時には有利に働く資格です。
■レバテック キャリアアドバイザーからの一言
どの資格も、取得することで一定のスキルの証明になりますが、単一の資格だけでなく、複数の資格をかけあわせて持っていると、より高い評価をえられやすくなる傾向があります。
近年はAWS認定資格が人気ですが、プロフェッショナルレベルのソリューションアーキテクトやDevOpsエンジニアの認定があると、企業からも一目置かれるケースが多いです。
インフラエンジニアへの転職で失敗しないためのコツ

ここからは、インフラエンジニアとして転職活動を行う際に押さえておきたいポイントについて紹介します。「年収を上げたい」「社会貢献度の高い仕事をしたい」「よりやりがいのある仕事をしたい」など、転職の目的は人それぞれです。転職理由・目的に関係なく汎用的に使える内容をまとめました。
大手企業と中小企業での仕事の違いを理解する
企業規模によって、担当する業務範囲に違いが出ることがあります。分かりやすくSIerを例に取ると、大手SIerはいわゆる上流工程であるインフラの要件定義や設計部分が主な業務になり、中小SIerでは設計に沿ったネットワークの構築や運用保守が主な業務になります。
大手になるとディレクションやマネジメント業務が主になるため、エンジニアとして幅広い構築経験を積みたい希望があれば中小SIerの方がおすすめです。このように、仕事内容の違いを理解することで転職活動の方向性も固まりやすくなります。
職務経歴書の書き方
職務経歴書には自身の業務経験やスキル(機器・OS・ツールの習熟度など)を書きますが、インフラエンジニアはその特性上、ほかの開発系エンジニア職より「運用」がフォーカスされやすいです。
そのため業務内容をまとめる際には、運用におけるトラブル対応の経験や業務フローの改善などを中心にピックアップするのがベターでしょう。ただし、上流工程を希望する場合はこの限りではありません。
関連記事:SE(システムエンジニア)の職務経歴書の書き方とテンプレート
志望動機・転職理由の書き方
志望動機・転職理由をまとめる際には、以下の4つを押さえるようにしましょう。
-
・今の会社から転職する理由
・その会社を志望した理由
・入社後に働くイメージ
・インフラエンジニアとしての将来像
キーワードは「一貫性」です。たとえば、「スキルアップしたいから」が今の会社から転職する理由なのに対し、その会社を志望した理由が「社会貢献性が高い事業に共感した」であれば、採用担当者に「無理に作られた理由なのでは?」という印象を与えてしまう可能性があります。
関連記事:インフラエンジニアの志望動機はどう書く?
面接対策
基本的にはほかの職種と大きな違いはありません。志望動機や転職理由、これまでの経験などの質問を通して「当社で活躍できる人材かどうか」を見極められることになります。
質問の傾向は会社ごとに違うため、レバテックキャリアでは各社ごとの事前に面接対策などをお伝えしています。面接対策ができるのは、転職エージェントを使うメリットのうちの1つです。
レバテックキャリアの転職支援サービスについて
インフラエンジニア転職で採用担当者が見るポイント
その求人で求めるレベル感(初級~中級レベル、上級レベル)によって、採用担当者が見ているポイントが異なります。しかし、インフラエンジニアは比較的市場に人材が流れてこないため、求めるスキル要件への一致度合いに関してはある程度緩和している企業も多いです。
その場合において、採用担当者が重視するポイントは「未経験の技術への習得意欲や習得速度」です。例えば、クラウドサービスでもAWSやAzure、Google Cloudなど複数あり、データベースではOracle Database、Microsoft SQL Server、MySQLなど複数の製品が存在します。1つのサービスや製品しか扱えないというのではなく、未経験の製品や技術に対しても積極的に取り組む意欲が求められます。
上記を踏まえ、「オンプレミスの経験しかないが、クラウドへの対応は問題なさそうか」「ホスト型の仮想化基盤の経験しかないが、コンテナに対する知見はあるのか」などが技術的な質問として聞かれることがあります。
求人内容をよく読み、企業が求めるスキルセットと乖離があった場合には、「どのようにして埋めるのか」「乖離をカバーできるようなエピソードはないか」といった準備をしておきましょう。
転職エージェントを活用するのも有効な手段
インフラエンジニアに転職するには、転職エージェントを活用するのがおすすめです。転職エージェントとは、キャリアアドバイザーが転職活動全般をサポートしてくれるサービスです。無料で利用できるので、いくつサービスを利用しても金銭的な負担はありません。
転職は希望の求人を探したり、履歴書や職務経歴書を準備したりと、多くの作業を行わなければなりません。働きながらやるとなると転職活動の時間が取れず、思うように転職が進まないという人もいるでしょう。
転職エージェントを利用すれば、一部の作業を代行してもらえたり、困ったときにアドバイスをもらえたりするなど、多くのメリットが得られます。インフラエンジニアのような、IT業界に特化した転職エージェントもあります。ぜひ転職エージェントの活用を検討してみると良いでしょう。
転職エージェント利用のメリット
転職エージェントを利用すると、面接対策や履歴書・職務経歴書の添削などをしてもらえるメリットがあります。どれも転職の際に必要な情報ですので知っておくと役立つでしょう。ぜひ参考にして活用してみて下さい。
非公開求人も紹介してもらえる
非公開求人とは、一般公開されていない求人案件のことをいいます。たとえば、誰もが知っている人気企業の案件や、重要プロジェクトの案件など、企業側にとって応募が殺到すると困るような案件があります。このような求人は、転職エージェントの紹介をはじめ限定された手段でしか知ることができません。転職エージェントとしても、その求人にできるだけマッチする人に対して紹介します。
そのため、より多くの求人から希望の求人を探したいなら、非公開求人も可能な限り見るべきです。転職エージェントを利用すれば、非公開求人を紹介してもらえます。
面接対策を実施してもらえる
採用面談にあまり自信がない人もいるでしょう。キャリアアドバイザーに相談すれば、面接対策を実施してもらえます。たとえば、面接時に想定される質問とその答えを事前に準備したり、採用面談時に知っておくべき企業の内情などを教えてもらったりして、自信をもって面接に望むことができます。
履歴書・職務経歴書を添削してもらえる
採用担当者の目を惹けるよう、履歴書・職務経歴書の書き方のアドバイスや、添削を行ってもらえます。企業によっては面接の前に一次審査として書類審査を行っているところもあるため、資料をわかりやすく記載し、自分の能力をアピールすることはとても重要です。
企業との交渉や面接の日程調整を代行してもらえる
希望の求人が見つかったら、その企業との交渉や面接の日程調整を代行してもらえます。また、その際の調整も転職者にとってメリットがあるように調整してもらえます。自分自身で実施する必要がないので、その分の時間をほかの転職活動の準備に当てられます。
転職エージェント利用のデメリット
転職エージェントの利用はメリットが多いですが、デメリットもあります。「利用して時間を無駄にした」とならないためにも弱みも理解しておくことが大切です。以下で詳しく説明しているので、活用する前に参考にしてみてください。
担当キャリアアドバイザーによってサービスの質が変わる
担当のキャリアアドバイザーの能力によってサービスの質が変わります。場合によっては、相性が悪く上手くコミュニケーションが取れない可能性があります。自分の希望が伝わらず要求とかけ離れた求人が紹介されたり、担当者との調整が手間に感じたりすることもあるでしょう。十分なサポートが得られない場合は、担当者を変えてもらうことも可能です。
自分のペースで転職活動ができないこともある
転職エージェントもビジネスであるため、たくさんの求人を紹介してきたり、人気の求人に応募させようと急かしたりすることがあります。逆に転職時期を明確に決めていない場合は、求人紹介を後回しにされてしまい、思うように転職活動を進められないこともあります。
自分のペースで転職活動を行いたい人にとっては、デメリットに感じることもあるでしょう。このようなことを防ぐためにも、転職活動の計画をあらかじめ考えておき、キャリアアドバイザーに明確に伝えることが大切です。
転職エージェント利用の流れ

転職エージェント利用の流れは、以下のとおりです。
-
1. 転職エージェントに登録
2. キャリアアドバイザーとの面談(カウンセリング)
3. 求人紹介
4. 書類添削・模擬面接
5. 見学・面接
6. 内定・給与交渉・入社日調整
転職エージェントを利用するには、まず必要事項の登録を行います。これにはオンラインでの簡単な登録フォームの記入や、履歴書及び職務経歴書の提出が含まれる場合があります。
次に、担当者とのやり取りを経て、キャリアアドバイザーとの初回面談(カウンセリング)を行います。この面談では、キャリアの希望、スキルセット、転職の動機などが詳しく話し合われ、転職までのスケジュールを決めていきます。
その後、キャリアアドバイザーは面談で確認した要望や適性に基づいて、適切な求人を紹介します。求人が見つかれば、履歴書や職務経歴書のブラッシュアップのサポートを受けながら応募書類を提出します。エージェントは応募プロセスをサポートし、面接のアレンジメントも行います。採用面接の対策として模擬面接の実施や、面接での回答のアドバイスも提供されることがあります。
採用面接後はフィードバックが行われ、場合によっては条件交渉の支援も受けられます。内定が決まると、入社日の調整や退職手続きのアドバイスも受けられます。最後に、入社が決定したら、エージェントからのフォローアップサポートを受けながら新たな職場でのキャリアをスタートさせます。
転職エージェント選びのポイント
数多くの転職エージェントが存在していますが、自分に合ったものを選ぶことが重要です。相性の悪い転職エージェントを使うと、希望に合わない企業に就職することになったり、なかなか自分に合う求人に巡り合えなかったりするためです。エージェントを選ぶにはどうしたら良いのか、ここでは、転職エージェントの選び方のポイントを紹介します。
総合型・特化型のどちらか確認する
転職エージェントには、総合型と特化型があります。
総合型は、取り扱っている求人の業界・業種の幅が広く、求人案件数も多い特徴があります。そのため、とにかく大量の求人案件の中から希望の求人を探したい人や、異業種の転職を行う場合に向いています。
特化型は、その業界に特化した求人を扱っています。業界全体の動向や企業ごとの詳しい情報が入手しやすいです。キャリアコンサルタントもその道に詳しい人が多いため、自分が望む業界・業種が決まっている場合は、特化型がおすすめです。
非公開求人の多さをチェックする
転職エージェントによっては、取り扱っている非公開求人案件数を公開しているところもあります。取り扱っている非公開求人数は転職エージェントによって異なるため、できるだけ非公開求人数の多い転職エージェントを選択しましょう。
複数のエージェントを併用する
転職エージェントは1つしか使えないという決まりはなく、いくつ利用しても問題ありません。そのため、気になる転職エージェントがあったら、とりあえず登録しておきましょう。複数の転職エージェントを併用すれば、希望の求人が見つかる可能性も高まります。
インフラエンジニアの年収相場
レバテックキャリアの求人によると、インフラエンジニアの年収はおよそ300万~1100万と幅が広いです。その理由は、担当する業務や経験年数・保有するスキルによって変動があるからといえるでしょう。たとえば、未経験であれば300万円程度ですが、アプリ開発や構築・運用などの経験がある人なら500万前後、その経験が3年以上やリーダー経験がある人だとそれ以上の年収が見込めます。
インフラエンジニアの求人例をチェック
インフラエンジニアにどのような求人があるのかを知ることは、転職する際にとても役立つでしょう。業務内容や求められるスキル・経験、年収など求人から分かることがたくさんあるからです。ここでは求人例を紹介するので参考にしてみてください。
【業界】
IT・通信
ソフトウェア/インターネット
【業務内容】
インフラの設計から保守まで幅広く担当
インフラの設計をはじめ、構築、運用、保守、調査、分析などインフラ業務全般に携わっていただきます。
<具体的な業務内容>
・開発エンジニアとの連携によるインフラアーキテクチャ設計、運用、改善
・アプリケーションエンジニアとの連携によるアプリケーションビルドパイプラインの設計、構築
・CI/CD環境の構築、運用
・モニタリング環境の整備
・障害対応、ボトルネックの調査、改善
【求められるスキル・経験】
・AWSを用いたインフラ設計、構築、運用の実務経験
・Linux サーバーの設計、構築、運用の実務経験
・当社のミッション、ビジョンに共感していただける方
・会社とともに成長していく意欲がある方
【想定年収】
400~800万円
【福利厚生】
健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険/通勤手当/残業手当/慶弔休暇/年末年始/有給休暇有給休暇/服装自由/資格取得支援制度/社外研修費補助/ハイスペックPC支給
【勤務地】
東京都
インフラエンジニアに関するよくある質問
インフラエンジニアに興味がある方や転職を考えている方の中には、需要状況やキャリアアップに必要なスキルについて知りたい方が多いようです。ここではインフラエンジニアに関するよくある質問について回答しているので、似たような疑問をもつ方は参考にしてみてください。
Q1. インフラエンジニアの需要状況について教えてください
インフラエンジニアの需要は高く、今後もなくならない見込みです。クラウドサーバーへの移行によって、インフラエンジニアの仕事が減っていくという意見もあるのは事実です。しかし、AIやIoT、フィンテックなど新しい分野でのIT技術の活用が進み始めているので、ITの根幹を担うインフラエンジニアの需要はなくならないでしょう。
Q2. インフラエンジニアの年収レンジはどれくらいですか?
インフラエンジニアの年収は、経験年数や担当業務、保有しているスキルによって変動があり、およそ300万~1100万と幅が広いです。未経験であれば300万程度からのスタートですが、ネットワークやサーバーの設計、構築までできるとだいたい400〜500万円の年収ゾーンでの採用となります。AWSの構築ができると500万円以上の年収を提示されることが多く、高い評価を得られるでしょう。
Q3. インフラエンジニアのキャリアアップに必要なスキルは?
企業のシステム部門では、インフラエンジニアはネットワークからサーバー、データベースまで幅広く任されるケースが多いため、それぞれの知識・スキルが求められます。資格取得や、新しいプログラミング言語の勉強、クラウドサービスの知識やスキルの取得は役立つといえるでしょう。
まとめ
インフラエンジニアに対する需要は、引き続き一定水準以上が見込まれています。ITサービスの開発や改善は今後も活発に行われることが予想されるためです。しかし、インフラエンジニアに求められるスキルは変化してきているという点には注意が必要です。インフラ設計、構築のほか、クラウド、仮想化といった新たな技術トレンドを取り入れることが今後は必須となっていくでしょう。
インフラエンジニアへの転職を考える場合は、技術スキル、ヒューマンスキル、マネジメントスキルを習得し、設計などの上流工程へ参画すると高収入になりやすいです。資格の取得も転職においては有効に働きます。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通したキャリアアドバイザーが、年収・技術志向・今後のキャリアパス・ワークライフバランスなど、一人ひとりの希望に寄り添いながら転職活動をサポートします。一般公開されていない大手企業や優良企業の非公開求人も多数保有していますので、まずは一度カウンセリングでお話してみませんか?(オンラインでも可能です)
転職支援サービスに申し込む
また、「初めての転職で、何から始めていいかわからない」「まだ転職するかどうか迷っている」など、転職活動に何らかの不安を抱えている方には、無料の個別相談会も実施しています。キャリアアドバイザーが一対一で、これからのあなたのキャリアを一緒に考えます。お気軽にご相談ください。
「個別相談会」に申し込む
レバテックキャリアのサービスについて