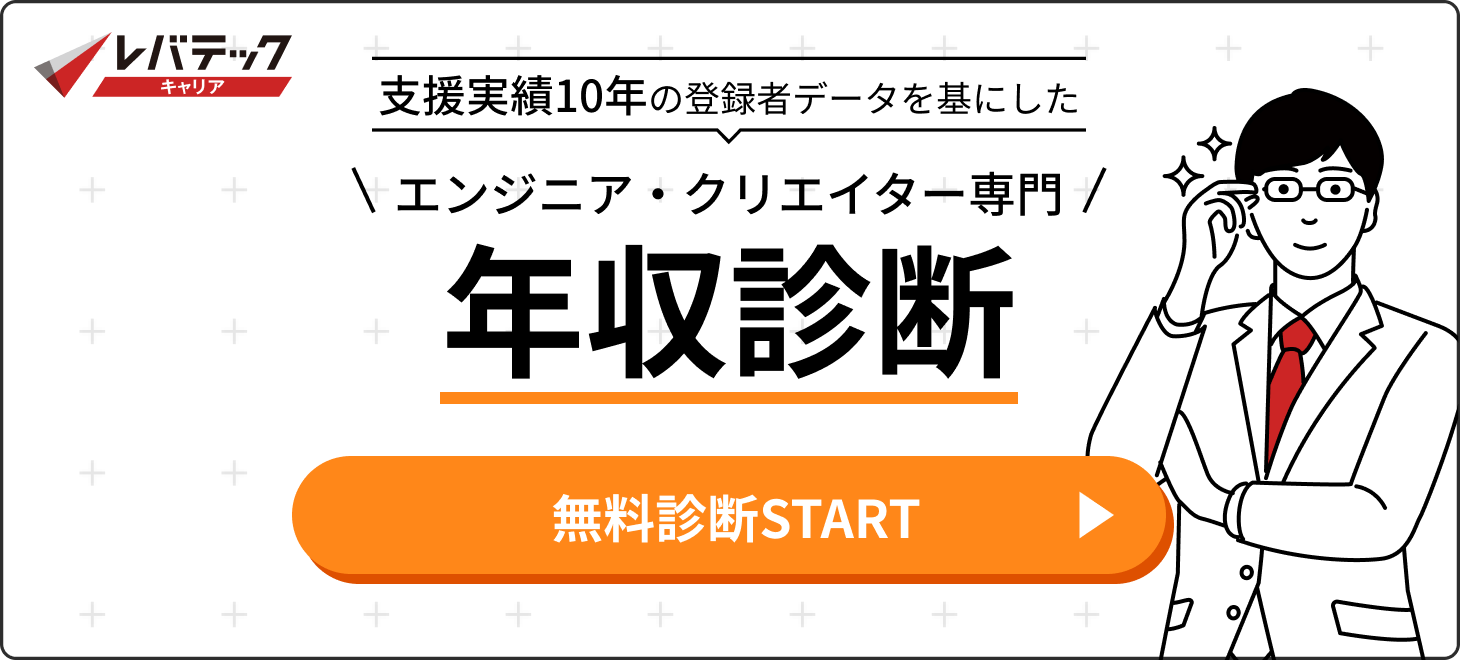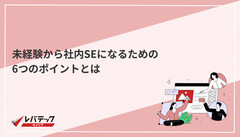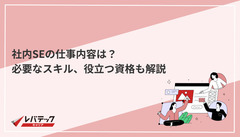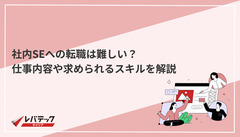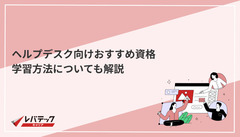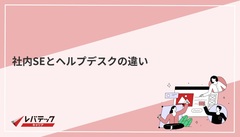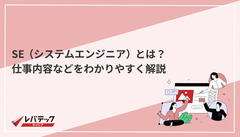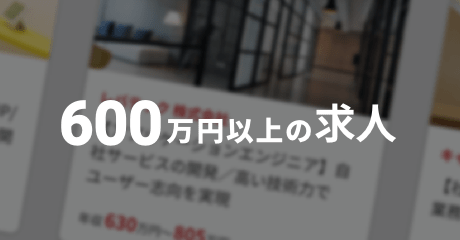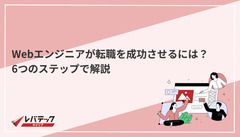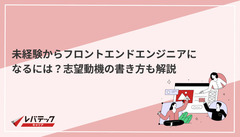社内SEの資格は主に4種類
社内SEの仕事は多岐にわたるため、関連する資格もさまざまです。社内SEの資格は主に、基礎知識の資格、技術系の資格、マネジメント系の資格、IT戦略・経営系の資格の4つのカテゴリーに分類できます。自分の携わっている業務やキャリアプランに沿って、取得したい資格を検討すると良いでしょう。
これらの資格は、業務の効率化やキャリアアップなどに役立ちます。ここでは、社内SEの資格について解説します。
1.基礎知識の資格
基礎的な資格は、IT全般の知識を幅広く身につけるのにおすすめです。社内SEを目指す方は、最初に基礎的な資格を取得することで、業務に必要な能力があることを証明できます。
また、日々の業務に直結する知識を身につけられることから、スキルアップにも役立ちます。これから社内SEを目指す方は、基礎的な資格取得を検討し、転職活動に活かしてください。
2.技術系の資格
技術的な資格は、専門性が高いIT技術に特化した資格です。プログラミングやネットワーク、サーバー、セキュリティなどの特定分野に関する高度な知識とスキルが求められるため、基礎知識の資格を習得後にチャレンジすると良いでしょう。
これらの資格を取得することで、社内SEとしての仕事の幅が広がり、昇進やキャリアアップにも有利になります。
3.マネジメント系の資格
マネジメント系の資格は、進捗管理や課題管理、リソース管理などプロジェクトを成功させるために行うさまざまなマネジメント業務に関する知識・スキルの習得に役立つ資格です。
マネジメント系の資格を取得することで、上流工程での意思決定や全体的な業務の管理・調整といったより高度な業務に携われるようになります。また、部下の育成やチーム全体の生産性向上など、マネジメントの実践力も身につけられるでしょう。
4.IT戦略・経営系の資格
IT戦略・経営系の資格は、マネージャーや経営層の視点を持ち、戦略の立案や実行に必要な知識・スキルの習得に役立つ資格です。最上流の業務を担当するには、単なるITスキルだけでなく、経営やビジネス全体に関する知識が求められます。社内SEとして上位ポストを目指すのであれば、このようなスキルの習得は欠かせません。
社内SEに関する基礎知識の資格
社内SEとして、必要な基礎知識を証明する代表的な資格を紹介します。まずは、ITパスポート試験の取得がおすすめです。その後は、基本情報技術者試験の取得を目指すと良いでしょう。基本情報技術者試験ではよりIT専門的な知識が試されるため、基礎知識をさらに深めることができます。
さらに上位の資格として、応用情報技術者試験もあります。エンジニアとしての経験を積み、よりスキルアップを目指したいときに挑戦すると良いでしょう。以下では、社内SEに関する基礎知識の資格を紹介します。
ITパスポート試験
ITパスポート試験は、ITの基礎の基礎を問う内容になっています。具体的には、情報システム、ネットワーク、データベースなどです。基礎と言ってもパソコンの使い方などよりは少し難しい内容になっています。
とはいえIT業界で働く人材として十分なレベルではないので、ITのことを知る最初の一歩の資格です。合格率は年度に寄りますが、受験者の50%〜60%程度が目安となります。CBT方式を採用したことにより、通年での受験が可能となりました。
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験はITエンジニアの登竜門ともいえる資格で、情報処理推進機構(IPA)が運営し、経済産業省が認定する国家資格です。令和5年度からCBT方式の採用により通年での受験が可能となりました。
令和5年度の受験者数は約14万7千人、合格者数は約5万7千人、合格率は約47%でした。試験の難易度としては中級から上級といえるでしょう。
IT業界未経験者にとっては専門的な内容も多く、プログラミングの基礎知識を試す問題も出題されるため、しっかりとした試験対策が求められます。科目Aは60問、科目Bは20問の選択式問題が出題される試験となります。
応用情報技術者試験
応用情報技術者試験も基本情報技術者試験と同様、情報処理推進機構(IPA)が運営し、経済産業省が認定する国家資格です。試験は毎年4月(春期)と10月(秋期)の2回開催されます。令和5年度春季の応募者数はおよそ3万2千人で、合格率は27.2%でした。
その名の通り基本情報技術者試験よりもワンランク上の応用力が問われる問題が多く、ITエンジニアとしてレベルアップを目指す人に最適な試験といえるでしょう。試験問題数は、午前が80問、午後が11問出題され、それぞれ150分の試験時間となっています。
社内SEに関する技術系の資格

基礎知識の資格より高度な知識とスキルを証明する資格として、特定領域に特化した試験も存在します。社内SEとしてさらなるスキルアップを目指す場合、技術系の資格の取得を検討するのが望ましいでしょう。
これらの試験は論述試験もあるため、実務経験を経てからの受験が一般的です。ここでは、社内SEに関する技術系の資格を紹介します。
システムアーキテクト試験
システムアーキテクト試験は、IPAの提供する高度な情報処理技術者向けの国家資格試験の一つです。システム開発の上流工程を主導する際に必要となる、要件定義スキル、システムのグランドデザイン設計スキル、アーキテクチャ設計スキルなどが問われます。社内SEとして上流工程に挑む際のスキルを示せる資格となります。
試験の開催時期は毎年4月の1回。令和5年度春季の受験者数はおよそ3,700人で、合格率は15.8%です。
ネットワークスペシャリスト試験
ネットワークスペシャリスト試験はIPAの提供する高度な情報処理技術者試験の一分野で、ネットワークエンジニアをターゲットとしています。ネットワークの設計や構築、運用、保守、セキュリティなど、ネットワークに特化して高度なスキルを問われる試験です。資格取得のための学習により、ネットワークエンジニアに求められる上流工程のスキルを身につけることができます。
社内SEはITインフラの管理を担当することも多く、業務の幅を広げることのできる資格となります。試験の開催時期は毎年4月の1回。令和5年度春季の受験者数はおよそ1万人で、合格率は14.3%です。
ORACLE MASTER
ORACLE MASTERは商業用データベースとして大きなシェアを持つオラクルデータベースに関するスキルと知識を認定するオラクル社によるベンダー資格です。DBAと開発者を主なターゲットとしており、一般的なSQLに関する知識からオラクル製品に特有の知識までが求められます。
CBT方式で提供されているため、通年で受験が可能です。Blonze、Silver、Gold、Platinumと多段階にレベル分けされているため、スキルにあわせてレベルアップを図れます。
社内SEは業務上データベースを扱う機会が多く、スキルは保有しておくにこしたことはありません。また、ORACLEを使っている企業への転職では、大きなアピールとなります。
CCNA
CCNAはネットワーク機器大手のシスコ社によるネットワークエンジニアとしてのスキルを認定するベンダー資格の一区分です。ネットワークエンジニアとして一般的なスキルとシスコ社製品の取り扱いに関する知識などが問われます。
シスコ社の認定資格には、エントリー、アソシエイト、プロフェッショナル、エキスパートのレベルがあり、さらに技術分野などにより資格が細分化されており、CCNAはその一つです。ネットワークに関する技術は社内SEとしても活用機会が多く、業務の幅を広げる資格となります。
CCNP
CCNPは、CCNAの上位資格として位置づけられている資格です。シスコ社の認定資格のなかで、CCNPは「プロフェッショナル」レベルの試験に該当します。
CCNPを取得することで、ネットワークの設計、構築、運用の各工程において、より高度な技術を持つことを証明できます。社内SEとしてキャリアアップを目指す場合、段階的にシスコ社の認定資格を取得していくことが望ましいでしょう。
LinuC
LinuCは、Linux技術者の能力を認定するLPI-Japanが運営する試験です。WebサーバーなどのITインフラには、Linux OSが多く利用されています。
そのため、Linuxスキルを証明するLinuCは、社内SEにとって役立つ資格といえるでしょう。LinuC
は、初級者向けのレベル1からエキスパートレベルのレベル3、さらに上位のLinuCシステムアーキテクト試験など、幅広い段階の認定制度があります。
初心者の方は、LinuCレベル1の取得がおすすめです。この資格を取得することで、Linuxの基本的な操作スキルや管理・運用に必要な知識を証明でき、社内インフラ保守や運用業務が可能になります。
さらなるキャリアアップを目指す場合は、上位レベルの取得も検討すると良いでしょう。
C言語プログラミング能力認定試験
C言語プログラミング能力認定試験とは、C言語の知識とスキルを証明する資格試験です。C言語は、組み込みシステムや業務システムなどの開発で活用されています。
この試験では、C言語の基本構文や変数・定数の利用方法、ライブラリ関数の活用などが問われます。C言語プログラミング能力認定試験を取得することで、社内システムの開発などに役立てることができるでしょう。
Javaプログラミング能力認定試験
Javaプログラミング能力認定試験は、Javaの知識やスキルを認定する資格試験です。Javaは、社内の業務システムやWebアプリケーションなど、幅広い分野で活用されている汎用的なプログラミング言語です。
この試験では、Javaの基本文法や制御構文、データ型などの問題が幅広く出題されます。Javaプログラミング能力認定試験は、初級レベルの3級から上級レベルの1級まで、段階的な試験区分が設けられているため、自分のレベルにあった試験への挑戦が可能です。Javaプログラミング能力の資格取得は、社内SEキャリアアップにも有効な選択肢といえます。
クラウドに関する資格
近年は企業がクラウドサービスを利用するケースが増加しています。従来のオンプレミスシステムをクラウドへ移行する取り組みが増えており、クラウド技術のスキルを身につけることで、社内SEとしての活躍の場を広げられるでしょう。
クラウドに関する資格としては、AWS認定資格やGoogle Cloud認定資格、Microsoft Azure認定資格が代表的です。以下では、これらのクラウドに関する資格を紹介します。
AWS認定資格
AWS認定資格は、クラウドサービスの代表格であるAWSの専門知識と運用スキルを証明する資格です。AWSはクラウド市場におけるシェアが最も大きく、企業のITインフラにも広く導入されています。AWS認定資格には、以下のようなレベルが設けられています。
-
Foundational :AWSサービスの基本的な知識を認定
Associate:AWSを使用してアプリケーションを設計する能力を認定
Professional:AWSをプロフェッショナルレベルで活用する高度なスキルを認定
Specialty:特定の技術分野で高度なスキルを認定
企業がAWSを採用・検討している場合、社内SEがAWS認定資格を取得していれば、AWSインフラの設計・構築・運用に大きな力を発揮できるでしょう。
Google Cloud認定資格
Google Cloud認定資格は、Google社が提供するクラウドサービスに関する専門知識と技術力を証明する資格制度です。この資格を取得すれば、Google Cloudの知識やスキルがあることをアピールできます。Google Cloud認定資格には、以下のようなレベルが設けられています。
-
基礎的な認定資格:Google Cloudのサービスや機能に関する基本的な知識を証明します
アソシエイト認定資格:Google Cloudを使ったシステム開発や運用に必要な知識を証明します
プロフェッショナル認定資格:Google Cloudを用いたシステムの設計、実装、運用、保守に関する高度なスキルを証明します
社内SEがGoogle Cloud認定資格を取得することで、社内のラウド戦略の策定や、Google Cloudを活用したシステム構築、運用管理などの場面で活躍できるでしょう。
Microsoft Azure認定資格
Microsoft Azure認定資格は、Microsoftが提供するクラウドプラットフォーム「Azure」に関する知識とスキルを認定する資格制度です。Azureでは、AI開発やDevOps(開発および運用サービス)、ストレージなどのサービスが提供されています。
社内SEがMicrosoft Azure認定資格を取得することで、Azureを活用したシステム構築や運用管理などに役立てられるでしょう。自社のクラウド戦略に合わせて、Microsoft Azure認定資格の取得をおすすめします。
サイバーセキュリティに関する資格
ITの活用が進む中で、サイバーセキュリティの重要性も増しています。そのため、社内SEにもセキュリティ対策の知識とスキルが必要とされるようになりました。サイバーセキュリティの知識を身につけるには、サイバーセキュリティに関する資格の取得がおすすめです。
サイバーセキュリティに関する資格としては、情報セキュリティマネジメント試験や情報セキュリティ管理士認定試験、情報処理安全確保支援士試験などが存在します。ここでは、サイバーセキュリティに関する資格を紹介します。
情報セキュリティマネジメント試験
情報セキュリティマネジメント試験は、組織の情報セキュリティに必要な基礎知識を認定する国家試験です。この試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主催しています。
この資格を取得することで、セキュリティ対策に関する基本的な知識を習得していることを証明できます。情報セキュリティマネジメント試験は、CBT形式を使った科目Aと科目Bの2部構成になっており、年間を通じて随時受験が可能です。
情報セキュリティ管理士認定試験
情報セキュリティ管理士認定試験は、一般財団法人 全日本情報学習振興協会が主催する、ITを利用するすべての人を対象とした基礎的なサイバーセキュリティの資格試験です。この試験では、主要なセキュリティの脅威とその対策、コンピューター基本知識、情報資産の保護管理技術などが問われます。
情報セキュリティ管理士は基礎レベルの資格と位置づけられているため、合格後はさらに上位のサイバーセキュリティ資格の取得を目指すことをおすすめします。
情報処理安全確保支援士試験
情報処理安全確保支援士はIPAが運営し、経済産業省が認定する国家資格、情報処理技術者試験の一分野で情報セキュリティのスペシャリストを対象としています。試験に合格すると制度に登録することができ、対外的なアピールとしても大きな資格です。
社内SEが本資格を保持することで、企業はビジネスの相手にセキュリティ対策の万全さを知らせることができるため、大きな価値を持つ資格といえます。
試験の開催時期は春期と秋期の年2回。令和5年度秋期の受験者数はおよそ1万2千人、合格率は19.7%でした。午前二部(午前Ⅰ50分、午前Ⅱ40分の多岐選択式)、午後(150分論述式)の試験形態です。
その他ベンダー試験
各種IT製品やソフトウェアに特化した認定資格試験は、各ベンダーから数多く行われています。これらのベンダー資格は、特定の製品やプラットフォームの専門知識と実践力を証明するものです。
ベンダー資格というだけで、マイナーな印象を持つ方もいますが、市場シェアの高い主要製品の資格を取得していると、高い評価を得られる傾向があります。ニーズの高い製品の認定資格を取得することで、社内SEとしての信頼性と専門性を高めることが可能です。自社のIT環境に合わせて、ベンダー試験の取得をおすすめします。
社内SEに関するマネジメント系の資格
社内SEとしてキャリアアップし、リーダー職以上を目指すにはマネジメントスキルが必須です。また、社内SEにとって社内で利用・提供しているシステム・サービスのマネジメントも重要な業務であり、その提供レベルを高めるための資格も存在しています。
ここで紹介する資格を活用して、マネジメントスキルの習得を目指しましょう。
プロジェクトマネージャ試験
プロジェクトマネージャ試験はIPAが運営する国家資格試験で、プロジェクトマネジメント全般に関する深い知識を問われます。習得のための学習により、進捗管理、リソース管理、課題管理、リスク管理、品質管理など幅広い領域の知識を身につけることが可能です。
試験の開催時期は毎年秋期の1回。令和5年度秋期の受験者数はおよそ7,900人で、合格率は13.5%でした。難関資格として知られていますが、社内SEにとっても社内開発でのプロジェクトマネジメントや外部に開発を委託する際のベンダーコントロールで役立つため、評価は高いです。
PMP®試験
PMP®試験はPMI協会が運営するプロジェクトマネジメントスキルを証明する資格です。PMBOKと呼ばれるグローバルスタンダードのプロジェクトマネジメント手法がベースとなっており、海外でも通用する資格です。IT以外のプロジェクトマネジメントでも評価されます。
合格率は公表されていませんが、60〜80%程度と言われています。また、合格後、継続的な活動が資格の維持には必要となります。
PJM-A試験
PJM-A試験はPMO協会が運営するプロジェクトマネジメントの基礎知識を証明する資格です。プロジェクトマネージャ試験やPMPと比較して難易度が低いため、はじめてプロジェクトマネジメントを学習するエンジニアに向いています。
試験の開催時期は随時。合格率は非公表ですが、正解率75%で合格でき、難易度は低めです。
PMO認定スペシャリスト
PMO認定スペシャリストはPMO協会が運営する、PMOに求められる知識を証明する試験です。PMOとは、自社などの組織内におけるそれぞれのプロジェクトを横断してマネジメント支援することで、会社全体のプロジェクトの成功率を高める職種です。社内SEはプロジェクトマネジメントスキルも必要な職種のため、応用スキルの習得を目的に学習してみても良いでしょう。
試験の開催時期は随時。合格率は公表されていませんが、20%程度と言われています。
社内SEに関するIT戦略・経営系の資格
社内SEとしても最上流の業務として、IT戦略、IT企画の立案があります。IT戦略スキルは、IT部門長やCIOなどを目指す上で必須のスキルです。
社内SEに関するIT戦略・経営系の資格には、ITストラテジスト試験やITコーディネータ試験、日商簿記2級、中小企業診断士試験が挙げられます。本項では、IT戦略、企画立案に関するスキル習得に役立つ資格を解説します。
ITストラテジスト試験
ITストラテジスト試験はIPAが運営する国家資格試験で、IT戦略やIT企画を立案するスキルが求められます。具体的には、情報技術を活用した事業戦略の策定、情報技術を活用したビジネスモデルの策定、情報システム戦略の策定、システム化計画の策定、システム調達などが出題されます。経営視点の習得に役立つでしょう。国家資格の中でも難易度は高めです。
試験の開催時期は毎年4月の1回。令和5年度春季の受験者数はおよそ5千人で、合格率は15.5%です。
ITコーディネータ試験
ITコーディネータ試験は特定非営利活動法人ITコーディネータ協会が主催する試験で、IT戦略の策定やIT戦略に基づいたプロジェクトの立ち上げ、プロジェクトマネジメントに関する知識を問われます。試験合格者は、6日間の研修を通してスキル定着を図る仕組みとなっています。
試験の開催時期は公式サイトにて告知されており、期間中であればいつでも受験可能です。公式サイトでは参考値として、合格率は60〜70%と発表しています。
日商簿記2級
日商簿記2級は、簿記試験のなかでももっとも王道の資格試験と言えるでしょう。日商簿記3級だと実務レベルとしてはやや不足していて、逆に日商簿記1級になると難易度が飛躍します。日商簿記1級は会計士や税理士を目指す人レベルの試験と言えます。
日商簿記2級は会計や税務を本業としない職業の人が実務レベルで活用するのにちょうど良いレベルの資格試験です。経理や事務の担当者が取得するケースも多いです。
試験の開催時期は統一試験は毎年3回、ネット受験は通年(受験会場による)で受験が可能です。令和6年2月の統一試験では受験者数はおよそ8700人で、合格率は15.5%です。
社内SEにとっても社内の入出金を管理する会計システムなどの構築、運用に役立つ資格です。
関連記事:社内SEが簿記を取得するメリットは?勉強方法なども紹介
中小企業診断士試験
中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応する診断・助言を行う専門家向けの国家資格です。一般社団法人中小企業診断協会が試験運営をしています。社内SEとして、所属企業の事業改善に役立つ提案、企画をする上で、役立つ資格となります。
例年一次試験は8月、二次試験は10月に行われます(事前に申し込みが必要)。その後、実務補習や養成課程を経て登録に至ります。一次試験は全7科目あり、各60%以上、40%未満が一科目もないことが合格基準です。
社内SEの仕事内容

社内SEの仕事内容は、所属する企業によって異なります。社内SEの仕事としては、社内システムの構築や運用・保守が代表的です。
また、社内ヘルプデスクとして自社社員からの問合せ対応を行うこともあります。さらに、経営戦略の実現や実行のためにITの企画を行うことも、社内SEの仕事の一つです。ここでは、社内SEの仕事内容について解説します。
関連記事:社内SEの仕事内容とは?必要なスキル、役立つ資格も解説
社内システムの構築・運用・保守
自社の業務を支援するシステムの構築、運用、保守を行います。対象は、業務システムなどのソフトウェア、ミドルウェア、ネットワーク、サーバー、PC、複合機など多岐に渡ります。企業やプロジェクトによっては外注し、社内SEはベンダーマネジメントのみを行う場合もあります。
PCやスマートフォン、タブレットなどの各種デバイス、ソフトウェアといったIT資産の管理も業務に含まれるケースも多々あります。
問合せ対応 (社内ヘルプデスク)
社内システムやパソコンの使い方などのヘルプデスクとして、社員からの問合せに対応します。IT機器に関するトラブルや利用者のサポートまで業務対象とすることもあります。
関連記事:社内SEとヘルプデスクの違い
IT企画
経営戦略の実現・実行のためにITを活用してどのような施策を行うか立案します。具体的には、社内課題の整理や課題解決アプローチ、予算策定、投資対効果の算出、プロジェクトの進め方などの調整を行います。
また、社内の業務部門と連携し、業務の効率化、改善、変革に向けたITの活用を考えるケースもあります。現場主体のIT立案に対しても、協力するポジションです。
社内SEとSEの違い
社内SEもSEも、ITを活用して課題を解決し、業務を改善することでメリットを生み出す仕事です。その違いは、業務対象となるクライアントが社内か社外かという点です。
この業務対象の違いが業務への関わりかたの違いとしてあらわれます。社内SEはシステムに対し、企画段階から設計、開発、テストを経てリリースし、その後の運用まで一貫して担当するケースが多いです。一方で一般的なSEはクライアントから請け負ったシステム開発プロジェクトの一部を担当し、作業工程により従事するプロジェクトが変わることも珍しくありません。
また、その成果も社内SEはシステム開発による業務への貢献などが評価されます。SEはプロジェクト単体でのQCDが評価対象となり、その後の運用やクライアント業務への貢献は重視されません。
関連記事:
社内SEとSEの違い|仕事内容や必要スキルを徹底比較
社内SEが「人気・勝ち組の職種」と呼ばれる9つの理由
社内SEのメリット・デメリット| 院内SEも含めて解説
社内SEが「楽な職種」と言われる5つの理由
社内SEが資格を取得するメリット
社内SEが資格を取得することには、さまざまなメリットがあります。具体的なメリットとしては、体系的な知識の習得とスキル向上が見込める点が挙げられます。
これにより、キャリアアップや資格手当により年収が上がる可能性があることもメリットの一つです。また、取得した資格は技術の証明となり、転職市場での競争力を高める助けにもなります。ここでは、社内SEが資格を取得するメリットについて解説します。
体系的知識の習得とスキル向上が見込める
資格を取得するためには、資格試験に向けた学習が必要となります。これは、日々の業務の中では整理しきれない技術的な情報を体系的に学習する機会です。
また、座学的な学習だけではなくプログラミングなどの演習も実施することでスキル向上も見込めます。
キャリアアップや資格手当により年収が上がることがある
資格の取得は明確なスキルの向上を示せ、所属組織内での評価にもつなげやすいです。スキルアップからキャリアの向上につながり、結果として年収の向上にも役立ちます。
さらには、所属する企業によっては資格の取得に手当てがつく場合もあります。こちらの面でも年収向上につながります。
関連記事:社内SEの将来性は?仕事内容や平均年収とキャリアパスも紹介
スキルの証明となり転職に役立つ
Tエンジニアとしての実力のすべてを資格で証明できるわけではありませんが、少なくとも一定のスキルの証明として資格取得は有効です。社内でのキャリアアップに役立つことはもとより、転職の際にも有用です。
社内SEとして働いていると、特定の企業文化でのみ有効なスキルも習得していきますが、これは社外と接する際に評価には繋がりません。転職時には現行業務に対する守秘義務も存在するため、保有スキルのアピールは難しくなりがちです。
保有スキルを第三者的な立場から証明してくれるため、転職でも有利に働く点が資格保有の大きなメリットの一つです。
関連記事:社内SEのキャリアパス|具体例やキャリアアップ転職のコツを解説
社内SEに必要なスキル
社内SEには、さまざまなスキルが求められます。社内SEに必要なスキルは、主に技術系スキルとそのほかのスキルの2つに分類されます。
社内SEがこれらを総合的に習得することで、企業の情報システム基盤を支える中核的な存在として活躍できるでしょう。ここでは、これらの社内SEに必要なスキルについて詳しく解説します。
関連記事:社内SEに必要なスキル|SEとの違いや役立つ資格も解説
社内SEの資格で証明できる技術系スキル
社内SEの仕事は、社内システムの設計や構築、保守など、ITスキルが必要です。社内SEの資格で証明できる技術系スキルとしては、プログラミングスキルや運用・保守に関する知識、システム開発に関する知識などが挙げられます。以下では、これらの社内SEの資格で証明できる技術系スキルについて解説します。
プログラミングスキル
社内SEにとって基本的なプログラミングスキルは必須です。直接自分がプログラミングを担当しないプロジェクトでも、プログラマーが開発したプログラムを理解できる程度のプログラミングスキルは身につけておきましょう。
運用・保守に関する知識
社内システムの運用や保守に関する知識も社内SEには求められます。特に基幹システムの運用保守は社内SEにとって、生命線と言えるでしょう。システムの専門家として、定期的なメンテナンスを行いつつ、トラブル発生時の対応など、会社の業務を円滑に進めるためにも、運用保守は重要な仕事です。
システム開発に関する知識
社内SEとしてはシステム開発に関する知識も身につけておきましょう。たとえばプロジェクトの開発手法だけでも、ウォーターフォールやアジャイルなどさまざまなものがあります。
基本情報技術者や応用情報技術者試験の勉強で基礎は身に付けられるため、しっかりと学習することをおすすめします。
社内SEに必要なそのほかのスキル
社内SEに求められるスキルは、技術的なスキルだけにとどまりません。社内SEに必要なそのほかのスキルとしては、問題分析や解決能力、プレゼンテーションスキルが挙げられます。
さらに、多くのステークホルダーと関わるため、コミュニケーション力も欠かせません。また、マネジメント力も求められます。そして、柔軟な対応力や課題発見・解決力も重要なスキルです。以下では、社内SEに必要なそのほかのスキルについて解説します。
問題分析、解決能力
社内SEとして最も優先すべき事項は企業の利益追求です。現行システムはそのために導入されており、システムの停止は業務の停止にも繋がり、企業利益の損失も発生しかねません。そういった意味で、現行システムを継続的に稼働させることは社内SEの重要ミッションなのです。
しかしながら、定常業務の中でもシステムの問題は発生しえます。ハードウェアトラブルや連携先の問題、特異なデータの発生など、いつどのような問題が発生するかは予測不可能です。
いざ、問題が発生した場合に、分析を行い、問題を取り除いて現行業務を復帰させる課題解決のスキルが重要となります。もちろん、自分だけで解決するわけではなく、必要な方面からの助力を得て問題の解決に最適な行動を行うことが最重要視されます。
プレゼンテーションスキル
社内システムの提案をする上で、社内SEにはプレゼンテーションスキルが欠かせません。システムに必要な機能やコストを適切に把握して、開発に関わるスタッフの協力を得るためには、自分の提案をわかりやすく伝えて理解してもらうことが大切です。
要点をまとめて簡潔に話すことを習慣にしていれば、大規模なプレゼンテーションを成功させやすくなるでしょう。プレゼンテーションのための資料作成も重要なスキルの一つです。
コミュニケーション力
社内システム開発のプロジェクトを円滑に進めるためには、ほかの社員や外注先とスムーズにコミュニケーションを取れるスキルも欠かせません。社内システムのトラブルや、ほかの社員からヘルプを求められたときに、システムの状態やヘルプの内容などをヒアリングして適切に理解するためにも、コミュニケーション力が重要です。
マネジメント力
社内SEにはマネジメント力も必要不可欠です。社内システムの開発では、プロジェクトを適切にマネジメントして開発を成功へと導きます。
小規模なプロジェクトから大規模なプロジェクトまで、参加しているスタッフの能力や性格、開発するシステムの目的や機能など、さまざまなことを考慮しながらマネジメントする力が求められます。
柔軟な対応力
システムのトラブルや社内のスタッフからの質問は予想もしていないときに起こりがちです。そのため社内SEには臨機応変に柔軟な対応力が必要です。複数の対応が同時に求められたときなどは、優先順位を素早く決めて、一つ一つ丁寧に対応することを心掛けましょう。
課題発見・解決力
継続的にシステムを利用して業務を行っていく中で、さらなる改善や効率化を目指すためには、業務を観察し課題を発見するスキルも必要となります。業務知識とITに関する知見を持った社内SEならではの視点で、システムとそれを活用した業務の課題を探します。
また、このような業務課題を見つけた場合には、その解決に向けた策を実施するスキルも大切です。即時に対応ができないような課題であれば、計画的にスケジューリングして解決まで導くことが求められます。
社内SEになるには
社内SEを目指すためには、必要となるステップがいくつか存在します。社内SEになるにはまず、現在の業務を通じて必要なスキルを習得することが重要です。
また、社内SEの仕事に関連する資格を取得して知識やスキルをアピールできるようにしましょう。転職エージェントへの相談も、効率的な転職活動を可能にします。ここでは、社内SEになる方法について解説します。
関連記事:
社内SEへの転職は難しい?仕事内容や求められるスキルを解説
社内SEになるには?求められるスキルや資格を解説
現在の業務を通じて必要なスキルを習得する
新卒で社内SEになるのは難しく、またいきなり社内SEを目指すケースも稀でしょう。現状Web業界やSIerで働いていて、そこから社内SEを目指している方が多いかと思います。社内SEとして転職するためには、Web業界やSIerで働いた経験が役立ちます。
面接では確実に前職で培ったスキルについて質問され、それが採用の重要な指標になるでしょう。そのため、今の仕事にしっかり取り組んでスキルを習得することは社内SEに転職する上でも重要です。
資格を取得してアピールする
IT業界で転職する際、資格は一つの指標になります。それは社内SEも例外ではありません。資格はもっとも客観的に能力がわかりやすい物差しなので、明確なアピール材料になるでしょう。
ただし実務経験やスキルよりも資格が重要というわけではないので、その点はご注意ください。実務経験、スキルに加えて資格を持っているとよりアピール材料になるということです。
転職エージェントに相談する
社内SEはIT業界全体の中で求人数が少ない傾向にあります。またその中でも、どの企業がベストなのか判断がつかない場合も多いでしょう。転職エージェントに相談すれば、非公開求人を紹介してもらえるメリットもあります。
社内SEになりたいのであれば、オープンになっている求人から応募するよりも転職エージェントに相談がおすすめです。
関連記事:社内SEの志望動機の書き方は?ポイントと例文も紹介
社内SEに関する資格を取得する際の注意点
社内SEが資格を取得する際には、いくつかの気をつけるべきポイントがあります。資格取得を目指すにあたって、具体的な目標と今のスキルを明確にした学習計画を立てることが重要です。
また、資格取得をキャリアアップへのステップとして位置づけ、キャリアプランを立てることも欠かせません。ここでは、社内SEに関する資格を取得する際の注意点について解説します。
目標と今のスキルを明確にした学習計画を立てる
社内SEが資格取得を目指す場合、自分の現在のスキルと目標を明確にした上で、しっかりとした学習計画を立てることが重要です。具体的な目標を設定することにより、学習過程でのモチベーションを維持しやすくなります。
また、自身のスキルを明確に理解することで、どの分野を強化すべきかを把握しやすくなります。資格取得に向けた効率的な学習を行い、合格を確実なものにしていくことが、社内SEとしてのキャリアアップにつながるでしょう。
キャリアプランを設計する
社内SEが資格取得を目指す際には、自身のキャリアプランを設計することが重要です。キャリアプランを設計することで、自分に必要な資格を効率的に取得できるようになります。
それにより、無駄な資格取得を避け、学習の効率化が可能です。また、キャリアプランとライフプランは密接に関係しています。キャリアプランを設計しておけば、突発的な出来事にも柔軟に対応できるメリットがあります。
社内SEに関するよくある質問
社内SEによくある質問としては、社内SEに役立つマネジメントや技術系の資格、必要とされるスキルについての質問が挙げられます。
また、未経験から社内SEを目指す方法や転職で採用される人の特徴についての質問も多いです。さらに、仕事のやりがいや魅力、難しさについての質問も多く寄せられます。
ここでは、社内SEについてのよくある質問と回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
Q1. 社内SEに役立つマネジメント系の資格は?
IPAが主催しているプロジェクトマネージャ試験、PMI協会が運営しているPMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)試験、PMO協会が運営しているPMJ-A(プロジェクトマネジメントアソシエイト)試験、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)認定スペシャリストなどがあります。
Q2. 社内SEにはどんなスキルが必要?
社内システムの開発をはじめ、社内のネットワークやサーバー構築、保守・運用、ヘルプデスクにいたるまで業務の幅は広いです。それぞれの業務に対応したスキルが求められます。企業によっても社内SEの定義は異なり、企業ごとに求められるスキルも変わります。
Q3. 未経験から社内SEになれる?
社内SEとしての業務がヘルプデスクや保守・運用がメインの場合は、未経験からでも従事することgが可能です。一方、システム構築や設計がメインの場合は、スキルや経験を積んだエンジニアのみを対象としている企業もあります。
関連記事:未経験から社内SEになるための6つのポイントとは
Q4. 社内SEの基礎能力を証明できる技術系の資格は?
IPAが主催している「基本情報技術者試験」と「応用情報技術者試験」が挙げられます。未経験から社内SEへの転職を目指す場合は、まずは基本情報技術者試験への合格を目指し、その後上位資格である応用情報技術者試験へ挑戦してみましょう。
Q5. 社内SEへの転職で採用されるのはどんな人?
採用される人の特徴は大きく分けて2つあります。
企業の社内システムでも開発が伴う業務の場合にはSIerなどに外注を行います。そのため、それらのプロジェクトをマネジメントできる人は採用されやすいでしょう。
また、社内SEは少数精鋭であることが多いため、幅広い業務に対応できる人が求められます。
Q6. 社内SEのやりがい・魅力は?
社内SEは、自ら開発に携わったシステムが成長・進化していく過程を体験できることが魅力の一つです。また、企業の直接的な貢献に結びつくやりがいを感じられるほか、企業の経営に関わる戦略的な仕事に携わることもできます。
Q7. 社内SEの難しさ・大変な点は?
社内SEの難しさの一つは、自身のITエンジニアとしての信念と、組織の一員としての責任が対立することにあります。そのため、技術力と組織マネジメントの両立をさせることが、社内SEの仕事には求められます。
まとめ
本記事では、社内SEの仕事に役立つ資格を基礎知識、技術系、マネジメント系、IT戦略・経営系の4つに分類して解説しました。
さまざまな資格がありますが、社内SEとして効率的にスキルアップするには、今の仕事に必要なスキルと今後のキャリアパスで必要となるスキルを見極めることが第一歩です。そして、資格試験を活用して効率的にスキルアップを図ってみましょう。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通したキャリアアドバイザーが、年収・技術志向・今後のキャリアパス・ワークライフバランスなど、一人ひとりの希望に寄り添いながら転職活動をサポートします。一般公開されていない大手企業や優良企業の非公開求人も多数保有していますので、まずは一度カウンセリングでお話してみませんか?(オンラインでも可能です)
転職支援サービスに申し込む
また、「初めての転職で、何から始めていいかわからない」「まだ転職するかどうか迷っている」など、転職活動に何らかの不安を抱えている方には、無料の個別相談会も実施しています。キャリアアドバイザーが一対一で、これからのあなたのキャリアを一緒に考えます。お気軽にご相談ください。
「個別相談会」に申し込む
レバテックキャリアのサービスについて