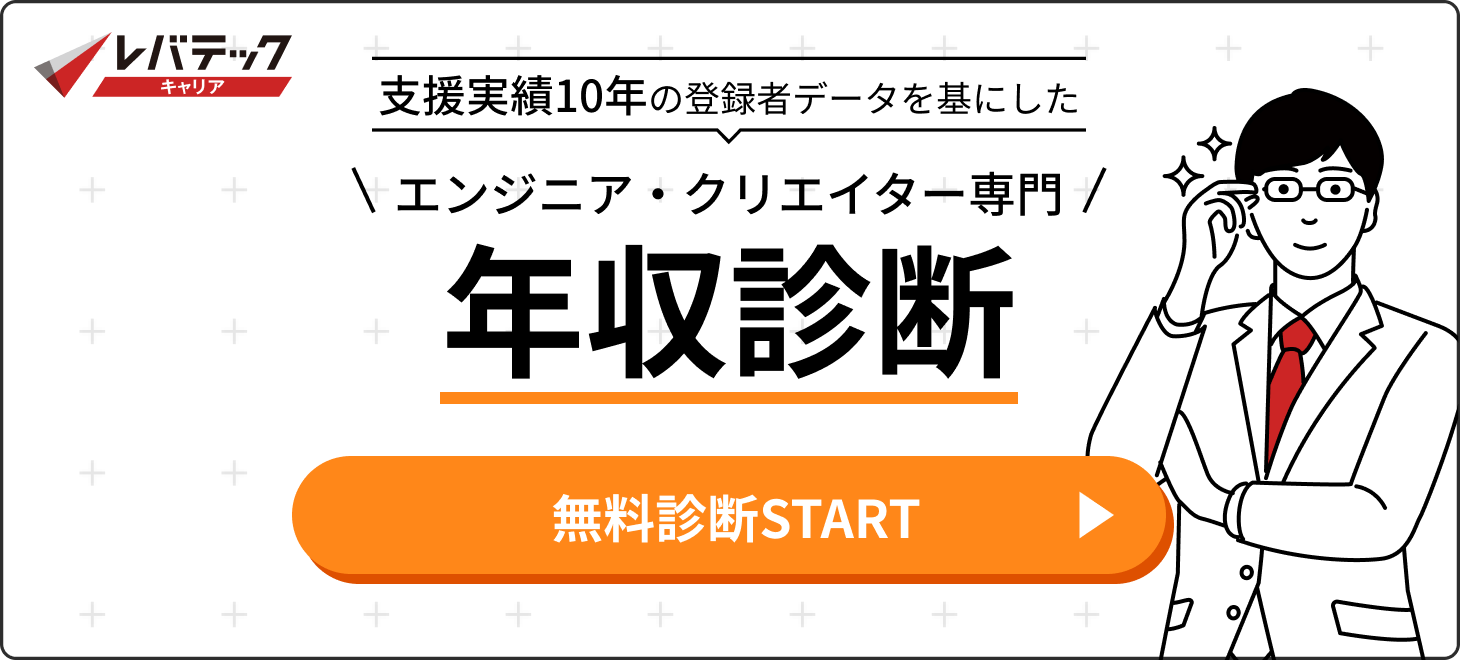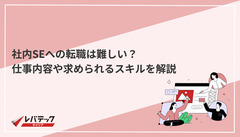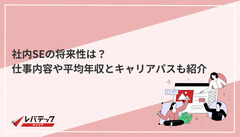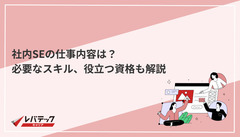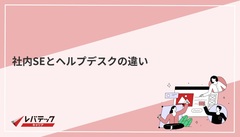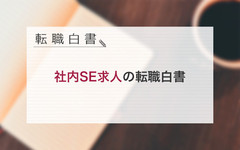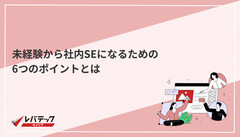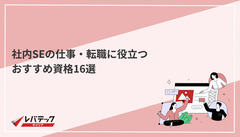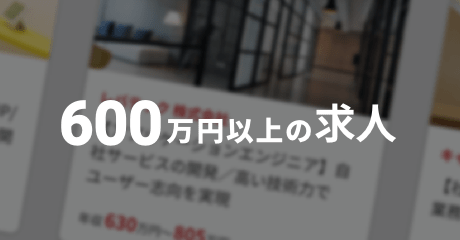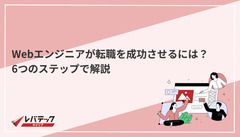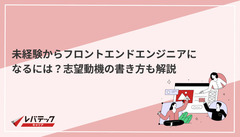社内SEは自社システムの開発や管理などの役割を担う

社内SEは、自社システムの構築や運用・保守、IT資産の管理といった業務を担当する仕事です。社内システムやパソコンに関連する業務だけに取り組むのが基本ですが、システムエンジニアの業務と大きく変わりません。社内システムの開発が行われる際は、社内SEが自ら開発に加わるパターンと開発を他社やフリーランスに外注(アウトソーシング)するパターンがあります。外注で開発を進める場合は、社内SEが進捗や品質を管理することがほとんどです。
働く場所によっては社内IT環境の予算の管理や、社員から来る社内システムやパソコンに関する問い合わせの対応、IT機器の故障時の不具合対応など、ヘルプデスクの役割を社内SEが担うこともあります。
関連記事:
社内SEの仕事内容は?必要なスキル、役立つ資格も解説
社内SEに必要なスキル|SEとの違いや役立つ資格も解説
SEやSES、SIとの違い

SE(システムエンジニア)は一般にソフトウェアの設計・開発に携わるエンジニアを指します。
社内SEもSES、SIに所属するSEもSEの範疇に含まれます。
SES(システムエンジニアリングサービス)やSI(システムインテグレータ)は、外部のクライアントからシステム開発を受注します。
それに対して、社内SEは自社の内部でシステム開発・システム運用に携わります。
社内SEの仕事内容

社内SEは、基本的には社内で利用する業務システムの開発や運用、管理を担当するIT技術者です。また、間接部門として企業のIT予算やIT資産の管理、業務効率を高めるための企画提案なども行います。
そのほかにも、社員から寄せられるシステムに関する問い合わせ対応や情報セキュリティ対策など、幅広い業務を担当します。よって、社内SEは技術力だけでなくコミュニケーションスキルやビジネス企画力も求められる職種です。
社内システムの開発における社内SEの仕事内容
続いて、社内SEの仕事内容を領域ごとに分け、それぞれの役割について解説します。まずは社内SEの開発業務である「社内システムの開発」における役割を説明します。
社内システムの評価、問題点の整理
社内システムの操作性や処理速度、コスト、不具合の発生頻度、各部門からの改善要求などを整理して改善するための評価を行います。
新システムの導入における方向性の提案
評価にもとづいて、新規に導入するシステムで改善したい問題点や、求められる機能を明確化し、関係者に提案して承認を取ります。
サービス、ベンダー選定
導入する製品・サービスの開発ベンダーを選定します。コンペを開催することも多く、労力の高い業務です。
予算計画の立案、予算管理
ベンダーの提案をもとに予算を算出し、社内で稟議を通します。このとき、予算はシステム導入にかかるコストだけでなく、その後のランニングコストも合わせて考えます。ハードウェアはリースやレンタルという手段もあるため、資産管理や設置場所なども考慮して様々なパターンで予算を比較検討します。
発注、進捗管理
契約時には企業とベンダーとの間でトラブルが起こらないように、法務部や弁護士の力を借りて契約内容を精査します。発注後は、ベンダーから進捗報告を定期的に受け、必要に応じて社内の関係者への報告会を開きます。作業の遅れや追加作業の発生時には、契約内容を確認しつつ必要な追加予算の確保や納期の調整も行います。
導入
受入試験を行い、品質確認ができれば社内PCへのインストールなどの導入作業を行います。
社内への周知、教育
システム導入後、新システムへの移行タイミングや利用方法について周知し、社内に教育の機会を設けます。まったく新しいシステムを導入する場合、管理者・ユーザーそれぞれのマニュアル作成も必要です。
ソフトウエア開発
企業によっては、ベンダーにハードウェアなど一部だけを発注しソフトウェア開発を社内リソースのみで行うケースもあります。
近年では、クラウド型の業務アプリケーションを導入するケースが主流で、自社で開発するケースは少数になってきています。自社で開発する場合は、この章で紹介してきた役割に加えて、要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、総合テストといった作業が発生します。
社内システムの運用における社内SEの仕事内容
次に、社内システムの運用における社内SEの仕事内容について詳しく説明します。社内SEは、運用方法の策定からマニュアル作成、そしてインシデントへの迅速な対応まで、多岐にわたる役割を果たします。
運用方法の立案・マニュアル作成
社内システムの利用方法や監視方法、メンテナンス方法などを立案し、具体的な方法をマニュアルに落とし込みます。社内の組織変更など、システム上の設定変更が多く生じる場合は、特に注意して運用計画を考えることが大切です。Wordなどで作成する場合もありますが、近年ではクラウド型のIT運用支援ツール(Q&A機能やインシデント管理機能、ファイル管理機能などを有するソフトウェア)で運用内容や操作方法を管理する方法が一般的です。
運用
マニュアルに沿ってシステムを運用します。具体的には、不具合発生時の応急対応やデータの復旧、サーバーの再起動、パフォーマンス監視などの作業を行います。企業によっては、社内SEは直接関与せず、ヘルプデスクに運用を任せる場合もあります。
インシデント発生時の対応
システム運用中に、ウイルスの感染やサイバー攻撃、そのほかのインシデントが発生した場合、応急対応や経営層への報告を行います。その後、原因究明や対応策を検討し、必要に応じてベンダーやコンサルタントに支援を依頼します。問題が収束した後は報告書を作って関係者に報告し、改善策の立案・実施を行います。社内SEはセキュリティの知識・スキルがあることが望ましく、インシデント対応では社内でリーダーシップを発揮することが必要です。
そのほかの社内SEの仕事内容
続いて、社内SEが担当するそのほかの業務について説明します。社内SEは、ITトレンドの学習・研究を行いつつ、ヘルプデスク、IT資産管理、IT予算計画の策定と管理など、様々な業務に取り組みます。
ITトレンドの学習・研究
社内SEは、社内の業務改善やコストダウンなどのために、最新のIT利活用を推進する立場です。そのため、展示会や情報誌でITトレンドや最新技術の動向を把握することが求められます。また、最新技術を把握するだけでなく、今後の潮流を見据えたスキル習得も大切です。
ヘルプデスク
業務システムやオフィス製品、OA機器などに関する社内からの問い合わせに対応します。ひとり情シスという言葉があるように、規模の小さい企業では社内SEがひとりしかいないために、システム開発から運用、ヘルプデスク対応まで行わなければならない場合も多々あります。一方で、年商が数十億円以上の企業では社内SEの業務が分業されているケースが多く、この記事で解説した役割すべてをひとりで担当するケースは稀でしょう。
IT資産管理
社内のサーバーやネットワーク機器、社用パソコンなどのIT資産を管理します。具体的には、IT資産額(5年償却が多いので毎年IT資産の状況が変わる)の集計や報告、インストールメディアやダウンロードコンテンツ、ソフトウェアのライセンスの割当状況、クラウドサービスのライセンス数や、保守契約の状況などを管理します。
IT予算計画の立案と管理
現行システムの維持に必要な予算、一時的に発生する保守費用やシステム開発に必要な予算を算出して予算計画を作ります。予算計画作成後は、経営層に次年度のIT計画と予算案を説明し承認を得ます。そして、承認された予算計画をもとに予算を執行し、日々の予算進捗状況を管理します。
関連記事:
社内SEの仕事・転職に役立つおすすめ資格12選
社内SEの将来性は?仕事内容や平均年収とキャリアパスも紹介
社内SEのキャリアパス・キャリアプラン例について
社内SEとSEの違い|仕事内容や必要スキルを徹底比較
社内SEに求められる知識・スキルとは
ここでは、社内SEに求められる知識・スキルとして以下の7つを紹介します。
-
・業務・業界に関する知識・スキル
・プロジェクトマネジメントスキル
・IT戦略の企画・立案に関するスキル
・社内システム構築ができるスキル
・社内システム保守運用に必要なスキル
・臨機応変に対応できるスキル
・セキュリティ対策への深い知識
それぞれの知識・スキルについて順番に説明します。
関連記事:社内SEに必要なスキル|SIに所属するSEとの違いや役立つ資格も解説
業務・業界に関する知識・スキル
システム開発・導入の主要な目的は、経営課題や業務課題の解決です。そのため、システム開発に携わる社内SEには業務知識の理解が求められます。
さらに、経営課題の解決策をシステムを通じて実現するには、自社が属する業界の慣習やビジネス環境を深く理解することも必要です。したがって、社内SEには業界知識も求められます。
プロジェクトマネジメントスキル
システム開発・導入は一般的にプロジェクト形式で進められます。したがって社内SEはプロジェクトマネジメントのスキルをもつ必要があります。プロジェクトを社内で完結させる場合であっても、外部にアウトソーシングする場合であっても、作業の進捗を管理したり、ステークホルダーと調整したりする役割は社内SEが担います。
IT戦略の企画・立案に関するスキル
社内SEになるとIT戦略の企画や立案を行います。具体的には、社内業務の改善や経費削減、効率アップなどの経営面を踏まえた社内システムを検討し、開発・導入するシステムの概要やスケジュール、予算などを企画案として作成し、経営層に提案します。IT戦略の企画・立案は、マネージャー以上の役職が担当することが多いです。
社内システム構築ができるスキル
社内システムを構築するのも社内SEの仕事になるため、構築に関する知識・スキルの習得も必須です。社内システムを導入する際には、どのようなシステムが必要なのかを調査・分析し、プロジェクトの企画から始まります。プロジェクトの企画が通ると、要件定義や設計、開発といったシステム開発の全工程で携わることになります。この際に、構築に必要なプログラミングスキルやITインフラ系の知識、UI/UXデザインの知識などが必要です。
社内システム保守・運用に必要なスキル
制作・導入したシステムの運用・保守に関するスキルも社内SEに必要なスキルのひとつです。社内システムの構築・導入の完了後や導入に関する業務がないときなどは、運用・保守の業務がメイン業務になります。主にサーバーやパソコン、ネットワーク、ソフトウェアなどの運用・保守を行い、システム障害の対策を講じる必要があります。システムやインフラ部分に関する知識、障害対応のスキル、コミュニケーション力といったスキルが必要です。
臨機応変に対応できるスキル
社内SEは突発的なシステムトラブルの対応や各種問い合わせ対応など、予定外の対応が求められる仕事です。そのため、あらゆる業務に対して臨機応変に対応できるスキルが必要になります。限られたリソースをどのように配分するか、リスクヘッジを踏まえた上でスケジュール管理が行えるかなど、不測の事態に備えた業務を遂行できる能力を身につけておきましょう。
セキュリティ対策への深い知識
社内システムのウイルス対策ソフトの導入やアップデート、不正アクセスの監視などのセキュリティ対策スキルも社内SEには必要です。多くの企業で社内の機密情報や顧客の個人情報などの重要データが保存されていますが、万が一これらの機密情報が流出してしまうと金銭的な損失や企業の信用問題に関わるなど大きなトラブルに発展します。このような事態にならないためにも、社内SEはセキュリティ対策に深い理解が必要です。また、社員向けにセキュリティ対策に関する通知や教育をする場合もあります。
関連記事:
社内SE転職の難しい部分と、目指したい人が身につけるべきスキル
社内SEが「人気・勝ち組の職種」と呼ばれる7つの理由
社内SEが「楽な職種」と言われる5つの理由
社内SEとヘルプデスクの違い
社内SEの将来性について

社内SEへの就職・転職を検討する際に重要なのが将来性でしょう。社内SEの将来性はあるのでしょうか?結論をお伝えすると、社内SEは今後も需要が高くなる職種だと予測でき、将来性があるといえます。
IT機器や自社システムなどを活用する企業が増えており、IT化は今後も進んでいく見込みです。その中で、IT環境の導入や開発、運用・保守を行う社内SEの仕事はますます重要性が高まります。
関連記事:社内SEの将来性は?仕事内容や平均年収とキャリアパスも紹介
多様性が重宝される
社内SEの基本的な仕事は自社システムの構築や運用・保守ですが、今後はより一層、幅広い知識やスキル、経験を活かした働き方が重宝されます。企業によっては、社内SEがヘルプデスクや社内インフラ整備などの業務を行うこともあるでしょう。このような多様性を身につけるには、自主的に幅広い知識やスキル、経験を得ることが必要です。他職種での業務経験や知識・スキルも上手く活用することで社内SEとして活躍していけるでしょう。
リモートワークの普及に伴い需要が拡大
多くの企業でリモートワーク化が進んだことにより社内SEの需要がますます拡大しています。しかし、リモートワークの採用にあたって課題もいくつかあり、中でもネットワーク環境の整備やパソコンやスマホなどの社用IT機器の確保・整備などは、多くの企業が課題としているところです。また、リモートワークに伴って、セキュリティ対策やクラウド活用などのIT環境の整備も重要性が高まっています。これらの課題解決を社内SEが担っていくことが予想でき、将来性は高いといえるでしょう。
社内SEのメリットとデメリット
社内SEになる場合にも、いくつかのメリット・デメリットが存在します。メリット・デメリットを踏まえた上で就職・転職をすることで、その後の後悔やミスマッチを減らせるでしょう。ぜひ参考にしてください。
関連記事:
社内SEのメリット・デメリット - 院内SEも含めて解説
社内SEが簿記を取得するメリットは?勉強方法なども紹介
社内SEのメリット
社内SEになるメリットには以下の4つが挙げられます。
・上流工程に携わることができる
・業務知識が身につく
・ベンダーマネジメントの知識が身につく
・業務システムの知識が身につく
一つずつ解説します。
上流工程に携わることができる
社内SEは自社システムの開発全般の業務に携わることになるため、企画の立案や要件定義などの上流工程から業務を行います。プロジェクトの上流工程に携わりたいと思う方には大きなメリットになるでしょう。また、上流工程ではプロジェクトの方向を決定したり、場合によってはクライアントと折衝したりと下流工程と比較して責任が大きいことから、給与面で優遇される傾向にあります。
業務知識が身につく
社内システムの開発・運用・保守に携わることから、自然と幅広い業務知識が身につきます。プロジェクトによって仕事内容は多岐に渡り、基幹システムやマーケティング、人事、生産管理などの知識が身につくでしょう。社内SEとして必要な業務知識を身につけると、社内での評価が上がりキャリアアップできることをはじめ、将来的にキャリアチェンジする際にも有利に働きます。また、ゼネラリスト的な働き方をしたいと思っている方にも利点といえるでしょう。
ベンダーマネジメントの知識が身につく
社内SEはITベンダーに発注する立場であるため、契約管理やパフォーマンス管理などのベンダーマネジメントの知識・スキルも身につけられます。ベンダーマネジメントはベンターのパフォーマンスを最大化し、プロジェクトを成功させることが目的です。プロジェクトを依頼したっきりで関与していないと、思ったような成果物に仕上がらなかったり、予期せぬトラブルに発展してしまったりといった事態を引き起こすことも想定されます。そのため、社内SEはベンダーと上手くコミュニケーションを取りながらプロジェクトをしっかり管理していくことが必要です。
ベンダーマネジメントの知識も、評価アップや就職・転職で有利に働くスキルになりますので、身につけることはメリットになるでしょう。
業務システムの知識が身につく
業務知識に付随して、基幹システムやグループウェア、会計パッケージなどの業務システムに関連する知識も身につきます。企業によっては、CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)などのマーケティング系のシステム開発や運用・保守にも携われることもあります。業務システムの知識を深めておくことで、ヘルプデスクの業務を行う際にも役立つでしょう。また、ここまで紹介したスキルや知識と同じく、習得しておくことで評価アップに繋がります。
社内SEのデメリット
一方、社内SEになるデメリットには以下の4つが挙げられます。
-
・企業次第で開発実務に携わることができない
・コスト部門とみなされてしまう
・ヘルプデスク業務になるケースもある
・開発をしたい人には物足りなさを感じる場合がある
メリットと踏まえて自分に合った職業なのか検討してみてください。
企業次第で開発実務に携わることができない
社内SEであっても働く場所によってはサーバー構築やプログラムの実装といった開発実務を外注しているケースがあり、開発に携われないことがあります。開発を外注している企業の社内SEの主な業務は、IT戦略の企画やマネジメントなどになります。開発まで担当したいと思っている方にとってはデメリットになるでしょう。社内SEとして自社システムの開発に携わりたい場合は、就職・転職を検討している企業で開発実務を外注していないか事前に確認しておくことを推奨します。
コスト部門とみなされてしまう
社内SEは企業の情報システム部門の担当者になるため、管理部門として扱われることがあります。つまり、企業に直接利益をもたらす部門ではなく、人件費が損益になるコスト部門とみなされてしまうということです。
コスト部門とみなされるデメリットには、営業や製造部門と比較して評価が上がりにくかったり、他部署と比べて賞与の割合が低かったりすることが挙げられます。年収や評価アップを積極的に狙いたいと思う方にはデメリットです。社内SEとして年収や評価アップを狙うのであれば企業規模が大きいほど待遇が良い傾向にあるため、そちらへの就職・転職を検討すると良いでしょう。
ヘルプデスク業務になるケースもある
企業によっては社内SEの数が非常に少なく、社内SEがヘルプデスクの業務も担うことがあります。自社システムの開発や上流工程に携わりたいと思う方にとって、ヘルプデスクの業務がメインになるのは不本意でしょう。特に、ヘルプデスクの業務はトラブル対応や問い合わせ対応など、ストレスを抱えやすい業務が多いです。人によっては仕事を続けるのが難しいと感じてしまうかもしれません。
ヘルプデスクとしての業務がまったくない企業は少ないかもしれませんが、自社システムの開発や運用・保守の業務をメインに仕事ができるかどうかは、働く前に確認しておきたいポイントです。
開発をしたい人には物足りなさを感じる場合がある
技術志向の人にとって、社内SEの仕事は退屈に感じるかもしれません。なぜなら、常に新しいシステムの開発に情熱を傾ける人にとって、社内SEの役割は多岐にわたり、時には雑多な作業も求められるからです。
社内SEは、社内システムに対して多面的なサポートを提供する必要があります。そのため、パソコンを初めて使う人に対して使い方を指導するなど、さまざまな業務に取り組むことがあります。
また、新規システムの開発に比べて、保守や運用管理にウェイトを置くこともあります。これらの要素を考慮し、自身が社内SEの役割に適しているかどうかを検討しましょう。
社内SEの平均年収について
社内SEに限った平均年収に関する公的なデータがないため、近いと考えられる厚生労働省が発表した『令和4年賃金構造基本統計調査』によると、システム・エンジニアの平均年収は約660万円です。平均年収は「(きまって支給する現金給与額)×12ヶ月+(年間賞与その他特別給与額)」で算出しています。
また、レバテックキャリアに登録されている社内SEの転職求人情報を見てみると、社内SEの年収は約400〜2,000万円と年収に大きな幅があります。経験やスキルによっては高年収も狙えるでしょう。
社内SEの求人例
ここでは、レバテックキャリアに登録されている社内SEの求人例をご紹介します。(2022年12月時点)
【想定年収】
400~1,600万円
【業務内容】
社内インフラや情報セキュリティに関する運用管理、ISO27001に関する業務、社員からの質問・相談への対応などの幅広い業務に携わっていただきます。
【具体的な仕事内容】
・社内のセキュリティリテラシー向上に向けた啓蒙や対策
・情報セキュリティ(ISMS)運用や各種規定の改定・改善業務
・既存システムの運用や改善業務
・社員からの要望に応じた新規システム導入
・各種インシデントに対する対応や改善業務 など
【求められるスキル・経験】
以下のいずれかの実務経験を1年以上お持ちの方
・インフラ(ネットワークやサーバー)設計・構築・運用・保守などの経験
・UTMなどのセキュリティシステムの設計・構築・運用・保守などの経験
また、問題解決のため現場へのヒアリングや調整相談など、コミュニケーションが円滑に取れる方を歓迎いたします。
未経験からの社内SEの目指し方
未経験から社内SEを目指すなら、基本情報技術者などのシステム開発の基礎知識を証明する資格を取得するのが有効です。社内SEへの転職にはITに関する知識やスキルを持っている方が有利です。資格を取得することで知識やスキルの証明になります。
また、経営層への提案やプロジェクト管理などの経験がある場合は、採用担当者に積極的にアピールしましょう。社内SEには情報システムの企画・開発において経営陣への提案やプロジェクトマネジメントスキルが役に立つ場面があります。
社内SEからのキャリアパス
社内SEからのキャリアパスとしては、リーダーやマネージャーへのキャリアアップやセキュリティエンジニア、ITコンサルタントなどへキャリアチェンジが挙げられます。
実務経験3年を目途として、自社に残る場合は管理職への昇進を目指すべきです。リーダーシップスキルを磨き、部門やプロジェクトのマネージャーとしての役割を担うことを目指します。また、転職・独立する場合、技術的スキルを磨きセキュリティエンジニア、ITコンサルタントへ転身を図ることができます。
リーダー、マネージャー、管理職などへのキャリアアップ
リーダーシップスキルを磨くことで、社内SEのリーダー職やマネージャー職に就くことができます。実際の業務での成果や同僚や上司からの高い評価がキャリアアップに繋がります。したがって、ITのスキルや知識と共にリーダーシップやマネジメントについて身につけることが大切です。
セキュリティエンジニア、ITコンサルタントなどへキャリアチェンジ
社内SEからセキュリティエンジニアやITコンサルタントを目指すこともできます。
セキュリティエンジニアの仕事は企業の情報資産を不正アクセスや情報漏洩から守ることです。自社の機密情報を守るという使命は社内SEと通ずるものがあります。したがって、セキュリティ関連のスキルを身につけてセキュリティエンジニアを目指すというキャリアパスは非常に有望です。
また、ITコンサルタントは顧客企業にITの効果的な活用に関するアドバイスを行う職種です。社内SEとして経験を積んで、システム開発やITプロジェクトを通じて経営問題を解決する能力を磨くことでITコンサルタントに転職することも可能です。
関連記事:
社内SEへの転職は難しい?仕事内容や求められるスキルを解説
社内SEになるには?求められるスキルや資格を解説
未経験から社内SEになるためポイントを紹介
社内SEの志望動機の書き方は?ポイントと例文も紹介
社内SEに関するよくある質問
社内SEへの転職を考えている方からよくあるご質問を紹介します。
仕事内容、SEとの違い、情シスとの違いなどについての質問が多いです。自分自身が疑問に思っていることに近い質問があれば、ぜひ参考にしてみてください。
Q1. 社内SEは何をする職種ですか?
社内SEは、自社のシステム開発や構築後の運用・保守、ITインフラの整備、ヘルプデスク業務などを行う仕事です。
社内システムの開発については、社内SEが自ら開発に携わるパターンと開発業務を他社やフリーランスに外注するパターンがあります。外注で開発を進める場合は、社内SEが進捗管理や品質管理を行います。
Q2. 社内SEとSEの違いは何ですか
SE(システムエンジニア)は一般にソフトウェアの設計・開発に携わるエンジニアを指します。
また、社内SEもこの定義に含まれます。
社内SEは、自社のシステム開発に従事するSEのことを指し、自社でのシステム開発に専ら携わります。
Q3. 社内SEと情シスの違いを教えてください
社内SEはエンジニアの職種で、情シス(情報システム部)は部署を表しています。
比較的大規模な企業では社内システムを管理する部署として情シスが設置されています。そこでは社内SEは情シスに所属しています。しかし、小規模な会社では情シスがなく、総務部などに所属している社員が社内SEの役割を担っているケースがあります。
まとめ
この記事では、社内SEの仕事内容や求められる知識・スキル、メリットとデメリット、将来性やキャリアパスなど幅広く解説しました。IT企業に勤めるSEと異なり、社内SEはシステム評価や改善立案、予算管理、ベンダーマネジメントなど上流工程に関する役割が多いという特徴があります。また、企業によってはECサービスの運用(画像やテキストのアップロード)やデジタルマーケティング、経営企画(ITを活用した改善提案やビジネス企画など)まで担うケースもあります。企業によって社内SEの業務内容は大きく異なるため、就職や転職をする際は求人情報をしっかり確認した上で応募してください。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。
「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。
「個別相談会」に申し込む
転職支援サービスに申し込む
※転職活動を強制することはございません。
レバテックキャリアのサービスについて