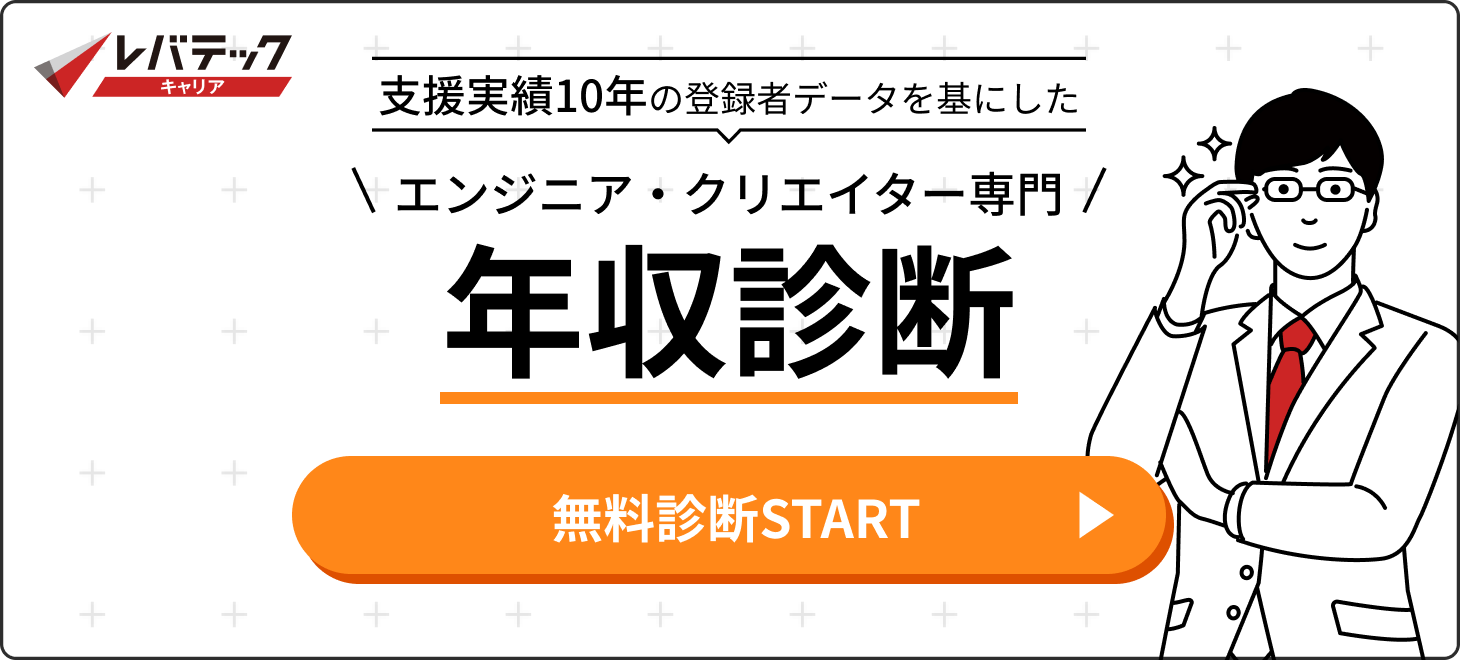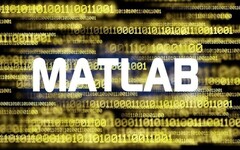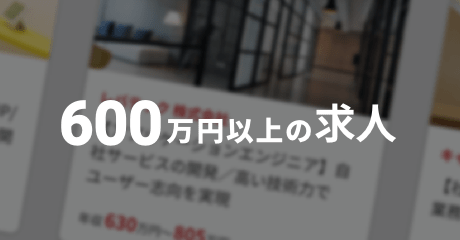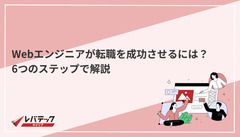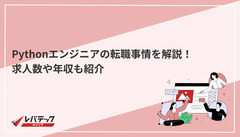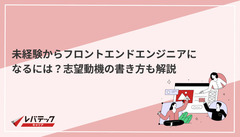SaaSとは
SaaS(サース)とはSoftware as a Serviceの略で、クラウド上でソフトウェアを稼働させて提供するサービスのことです。利用者はWebからSaaSにアクセスして利用できることが大きな特徴です。
従来のソフトウェアは、CDなどの物理媒体やデータのダウンロードとライセンスで販売されてきました。購入したソフトウェアはPC等のデバイスにインストール・起動して、ライセンスを入力して利用する形態が一般的でした。
SaaSでは、サービス事業者がソフトウェアをサーバーで稼働させ、ユーザーがインターネット経由で利用できるシステムを提供します。
ユーザーは、利用のための契約をすればすぐに使用開始でき、月額または年額で利用料金を支払う形式が一般的です。サブスクリプション契約により一定期間の利用に対し料金を支払い、利用者はソフトウェアを所有はしないことが従来のソフトウェアの購入とは大きく異なります。
クラウドの利用は年々増加しており、総務省の令和4年通信利用動向調査の結果ではクラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は72.2%で、前年70.4%から1.8ポイント上昇しています。継続的に上昇傾向にあり、上昇幅は狭まっているもののSaaSの利用は今後も増加が見込まれます。
SaaSとIaaS ・PaaSとの違い
クラウドサービスは提供するサービスの層により、SaaS、PaaS、IaaSに分けられます。この3種類以外にもXaaSと呼ばれるサービスが複数存在しますが、本項では最も一般的な3種類の間の違いについて主に解説します。
SaaSとIaaSの違い
IaaSとはInfrastructure as a Serviceの略で、システムに必要なサーバー・ストレージ・ネットワークなどのITインフラを、インターネットを経由して利用できるサービスのことです。
利用したいハードウェアのスペックやOSを、ユーザーが自由に選択して構成でき、拡張や縮小も簡単にできる特徴があります。
SaaSや後述するPaaSよりも自由度の高いサービス形態であり、言い換えれば、クラウド上にあるITインフラです。サービスレベルでの提供を行うSaaSとは提供するサービスの層が違うといえます。
SaaSとPaaSの違い
PaaSとはPlatform as a Serviceの略で、アプリケーションの実行に必要なプラットフォームを、インターネットを経由して利用できるようにするサービスのことです。具体的には、IaaSのサーバー・ストレージ・ネットワークなどに加えてOS、ミドルウェアなどがPaaSで提供される内容に含まれます。
PaaSを利用することにより、ユーザーは開発環境を構築する際にかかる手間を軽減できます。SaaSは、このIaaSやPaaSなどで構築したインフラ環境上にソフトウェアを構築して提供されるサービスという関係です。
そのほかの「〇aaS」
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| XaaS(X as a service) | SaaS、IaaS、PaaSなどのクラウド上で提供するサービスの総称です。EaaS(Everything as a service)、AaaS(Anything as a service)も同義語です。 |
| BaaS(Backend as a service、Banking as a Service) | Backend as a service モバイルアプリケーションのバックエンド処理を提供するクラウドサービスです。MBaaSとも呼ばれます。 Banking as a Service 金融機能を提供するクラウドサービスです。 |
| DaaS(Desktop as a service) | クラウドサービスを介して仮想デスクトップ環境を提供するサービスです。 |
| MaaS(Mobility as a Service) | 交通サービスに高度なIT技術を加えたサービスです。自動運転技術やAIによるアシスト、カーシェアリングなどが該当します。 |
| RaaS(Retail as a Service) | 小売業で生み出されたテクノロジーや仕組みを他の小売業でも利用できるように汎用的にしたものです。 RaaSはRobotics as a Service、Ransomware as a Serviceの略としても用いられることがあります。 |
SaaSのメリットとデメリット
クラウドサービスの登場から普及に至るまでの速度はとても早いものでした。クラウドサービスは多くのメリットを持ち、そのメリットがクラウドサービスの利用が拡大した理由とも密接に関係しています。その一方でデメリットも存在しています。
本項では特にパブリックなSaaSについてのメリット・デメリットを紹介します。
SaaSのメリット
SaaSのメリットには下記があげられます。これらのメリットはシステムやサービスを提供する上でSaaSという形態を選択する理由およびSaaSを業務に採用する理由としても、そのまま当てはまります。
スモールスタートができる
SaaSは、クラウド上のシステム規模を比較的容易に拡大できます。そのため、新規サービス立ち上げ時には小規模なシステムで開始し、需要の増加に応じて規模を拡大させることが可能です。これにより、新しく事業を開始する際のリスクを軽減できるというメリットがあります。初期投資を抑えて事業を始め、後々ビジネスを拡大するスタートアップにも向いています。
スピーディーなサービスの立ち上げやプロトタイプ作成ができる
SaaSは物理的なサーバー構築など、インフラの手配に関するリードタイムを省くことができます。サービス立ち上げまでの期間を短縮してスピーディーにシステムを開発したい場合や、ライトにプロトタイプを作りたい場合に適しています。
初期導入コストが低い
SaaSを利用する場合には、サーバーなどのハードウェアの購入、構築作業、ソフトウェアの購入・インストールが不要であり、初期導入コストを抑えられます。
利用料金はサブスクリプション型(月額や年額制)が多いため、従業員の増減が多い企業も導入しやすいでしょう。
保守管理の負担が少ない
人件費
SaaSを利用する場合は、自社でのシステムの保守管理は基本的に不要です。自社で保有するオンプレミスのシステムでは、インフラやソフトウェアの障害対応などを自社の情報システム部門で行うケースが多いですが、SaaSはサービスを提供する事業者が保守管理を行うため、人件費を抑えられます。
設備費
SaaSを利用する場合は、ハードウェアなどの設備を自社で持つ必要がありません。データセンターやサーバールームなどの設備が不要となり、空調設備や電気代も不要となります。ハードウェアの保守・メンテナンスなども不要となるため、設備に関する費用を削減できます。
常に最新機能を利用できる
クラウドサービスとして提供されるサービスは、基本的にサービス事業者がクラウド側でアップデートを行います。機能追加や新たに発見された脆弱性へのセキュリティアップデートもサービス事業者が随時行うため、利用者は常に最新機能を利用できる点もメリットです。
インターネットがあればどこでも使用可能
パブリッククラウドのSaaSの場合、インターネットを介してどこからでも利用することが可能です。企業の事業所内での利用に加え、外出先や自宅での作業などでも利用することができます。物理的なロケーションによる制限を受けずに、業務を行うことを実現できます。
幅広いデバイスで使える
Webブラウザから利用できるSaaSの場合、Webブラウザを持つ各種のデバイスで利用することが可能です。PCやサーバーに加え、スマートフォンやタブレットなどのブラウザでも同様に扱えます。インターネットを介してアクセスできるため、IoT機器などからの利用も視野に入れることができるでしょう。
大人数で同時作業が可能
SaaSは複数のユーザーで同一のデータに対するアクセスを可能としているケースが多いです。複数人で並行に作業を進める場合などでも、制約を受けずに利用することができます。大人数でリアルタイムに情報の共有を行うことができる点も大きなメリットとなります。
SaaSのデメリット
SaaSという形態をサービスの提供に選択する場合、業務上の機能をSaaSを利用して実現する場合には、その形態を理由としたデメリットも存在しています。メリットとトレードオフの関係となるデメリットが多いため、サービス提供の企画時や導入検討時には熟慮が必要です。
セキュリティリスクがある
SaaSではクラウド上のシステムを利用するため、データをサービス事業者に預けることとなります。このデータには、SaaSの利用の方法や活用範囲により企業の機密情報や顧客の個人情報なども含まれます。このため、自社ではコントロールできない範囲で不正アクセスなどが発生するリスクが存在します。
カスタマイズの自由度が低い
SaaSでは、多くの場合、個別カスタマイズよりも汎用性が重視されます。多数のユーザー向けに提供されているパブリッククラウドのSaaSの場合は、その傾向は顕著です。カスタマイズの自由度が低いため、サービスに合わせて業務の変更が求められるケースもあることはデメリットの一つとして認識しておきましょう。
通信障害の影響を受ける可能性がある
パブリッククラウドのSaaSを利用する場合、自社でシステムを持つ場合に比べて、通信障害の影響を受けやすい点もデメリットです。
パブリッククラウドにはインターネット経由でアクセスすることが前提です。利用している通信回線に障害が起こると、SaaSが正常に稼働していてもアクセスがしづらくなることがあります。
運用費(ライセンスコスト)がかかる
SaaSの多くは、アクセス数やユーザー数に応じた料金体系となっています。そのため、毎月運用費がかかるほか、事業拡大とともに運用費が上がることが懸念されます。自社でのシステム構築に比べてコストが高くなるケースもあるため、事前に綿密な試算が必要です。
SaaSの代表的なサービスとは

SaaSとして提供されるサービスは多岐に渡ります。本項では、SaaSの代表例を紹介します。
Web会議システム
リモートワークに必須となったWeb会議システムは、SaaSの代表的なサービスです。アプリのダウンロード版もありますが、基本的にブラウザだけあればサービスを使用できます。
代表例:Zoom、Microsoft Teams、Google Meet
ERPシステム
ERPは「Enterprise Resources Planning」の略で、経営に関する情報や資源を統合的に管理する考え方です。ERPシステムは、会計・人事・生産・物流・販売などの幅広い業務分野の機能を持つ基幹業務システムであり、近年ではSaaSとしても提供されています。
代表例:Salesforce、SAP S/4HANA、NetSuite
オンラインストレージ
オンラインストレージは、クラウド上にデータを保存できます。従来は自前のサーバーなどに共有フォルダを置き、チームメンバーで共有・更新していましたが、近年ではこの工程をクラウド上で行うケースが増えており、これもSaaSの一種といえます。
代表例:OneDrive、Box、Dropbox、Googleドライブ
業務チャット
業務上の連絡や情報の共有などに用いられるコミュニケーションツールはメール、メッセージアプリから、SaaSによるチャットツールへと主流が移り変わりつつあります。これらのチャットツールには、多くの場合Web版とアプリ版のUIが用意されていますが、バックグラウンドとなっている情報の保持、やり取りを行う仕組みはSaaSとして提供されています。
代表例:Slack、Teams、Meet、Chatwork
タスク・プロジェクト管理
複数人で行う業務において、実施すべきタスクや進捗状況、その他の情報共有を管理するツールがタスク・プロジェクト管理ツールです。これらのツールの機能はSaaSのメリットを活かせる場合が多く、様々なSaaSが提供されています。
代表例:Backlog、Redmine、Notion、Trello
SFA・CRM
SFA(Sales Force Automation)は営業支援ツール、CRM(Custmer Rerationship Management)は顧客管理システムであり、営業やマーケティング、カスタマーサービス部門の業務プロセスをデジタル化し、効率化するツールです。商談や顧客に関する情報を共有、管理することができるこれらのツールは、SaaSとして様々な企業から提供されています。
代表例:Salesforce、Sansan、Hubspot CRM、Microsoft Dynamics 365、Oracle Sales Cloud
会計システム
企業や個人事業主の入出金を管理する会計システムもクラウドサービスとして提供されています。事業における資金管理、税務管理、請求書や納品書などの帳票出力などの機能をもちます。従来はパッケージ製品のソフトウェアが多かったのですが、クラウドサービスの普及によりSaaSのサービスが主流に移り変わりつつあります。
代表例:freee、弥生会計、マネーフォワード、勘定奉行クラウド
勤怠管理
出勤、退勤の時刻の入力と管理、休暇申請などをデジタルに管理するのが勤怠管理システムです。テレワークなどの多様な働き方が進められる中、様々な環境から利用できるSaaSの勤怠管理サービスも多数登場しています。勤怠や休暇の情報は、人事や給与管理とも関連性が高く、システム間連携機能を持つサービスも少なくありません。
代表例:ジョブカン勤怠管理、KING OF TIME、マネーフォワードクラウド勤怠
SaaSを導入する際に確認すること
業務にSaaSを導入する場合に、事前に確認しておくべきポイントが存在します。ビジネス上の選択肢として、費用内で本来の目的を実現することができるかどうかが焦点です。
利用目的や実現したい業務を明確にする
どのような業務に向けて、どのような目的でSaaSを導入するのかを明確にして、適したSaaSを選択することが一つ目のポイントです。
SaaSを導入する場合、何らかの業務効率化や自動化などが目的にあり、業務量やコストなどの目標を実現する手段となります。このためには、既存の業務にあったSaaSを選択するか、効率の良いSaaSに合わせて業務を変更することが必要です。
また、実現できた業務効率化に対しコストメリットが生まれることも事前に確認しておきます。
利用する人数や業務量を確認しておく
SaaSの利用に関しては、人数や利用量により利用料金の変わる契約が一般的です。SaaSのサブスクリプション契約の場合には、初期費用はかかりませんが、継続的に利用した場合には取り扱うデータが増え利用料金が変動する可能性があることも考慮しなければなりません。
SaaSを選ぶポイント
SaaSを利用するにあたって、サービス選定のポイントを紹介します。優れたサービスは多数存在しますが、業務の形態・手順やコストメリットなどは導入先の企業や組織ごとに異なります。所属組織に最も適したサービスを選ぶことが重要です。
目的、用途に合った機能のあるSaaSを選ぶ
SaaSを利用する目的、用途を明確にした上で、それが実現できる機能をもったSaaSであることが選定の第一の基準です。
SaaSというくくりでは、非常に多くのサービスが存在しています。まずは、目的、用途を洗い出して、サービスのカテゴリを絞ってSaaSを選択しましょう。
他サービスと比較する
同じカテゴリのSaaSの中でも、複数のサービスが用途や目的に該当する場合には、各SaaS間で比較を行います。SaaSの特徴、機能、サービスの精度、料金体系、サポート体制、導入実績や事例などが比較の対象です。
トライアルを活用する
各SaaSが提供する情報では、基本的にメリットが前面に出されています。これらの情報から見て取れない部分を確かめるためには、無料トライアルの活用やデモンストレーションを見ることが有効です。トライアルやデモで、SaaSの使いやすさ、機能の分かりやすさ、発生するデータ量などをより正確に知ることができます。
ベンダーに相談するのも一つの手
自社でのSaaSの選定や比較が難しい場合には、各種のSaaSを代理店として扱うベンダーに相談し、適したサービスを探すのも方法の一つです。事例を多く持つベンダーはノウハウを蓄積している可能性も高く、SaaSごとの特徴などにも精通しています。また、SaaSを導入する際の、定着に向けた社内教育やアフターフォローもサポートが望めます。
SaaSを利用する際の注意点
SaaSを業務で利用する場合には、いくつかの注意点があります。
いくらクラウドサービスと言えど、預けたデータが失われないことを保証するものではありません。サイバー攻撃やヒューマンエラー、障害などでデータが失われる可能性を考え、データのバックアップをとっておく必要があります。
また、SaaSを導入した場合、自組織内でサービスが浸透し、活用されることが重要です。このため、組織内の従業員に対し利用方法の教育を行い、活発に利用される土壌を作る必要があります。
SaaSの利用におけるセキュリティに関しても、注意を払う必要があります。クラウドサービスにおけるセキュリティは、責任共有モデルの考え方が適用されるケースが多く、サービスの提供者と利用者が適切に対応することが求められます。クラウドサービスそのもののセキュリティ対策は事業者が責を負いますが、サービス上の設定、アクセスや権限の管理については利用者側で十分に配慮が必要です。
SaaSエンジニアの仕事内容と必要とされる知識・スキル
SaaSを提供するエンジニアの仕事内容と、必要とされる知識・スキルを解説します。
SaaSを提供するエンジニアは、Webサービスを提供するITエンジニアです。サービス・プロダクトの開発を行い、リリース後は継続的に機能追加や改善を繰り返す運用フェーズも担当します。継続的な開発とリリースを繰り返すため、アジャイル、スクラムなどのシステム開発手法が採用されている現場が多いという特徴があります。
SaaSエンジニアといっても、フロンエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニア、クラウドエンジニアなどさまざまな職種があり、仕事内容がそれぞれ異なります。また、これらのなかで複数の仕事を担当する場合もあります。
関連記事:SaaSエンジニアに必要なスキル・仕事内容・メリットを解説
フロントエンドの開発
フロントエンドエンジニアは、ユーザーがシステムを利用するための画面など、ユーザが直接触れるフロントエンドの開発を行います。デザインをもとにサービスの画面部分の開発を行うため、HTML・CSSなどの画面表示に関する言語やフレームワークの技術が必要です。
サーバーサイドの開発
フロントエンドからリクエストされる処理を行うシステム開発は、サーバーサイドエンジニアが担当します。ソフトウェアの中心部分となるデータベース制御や、API開発などのスキル・知識が求められます。
クラウドのインフラの構築・管理・チューニング
クラウドエンジニアは、クラウド上にあるサーバー・OSなどのインフラの構築・管理・チューニングなどを行います。AmazonのAWSやGoogleのGCP、MicrosoftのAzureなどに関する知識・スキルが求められます。
関連記事:
クラウドエンジニアの需要が高い理由を解説!将来性や年収も紹介
インフラエンジニアにAWSスキルが求められる理由
AWSとは?特徴や資格、サービスを初心者向けに解説
AWSのEC2とは?利用するメリット、需要の高さを解説
AWS Amplifyとは?特徴や料金、メリットなどを解説
SaaSエンジニアの知識・スキル習得のポイント
SaaSエンジニアに必要となる知識・スキルを習得するためのポイントを紹介します。SaaSはWebサービスと重なる部分が多く、実際にWebアプリケーションを構築して理解を深めることが重要です。
実践を通した習得
オンラインコースや書籍から基礎となるWebアプリケーションに関する知識、スキルを学びましょう。これらのコンテンツ内にあるコードを動かして理解を深めます。
さらにスキルを向上させるため学んだ知識を、実際のプロジェクトや小さなアプリケーションの開発に活用して、経験やスキルを積み上げるとよいです。
特定のクラウドサービスに特化して学習する
SaaSエンジニアとして働く場合、各種のクラウドサービスを活用することが必須となります。クラウドサービスの提供者は多く、すべてのクラウドサービスをマスターすることは困難であるため、はじめは一つのサービスに絞り、仕組みや特性、構築方法などを深く理解するのが効果的です。
参考:AWS、クラウドスキルの習得やキャリア開発のための3つの無料トレーニングプログラムを開始
最新技術のトレンドを追う
SaaSやクラウドの技術は日々進化しています。最新の情報をキャッチアップすることが重要です。新たに登場するSaaSにも注目し、技術的なトレンドを追うための取り掛かりとするのも一つの方法です。
セキュリティ意識の醸成
パブリッククラウドのSaaSは多くのユーザーに公開されるため、セキュリティが非常に重要です。セキュリティのベストプラクティスや脆弱性に関する知識を習得しましょう。自分の担当する領域や分野での、セキュリティ対策から身に着けるのがおすすめです。
SaaSに関するよくある質問
SaaSに関するよくある質問と回答をまとめました。SaaSの概要を知り、キャリアパスの検討材料として頂ければ幸いです。
Q1.SaaSとは何ですか?
SaaSはクラウドサービスの一種で、インターネットを介して利用可能なソフトウェアサービスです。利用者は、Webブラウザなどからアクセスし、場所や時間の制約をあまり受けずに利用することができることが大きな特徴となります。
SaaSの持つ機能、提供する内容は、サービスごとに異なり、幅広い分野のSaaSが生まれています。
Q2.SaaSの身近なサービス例を教えてください
業種や業界を問わずによく利用されているSaaSの例として、下記があげられます。
・Web会議システム
代表例:Zoom、Microsoft Teams、Google Meet
・オンラインストレージ
代表例:OneDrive、Box、Dropbox、Googleドライブ
・業務チャット
代表例:Slack、Teams、Meet、Chatwork
Q3.クラウドサービスとSaaSの違いは何ですか?
クラウドサービスとは、ネットワークを介して、ソフトウェアやプラットフォームなどを提供するサービスの総称です。
SaaSはクラウドサービスの中でも、ソフトウェアによるサービスを提供するものだけが該当します。
まとめ
クラウドサービスとは、ネットワークを介して、ソフトウェアやプラットフォームなどを提供するサービスであり、その中でもソフトウェアによるサービスを行うものはSaaS(Software as a Service)と呼ばれます。従来はソフトウェアの提供は端末へのインストールを伴うことが多かったのですが、近年ではSaaSによる提供に主流が移り変わりつつある状況です。
SaaSは利用者にとって、利用場所や時間の制限を受けづらいことや、初期導入コストが低いこと、保守管理の負担が少ない、常に最新機能を利用できる、多人数での同時利用に適するなどのメリットをもちます。また、サービス提供においてはスモールスタートがしやすく、スタートアップに適する特徴も持っています。
業務へのSaaSの導入に関しては、用途や目的を定めて、適したサービスを選定することが重要です。コスト負担に関しては、SaaSをどれだけ利用するかで変わってくるため、事前に試算しておきましょう。
SaaSを開発するエンジニアには、Webのフロントエンドエンジニアやサーバーサイドエンジニア、インフラエンジニアなどが該当します。SaaSの開発・提供は、システムの受託開発やパッケージ製品の開発と異なり、継続的に機能追加、リリースを行うため、アジャイルやスクラムなどの手法が取り入れられているケースが多い特徴があります。
SaaSは利便性の高さから、多くの企業や組織に浸透しており、利活用が進んでいます。エンジニアにとっては、活用のためのスキル・知識は業務の効率化に役立つものです。また、今後もSaaSという形態は広く利用されていくことが予測できるため、SaaSの開発に携わるエンジニア職種を目指すこともキャリアパスの選択肢としてみてください。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。
「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。
「個別相談会」に申し込む
転職支援サービスに申し込む
※転職活動を強制することはございません。
レバテックキャリアのサービスについて