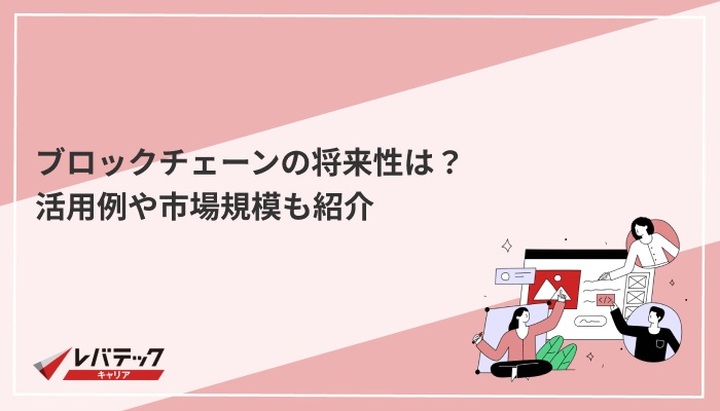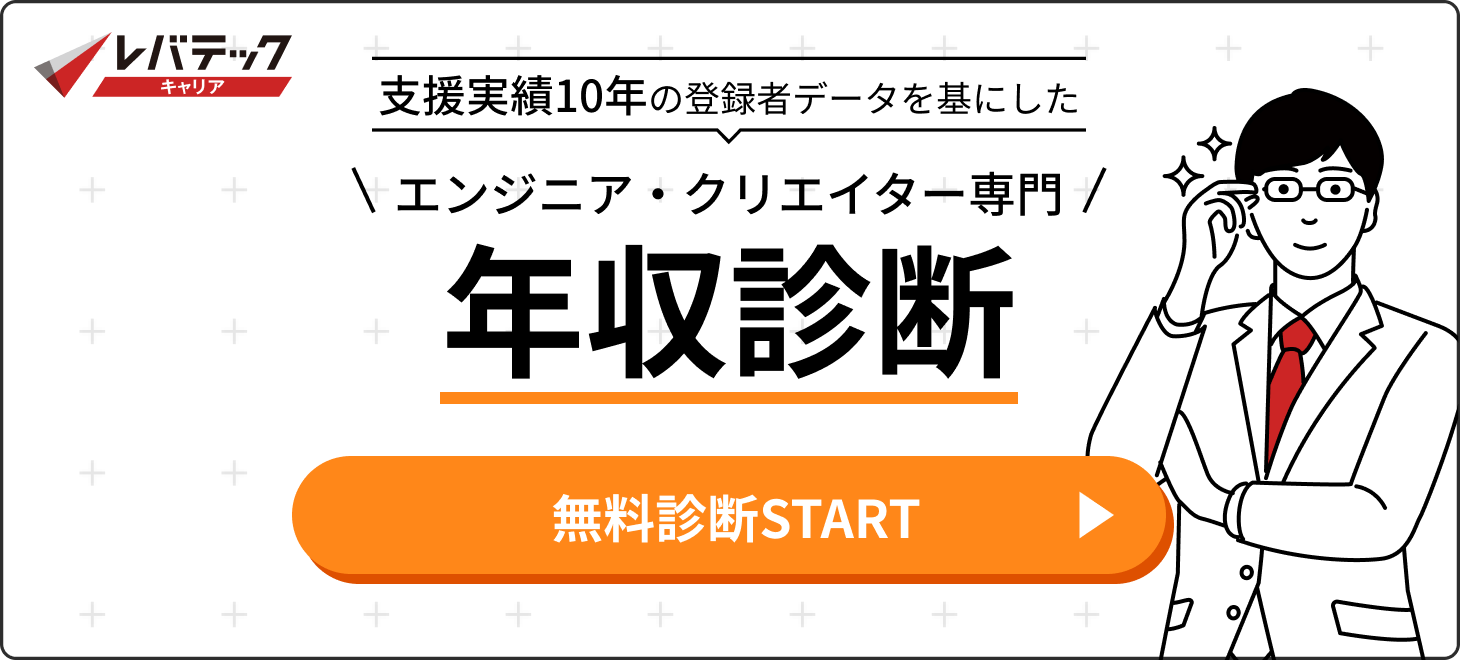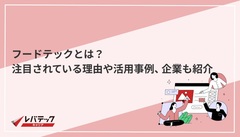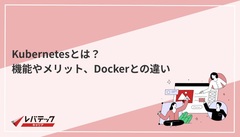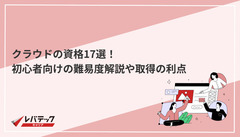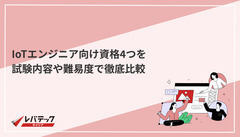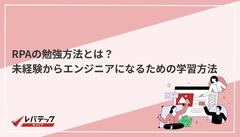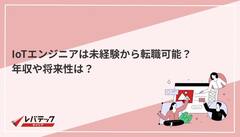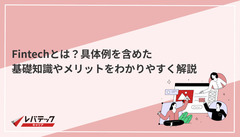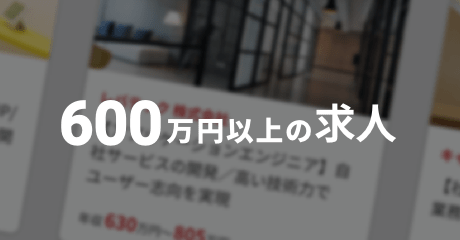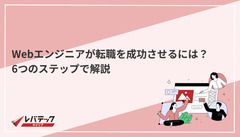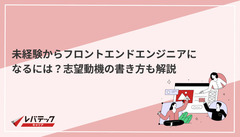- ブロックチェーンとは?
- ブロックチェーンの市場規模と将来性について
- ブロックチェーンの活用が期待されている分野
- ブロックチェーンエンジニアとは?
- ブロックチェーンエンジニアになる方法
- ブロックチェーンエンジニアに必要な知識
- ブロックチェーン開発で用いられる代表的なプログラミング言語
- ブロックチェーンに関するよくある質問
- まとめ
ブロックチェーンとは?
ブロックチェーンと聞くと、ビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)を思い浮かべる方は多いでしょう。まさに、仮想通貨の取引は、ブロックチェーン技術によって支えられています。世界中で頻繁に行われる大量の取引情報を分散して保存する仕組みにより、高い安全性と信頼性が担保されている技術です。
また、ブロックチェーンの技術は食産業における流通経路のトラッキング管理、アート・音楽作品といった著作物の保有権・著作権の管理などができ、仮想通貨以外の分野でも注目されています。そのため、ブロックチェーンはあらゆる業界の将来性に深く関わる技術です。
ブロックチェーンの概要や市場規模について解説します。
関連記事:ブロックチェーンとは?仕組みやメリット・デメリットを解説
ブロックチェーンの定義
ブロックチェーンとは、任意のデータを格納するブロックとブロック同士をつなぐチェーンを基礎とする分散型データベース技術の総称です。電子署名とハッシュポインタによる高い「耐改ざん性」を持っています。データ構造(箱)を鎖のようにつなぐため、「ブロック(箱)+チェーン(鎖)」と呼ばれています。
日本ブロックチェーン協会によれば、広義のブロックチェーンは以下のように説明されています。
電子署名とハッシュポインタを使用し改竄検出が容易なデータ構造を持ち、且つ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノードに保持させることで、高可用性及びデータ同一性等を実現する技術
出典:日本ブロックチェーン協会 ブロックチェーンの定義
ブロックチェーンの特徴

ブロックチェーンには以下のような特徴があります。
-
・取引をする際に信用を担保できる・不正取引を取り除ける
・コスト削減ができる
ブロックチェーンには複数の種類がありますが、いずれも上記の特徴は共通しています。それぞれの理由について解説していきます。
取引をする際に信用を担保できる
ブロックチェーン取引で信用を担保できるのは、ブロックチェーンが以下のような仕組みになっているからです。
-
・暗号署名が付与された取引情報をネットワークに発信する
・同時に複数の分散型台帳(データベース)に書込みを行い、取引情報を管理する
・データベース間の情報が一致するよう、合意形成の手法で承認処理が行われる
・承認後の取引情報を別の第三者へ送信する
これら一連の処理を「P2P(Peer to Peer)」の状態で自動的に行います。P2Pとは、ネットワークにつながっている端末間でデータやファイルをやり取りする手法で、サーバーを介さない仕組みです。
中央管理者が存在しないため、複数のデータベースで管理しています。一ヶ所だけがデータを握るわけではないので、結果的に信用を担保できるということです。
不正取引を取り除ける
ブロックチェーン取引は、中央管理者に依存することなく取引情報が分散され、世界中の不特定多数のユーザーによって管理されています。そのため、仮に誰かが不正を試みようと思った場合、複数に連なるブロックのデータをすべて矛盾なく改ざんする必要があります。そうしなければ、データを照合した際に改ざんがバレるからです。
複数ヶ所にデータがあるとそれだけ不正取引やデータの改ざんに手間や時間がかかり難しいため、結果的に改ざんしようとする者が不正をしにくくなっている仕組みといえます。
コスト削減ができる
ブロックチェーンの場合、一ヶ所で管理せずに分散管理しているので、サーバー代や保守や管理の費用がかかりません。また取引認証も分散して自動で行われるため、この点でもコストがかかりません。さらに処理の負荷も一ヶ所に集中しないため、コストパフォーマンスに優れています。
ブロックチェーンのタイプ
ブロックチェーンを用いる場合には、「分散性」「安全性」「処理速度」などを考慮して運用環境や目的に合わせた種類を選択します。タイプは以下の3種類に分けられます。
・パブリックチェーン
・プライベートチェーン
・コンソーシアムチェーン
それぞれ特徴が異なりますが、種類によって機能面のパフォーマンスの程度も変わってきます。その点からいうと、パブリックチェーンとコンソーシアムチェーンの中間の特性を持つのがプライベートチェーンです。
「管理者を複数設けるかどうか」、「取引情報の共有範囲をどこで線引きするか」などの観点から最適な種類を判断する必要があるでしょう。では、ブロックチェーンのタイプ別に特徴を解説していきます。
パブリックチェーン
ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨取引で使用されている仕組みです。中央管理者が存在せず、誰でもネットワークに参加でき、参加者自体が取引情報の承認者になれます。そのため、ほかの種類と比べて極めて安全性が高いです。
一般的にいわれるブロックチェーンは、パブリックチェーンを指すことが多いでしょう。
プライベートチェーン
中央管理者が存在し、ネットワークへの参加は許可制で、なおかつ取引情報の承認は中央管理者が行う仕組みです。「許可型ブロックチェーン」とも呼ばれることもあります。ネットワークへの参加者と承認者を限定することで、取引や個人情報の秘匿性を高めていることが特徴です。また、パブリックチェーンに比べて承認の処理速度が速いのが強みといえます。
プライベートチェーンは、限定されたシステム内で利用したい一般企業向けに適しています。
コンソーシアムチェーン
プライベートチェーンの発展型で、中央管理者を複数設置し、承認処理の柔軟性を高める方式です。プライベートチェーンでは、承認者の数に比例して承認速度が速くなる傾向にあるため、秘匿性と柔軟性を同時に確保したい場合に使用されます。また、管理者が分散されることで、改ざんや不正への耐性を高める効果もあります。
複数の企業がブロックチェーンの共同開発を行いたい場合などに選択されるケースが多いです。
ブロックチェーンの市場規模と将来性について
ブロックチェーンは市場規模が拡大しており、今後も技術の進歩が期待されると予想されているため、将来性のある技術といえます。
また、ブロックチェーンの需要は、特定の業界に限られません。そのため、さまざまな業界で活躍するエンジニアにとって、ブロックチェーン技術は自身の将来性を広げるきっかけにもなるでしょう。
今後の市場規模と将来性について詳しく解説します。
ブロックチェーンの市場規模
IoTを含む幅広い分野への応用が期待されるブロックチェーン技術は、国内外ともに、非常に大きな市場規模です。
2016年に発表された経済産業省の平成27年度 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(ブロックチェーン技術を利⽤したサービスに関する国内外動向調査)によると、日本国内のブロックチェーン関連技術の市場規模だけでも、67兆円にも上ると試算されています。これは、国内医療・福祉業界に並ぶほど大きな市場規模です。
また、GlobalDataの調査レポートによると、世界のブロックチェーン関連技術の市場規模は2021年度で61億米ドル(約8000億円)に達し、2022年から2030年にかけて62.4%以上の年平均成長率で拡大していくとの予測があります。このように、国内外で高い需要があり、今後もさらに市場規模の拡大が期待されます。
ブロックチェーンの将来性
ブロックチェーンは十分な将来性を持つ技術ということができます。
ブロックチェーンには、24時間無休稼働を前提とした信頼性の高い仕組みを、低コストで構築できる強みがあります。近年、データ活用の拡大や5G普及に伴うIoT商品の拡充により、サイバーセキュリティのリスクは高まっています。そこで、さまざまな分野のセキュリティ対策として、ブロックチェーン技術の活用が期待されています。
ブロックチェーンの活用が期待されている分野
ブロックチェーンの活用が期待されている分野は多いです。ブロックチェーンは、「同じ情報を複数の当事者がリアルタイムに共有することで効率化が進む業務」や「経緯、履歴の信頼性を保ち、改ざんを防ぐ必要がある業務」に適しています。そのため、あらゆる分野でその技術を活用しようとする動きが広がっています。
ブロックチェーンが普及し始めた当初は、仮想通貨のイメージが強かったですが、現在では金融、食品、物流、医療などにおける活用事例が多くあり、市場の伸びとともに将来性が期待されています。具体的には、次のような分野の業務です。
国際送金
国際送金は手数料が高い上に数日単位の時間を必要とするため、頻繁に送金を行う事業者の負担となっていました。この原因は、SWIFT(スイフト)と呼ばれる国際銀行通信協会のインフラを使用しているためです。国際送金のインフラは40年以上前の仕組みで、送金データが複数の銀行を伝って送金されます。
これに対し、ブロックチェーンを利用した国際送金では、分散型台帳による自動的な承認処理で取引の正当性が担保されるため、この処理が発生しません。その結果、数秒〜数十分程度の時間で送金が完了し、手数料も抑えられます。
国際送金の利便性向上は、ブロックチェーンが注目される大きな理由の1つでもあり、実用化に向けた試みが着々と進んでいます。
食品のトレーサビリティ
食品業界では、食の安全性を確保するために「トレーサビリティ(追跡可能性)」を高めることが重要です。材料がどこから調達され、どこで加工され、どのように運ばれて売られているかを、しっかりと把握できれば食品の安全性を高められます。
しかし、サプライチェーンをつなぐ利害関係者の数があまりにも多いと、情報伝達が正常に行われず、追跡能力が確保しにくくなります。そこでブロックチェーンを使い、食品の安全性・信頼性を検証する仕組みが活用され始めています。
検査プロセスの合理化
建設業界では、工事の出来形(できがた)確認業務の合理化にブロックチェーンを活用する動きがあります。出来形確認では、工事の目的物が発注側データと合致しているか、受注者が提出した検査帳票が正確かなどをチェックする必要があります。
しかし、チェックに必要な情報が膨大であったり、点在していたりすると、確認に要する負担が大きくなりがちです。また、誤差の判定にも時間がかかるでしょう。こうした課題を解決するために、耐改ざん性と合理的な処理機能を持つブロックチェーンを活用する動きが広まっています。
医療技術
昨今の日本では、高齢化や医療サービスの充実に伴い、健康寿命が伸びないまま平均寿命が伸びています。そのため年々医療サービスの仕事量が増加しており、この状況を放置すると医療サービスの需要と供給のバランスが崩れ、医療崩壊を引き起こしかねません。
そのため医療業界では、予防医療に力を入れ医療崩壊を防ごうという考えが広まっています。予防医療の真価を発揮させるには、ヘルスケアデータの活用とシステム変革が必要です。
医療で扱う情報は、個人情報の中でも特に秘匿性の高い情報です。また、中央管理者の存在が障害になりうると考えられています。これらの点において、ブロックチェーンは医療業界のシステム変革に適しているため、注目されています。
AI技術
ブロックチェーンは、AI技術と組み合わせることで効果が高まり、さらに多くの分野へ使用できます。たとえば、AIにブロックチェーンの暗号技術を組み込むことで、暗号を解読せずにそのまま扱うことが可能です。
また、暗号技術を用いれば、セキュリティの向上につながり、専門知識のない企業でも扱いやすくなります。さらに、AIに解読させた過程をブロックチェーンに記載することで、AIの意志決定の検証が可能です。
NFT(非代替性トークン)
NFTは、ブロックチェーン技術を活かしアート作品や音楽作品などさまざまなモノに世界で唯一無二の価値をもたらすデジタルデータとして知られています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を用いて取引され、誰でも購入したり売却したりできます。
日本円と米ドルが互いに交換できるように、仮想通貨同士も交換可能です。しかし、NFTには保有権や著作権などのデータが結びついています。そのため、たとえばイラストをNFT化した場合、それは何にも代替できない固有の資産となり、盗作される心配もありません。
最近では、不動産投資において投資家にNFTを販売しその分だけ所有権を移転したり、NFTで不動産の売買を行いブロックチェーン上に権利移転の記録を保管したりといった事例も見られます。またゲームでも、希少性の高いアイテムやオリジナルで作成したアイテムをNFT化し売買するケースが見受けられ、確実に活用の場が広がっているといえるでしょう。
ブロックチェーンエンジニアとは?
ブロックチェーンエンジニアとは、ブロックチェーンの開発や、ブロックチェーンを活用したアプリケーションの開発・実装を手掛けるエンジニアです。ブロックチェーン技術だけでなく、システム開発に関する知識も求められるため、ハイレベルな業務といえるでしょう。ここからは、ブロックチェーンエンジニアの将来性や平均年収、仕事内容について解説します。
将来性
ブロックチェーン技術の需要増加に比例して、ブロックチェーンエンジニアの需要も高まっているため、将来性は明るいといえます。特に金融サービスに変化をもたらすとされる「フィンテック」で必要なことから、金融業界を中心に需要が高いです。
また、ブロックチェーンの知識だけでなく、プログラミングスキルや導入企業に関する業界知識も求められるため、条件を満たすエンジニアの数が少なく、需要が高まる理由の1つとなっています。
平均年収
レバテックキャリアで扱っている求人によると、2024年3月時点でのブロックチェーンエンジニアの年収は420万円〜1200万円前後、平均年収は約810万円で、一般的なITエンジニアと比べて給与の水準が高いです。需要に対してエンジニアの数が少なく、どの企業も採用活動に苦戦しているため、高給を提示する企業もあります。
また、高い需要や好条件な待遇が受けられる可能性が高いため、企業に雇用されず、フリーランスエンジニアとして働くことも可能です。
仕事内容
主な仕事内容は、ブロックチェーン本体や、ブロックチェーンを基盤としたアプリケーション・ソフトウェアの開発・実装です。顧客の要望に対して最適な基盤を作り、自社独自のブロックチェーンを開発・実装します。また、ブロックチェーン技術の研究も行います。
ブロックチェーンを基盤としたアプリケーション・ソフトウェアの開発・実装は、仮想通貨プラットフォームだけではありません。取引管理システム・シェアリングサービスなど関わる業界は多岐に渡るため、今後も将来性が注目される職種でしょう。
ブロックチェーンエンジニアになる方法
ブロックチェーンエンジニアは、独学や学校に通うことで未経験からでも目指せます。しかし、専門的な知識・スキルが要求されるため、まったく開発経験のない人がいきなり転職するのは非常に難易度が高いといえます。そのため、まずはWeb系の開発業務で実務経験を積み、徐々にブロックチェーン技術を習得し、転職を目指すことをおすすめします。
まずはWebエンジニアになる
Webエンジニアを目指すことも、未経験の人にとっては難易度が高いでしょう。しかし、Web開発などのフロントエンドエンジニアは、未経験から応募できる求人も少なからずあるため、転職できる可能性があります。
未経験エンジニアが入社できる可能性が高いのはスタートアップ企業が多いです。志望するスタートアップ企業で必要となるプログラミング言語のほか人気のRuby on railsやReactを学んで転職すると良いでしょう。プログラミング言語やRuby on rails、Reactを学ぶことでプログラミングの思考法を身につけられます。また、人気の技術なので市場価値も上がります。
ブロックチェーン技術を学ぶ
ブロックチェーンエンジニアを目指すには、教本やWeb教材などを活用し、ブロックチェーン技術の基礎を学ぶことが大切です。また、知識を身につけるだけでなく、実際にブロックチェーンの開発に挑戦すると良いでしょう。
ブロックチェーンの教材は初心者向けのチュートリアルから本格的な実装例までWeb上で確認可能です。たとえばUdemyでは、ブロックチェーンの仕組みが学べる初心者向けの講座が受講できます。また、ブロックチェーンに関連する仮想通貨やNFTなどに特化した講座もあります。
関連記事:ブロックチェーンに関する資格を解説!取得するメリットとは
ブロックチェーンエンジニアに必要な知識

ブロックチェーンエンジニアに必要な知識として、以下のようなものが挙げられます。
-
・暗号技術に関する知識・ブロックチェーンに関する知識
・システム、アプリケーション開発に関する知識
ブロックチェーン技術はあらゆる業界で活用されてきているため、1つのサービス・システムを開発するには、組み合わせる技術の知見やその関連知識も欠かせません。たとえば、仮想通貨に関わるブロックチェーン技術を実装するなら暗号技術の知識は必須です。
ブロックチェーンエンジニアに求められる各知識の内容について解説していきます。
暗号技術に関する知識
暗号技術はブロックチェーンの核です。データの内容を暗号化し第三者に分からないようにすれば、ブロックチェーン特有のセキュリティが担保された取引ができます。暗号技術を細分化すると、ハッシュ関数、公開鍵暗号方式、電子署名などがあります。ブロックチェーンエンジニアは、これらの仕組みを理解した上で開発を進める必要があるでしょう。
ブロックチェーンに関する知識
ブロックチェーンエンジニアには、当然ブロックチェーンに関する知識は必須です。ブロックチェーンの技術も細分化されており、暗号技術以外にも、P2Pネットワーク、コンセンサスアルゴリズム、スマートコントラクトなどがあります。
ブロックチェーンの全体構造と細部の技術を理解することで、ブロックチェーン開発が可能になります。厳密にいえば、既存のコードを使ってプログラミング自体はできますが、理解しないままコードを書いてしまうと不具合やセキュリティ事故につながる可能性が高いです。
システム、アプリケーション開発に関する知識
ブロックチェーンエンジニアはブロックチェーンの開発を行いますが、土台として一般的なシステム開発、アプリケーション開発スキルが必要です。具体的な工程としては、要件定義、設計、プログラミング、テストが挙げられます。
Web開発のスキルや業務システム開発のスキルが必須というわけではありませんが、ブロックチェーン開発でも共通する部分が多いです。たとえば、言語に関わらず基本となるアルゴリズムの考え方、プロジェクトの流れ、設計書の作り方、などは最低限理解している必要があります。
エンジニアとして最初のキャリアがブロックチェーンエンジニアということは少ないので、多くの人は何らかの開発経験を経ているでしょう。それだけ、ブロックチェーンエンジニアには開発そのものに関する理解とスキルが求められます。
関連記事:ブロックチェーンの勉強方法について!おすすめの本やサイト、基本用語も紹介
ブロックチェーン開発で用いられる代表的なプログラミング言語
ブロックチェーン開発で扱われるプログラミング言語は複数あります。AIに用いられるPythonのように、特定の言語に偏っているわけではありません。ブロックチェーン開発においてよく使用されるプログラミング言語には以下が挙げられます。
-
・C言語(C++)・C#
・JavaScript
・Solidity
・Go言語
それぞれの言語の特徴や、どのような開発で使用されることが多いのかなどについて解説していきます。
C言語(C++)
ブロックチェーンが世に知られるきっかけになったビットコインはC言語(C++)で開発されています。そのため、ブロックチェーン開発ではC++が代表的なプログラミング言語です。C++はC言語の一部の機能を拡張したもので、オブジェクト指向の機能を持っています。
C言語とJavaの経験がある方は、組み合わせたようなものをイメージすると分かりやすいでしょう。オブジェクト指向の言語経験がない方にとってはハードルが高めですが、逆にオブジェクト指向言語の経験があればC言語よりも理解しやすいです。
関連記事:C言語とは|特徴やC++やC#との違いを分かりやすく解説
C#
C#はC言語、C++、Javaを組み合わせた派生言語です。ブロックチェーン開発の中でも、MicrosoftやWindowsアプリ開発で使用されることが多いです。ただしOSに依存するわけではなく、あくまでも相性が良いというだけです。汎用性という面では、幅広い開発で使用されています。
関連記事:C#とは?特徴やメリット、C言語やC++との違いを解説
JavaScript
JavaScriptはフロントエンドのイメージが強いですが、サーバーサイド用のフレームワークもあります。そして、Webのブロックチェーン開発ではJavaScriptが使われることがあります。この場合、サーバーサイドの一部とフロントエンドの両方にJavaScriptを使用するのが一般的です。
JavaScriptはブロックチェーン開発だけでなくWeb開発でも主要言語なので、スキル習得の汎用性が高いのがメリットです。
関連記事:JavaScriptとは?基本の書き方を初心者にわかりやすく解説
Solidity
Solidityは多くの方にとっては聞き慣れないプログラミング言語でしょう。イーサリアム上でスマートコントラクトを開発するために用いられる、用途が狭めの言語です。文法はJavaScriptに似ているので、使用ハードルは低いでしょう。
スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で取引が行われた際に自動的に実行されるプログラムのことです。つまり、Solidityはブロックチェーン開発と関わりの大きい言語といえます。習得すればブロックチェーンエンジニアとして就職・転職する場合に有利になります。
Go言語
Go言語はGoogleが開発したプログラミング言語であり、ブロックチェーン開発でも使用されています。コードがシンプルで使いやすいことから、Webを中心に幅広く使用されるようになっています。
Go言語はGoogleが開発していることに加えて開発対象の幅が広いため、ブロックチェーン開発でも今後使用頻度が増える可能性が高いでしょう。そのため、エンジニアとしては習得するメリットが高いです。ちなみに、Go言語は年収ランキングでも上位にランクインすることが多く、案件数も右肩上がりに伸びています。
関連記事:Go言語エンジニアの転職で知っておきたいこと
ブロックチェーンに関するよくある質問
ブロックチェーンに関するよくある質問と回答を紹介します。
Q1. ブロックチェーンエンジニアに将来性はありますか?
ブロックチェーンの技術は今後より需要が高まる可能性が高いです。そのため、ブロックチェーンエンジニアの将来性はあります。現状はフィンテックと呼ばれる、金融とITを組み合わせた分野での需要が高いです。社会的に注目度が高い分野で経済の軸にもなっているためブロックチェーンエンジニアは重要な存在といえます。
Q2. ブロックチェーンエンジニアの年収はいくらですか?
ブロックチェーンエンジニアの年収は420万円〜1200万円前後、平均年収は約810万円とされています。一般的なエンジニアと比較するとかなり年収の水準は高いです。それだけ需要に対して供給が追いついておらず、また高いスキルが求められるということでもあります。
Q3. ブロックチェーンのメリットは何ですか?
ブロックチェーンのメリットとして以下が挙げられます。
-
・取引をする際に信用を担保できる
・不正取引を取り除ける
・コスト削減ができる
ブロックチェーンは同時に複数ヶ所にデータを記録するので、信用を担保でき、不正取引を防止できます。また一ヶ所で管理する必要がないので、コスト削減にもなります。
Q4. ブロックチェーンのデメリットは何ですか?
デメリットとしては、以下が挙げられます。
-
・記録された情報を削除できない
・集団でデータ改ざんできる可能性がある
・処理に時間がかかる
ブロックチェーンは高い耐改ざん性が認められている一方、長い時間と巧妙な手法によれば不正の可能性は必ずしも否定できません。また、データが多いほど処理速度に影響します。
まとめ
ブロックチェーンは仮想通貨を中心に伸びている技術で、今後も伸びていく可能性が高いです。そのため、ブロックチェーンエンジニアは将来性の高い職種です。また技術が代替されても、ブロックチェーンの技術は応用が利くので技術変化に合わせられます。
ブロックチェーンエンジニアはエンジニアとしてのスキルが高いため、ほかの分野でも活躍が見込めます。ブロックチェーン単体でもある程度安泰ですが、幅広く応用できるスキルを複数習得していくとエンジニアとしての将来性も高まるでしょう。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。
「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。
「個別相談会」に申し込む
転職支援サービスに申し込む
※転職活動を強制することはございません。
レバテックキャリアのサービスについて