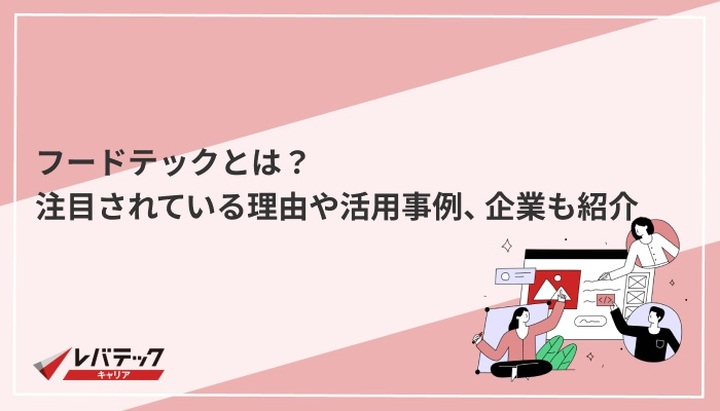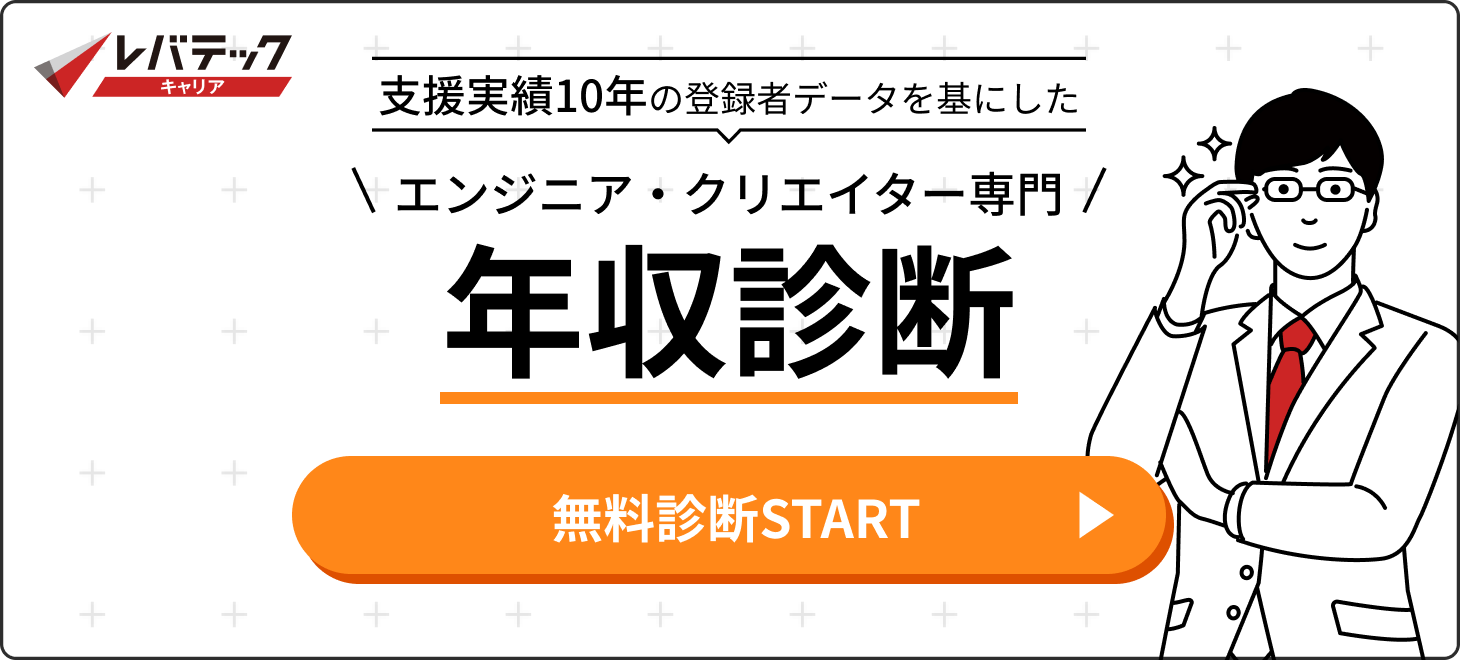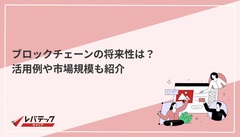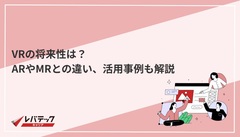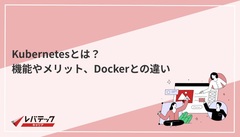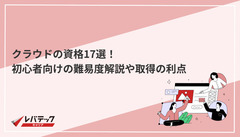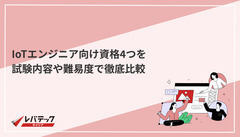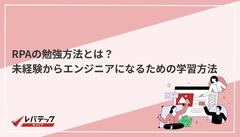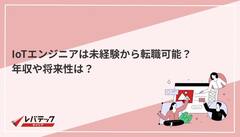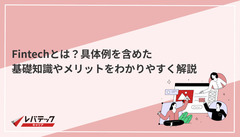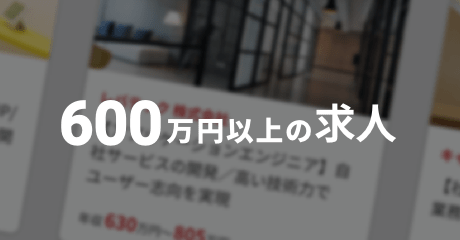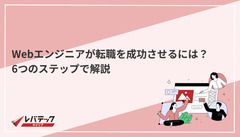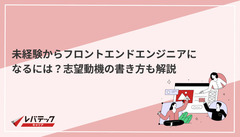- フードテックとは最新テクノロジーで食問題を解決する技術
- フードテックが注目されている理由
- フードテックを活用する企業の事例
- フードテック領域で求められる人材のタイプとは
- フードテックで誕生した最新技術
- フードテックの問題点は費用面のハードルの高さ
- フードテックに関するよくある質問
- まとめ
フードテックとは最新テクノロジーで食問題を解決する技術
フードとテクノロジーを合わせた造語であるフードテック。食に関する最先端技術を指す言葉です。フードテックとは、端的に言えば「食とテクノロジーが結びついた分野、もしくはそこで使われる技術」を指す言葉です。既存ビジネス領域と先端ITなどの融合である「X-Tech(クロステック)」の中でも、近年特に注目が集まる分野で、次々に新しいサービスが登場しています。
フードテックは、2015年頃から欧米を中心に取り上げられるようになり、2018年頃からは日本国内でもフードテック関連ビジネスが展開されるようになりました。
フードテックは、食品ロスの削減や代替肉の開発など、食料資源の問題やSDGs(持続可能な開発目標)とも深い関りがあります。また、食を中心としながらもIT・農業・ロボティクスなど広い分野を巻き込むことから、ビジネスシーンに与える影響は計り知れません。
こうした事情から、フードテックは人間社会が持続的に成長していくための「キーテクノロジー」として認識され始めています。
フードテックが注目されている理由

では、なぜここまでフードテックが注目されているのでしょうか。その理由を整理してみましょう。
世界人口の増加に伴う食料危機への懸念
日本では少子高齢化が進んでおり、人口は減少傾向にあります。しかし、世界では人口は増加傾向です。国連の調査によると、2022年時点で80億人を突破し、このまま増加すれば2058年には100億人を超える見通しです。人口が増加すればそれだけ食料の必要量が増えるため、供給が追い付かなくなります。
その食料危機への備えとしてフードテックは期待されています。
飢餓問題の深刻化
世界的に人口増加が起こっていますが、特に人口が増えているのは発展途上国です。そのため、飢餓問題がより深刻化しています。食料を入手するためのお金はないが、子供は増えていくという状況になっています。またこういった状況下では、食料の保存も設備的に難しく、無駄になってしまっている食料があります。
前述した食糧危機への備えと関連する部分もありますが、「食料の保存技術」や「過酷な環境下での食料生産」など、飢餓問題解決に向けた技術は日々研究されています。
SDGsにもつながる
フードテックは食料を無駄にしないための取り組みでもあるため、SDGsにもつながります。SDGsはSustainable Development Goalsの略で、持続可能な開発目標という意味です。
フードテックを推進することはSDGsにつながり、また企業戦略としてSDGsへの取り組みをアピールしたい企業がフードテック関連企業に出資や共同開発するという好循環も起こっています。
多様化する食への対応
食に求める価値観は多様化しています。グルメにこだわる人、少食を良しとする人、菜食主義の人、高タンパク質にこだわる人、など人によって食に求めるものはいろいろです。これらのニーズに幅広く対応するのにフードテックが役立ちます。
フードロスの増加
発展途上国では飢餓が問題になっていますが、一方で先進国ではフードロスが問題になっています。つまり残った食料が廃棄されているということです。フードテックによって、食料配分の問題解決、フードロスの解消が実現できる可能性があります。
人手不足への対策
少子化やITなどへの人材流出によって、食に携わる人材の現象、高齢化が進んでいます。特に、農業・酪農・漁業などの分野は深刻な人手不足と高齢化の状況です。フードテックではロボットやIoTを活用して、食に関わる業務の効率化や自動化を行います。その結果、食に携わる業界の人手不足解消につながります。
世界の飲食料市場の規模拡大
世界の飲食料市場規模は年々拡大しており、2030年には1,360兆円もの市場規模に成長すると見られています。特にアジア圏での成長力は目を見張るものがあり、2015年から2030年の15年間で1.9倍にまで伸びると見込まれています。
つまり飲食料市場に密接に関連するフードテックも、今後大きく伸びる産業・技術として注目されています。
参考:「世界の飲食料市場規模の推計」(農林水産政策研究所)
日本政府によるフードテック推進の動き
日本では、政府がフードテックを推進しています。たとdえば、 2020年、農林水産省が「フードテック官民協議会」を立ち上げました。2021年7月には、フードテックを推進する新事業・食品産業部を始動しています。食品作業を活性化することで食の問題を解消することや、経済を循環させることが狙いです。
フードテックを活用する企業の事例
実際に、世界で活躍するフードテック活用企業とはどのようなものがあるのでしょうか。世界でもフードテックを盛んに取り入れる代表的な企業を紹介します。
代替肉でバーガーキングと提携する「インポッシブル・フーズ」
食用肉の不足を解決するために、インポッシブル・フーズでは人工肉の一種である「代替肉」を製造・販売しています。ヘムと呼ばれる大豆を原料にすることで、本物そっくりの色と味の再現に成功。この代替肉は有名ファストフード店であるバーガーキングと提携しており、世界中で扱われています。
大豆を使った代替肉は食料不足を解決するほかに、宗教の問題や栄養不足をも補えます。牛肉を製造する畜産業では温室効果ガスを大量に排出するエコロジーの問題点がありますが、環境にも優しい考慮をする展開がインポッシブル・フーズの特徴です。
酪農・畜産の生産性向上と効率化を図る「ファームノート」
ファームノートとは、クラウド牛群管理システム「Farmnote」を提供する企業です。このシステムは酪農の飼育における行動ロスを減らす目的で設計され、過去のビッグデータによって牛の状態の見落としをなくすといった畜産の生産性向上が期待できます。従来の酪農・畜産から進化し、DXを推進する取り組みです。
ファームノート本社は北海道帯広市にあり、顧客数はおよそ4,500社。国内畜産だけでなく世界にも技術提供することで、人材の高齢化や人材不足を解決するきっかけとして注目されています。
冷凍技術とインターネットでフードロス削減「デイブレイク株式会社」
デイブレイク株式会社は食品流通において欠かせない食材冷凍の技術を革新する企業です。新鮮なまま食材を流通に乗せる特殊冷凍ソリューションを軸とし、特殊冷凍機械販売から流通へのコンサルティング、業務用特殊冷凍食材販売まで手がけています。
同社が開発した特殊冷凍機「アートロックフリーザー」は2022年Microsoft社提供のスタートアップ支援プログラム「Microsoft for Startups」にも採択されており、知っておきたいフードテック先進企業のひとつです。
鮮魚注文Webサービスを展開する「フーディソン」
水産業への取り組みが見られるフーディソン。生産流通のプラットフォーム構築を事業の主軸とし、鮮魚注文Webサービスを展開しています。ユーザーは企業から一般消費者まで幅広く設定されており、欲しい量の鮮魚をインターネット上で即座に注文できるシステムを構築しています。サプライニーズに直結することで、食品ロスを削減することができます。
また鮮魚加工技術に特化した人材紹介・派遣などのキャリア事業も手がけており、食品ロスという物流問題と人材不足の問題どちらへの取り組みも行う企業です。
事前注文と決済でスムーズな商品引き渡し「ShowcaseGig」
モバイルプラットフォーム「O:der」に注力するShowcase Gig。企業とユーザー連携を推進したり、モバイル決済分野で実績を残すなど、食材の流通を促し食品ロス問題を解決する取り組みを進めています。
ファーストキッチンウェンディーズなど大手チェーンストアも同社のシステムを採用し、2020年には吉野家が全国店舗で導入したことから、注目を集めています。大手チェーン店だけでなく中小飲食店での導入事例も増えていることから、今後食品業界のモバイル決済定番プラットフォームになると期待されています。
Delibotで盛り付け自動化「コネクテッドロボティクス」
コネクテッドロボティクス株式会社では食品を扱うロボットシステムを開発しています。中でも力を入れている製品が惣菜盛付ロボット「Delibot」です。Delibotは柔らかくてつかみにくい食材でも規定量を計測してつかみ、盛り付けることができます。スピードは、4台で1時間1,000食です。人材不足を解消するためのフードテック事例と言えるでしょう。
デリバリーサービスで中食を定着「UberEats」
UberEatsは日本でも定着していますが、これも一種のフードテックです。従来のデリバリーは電話をかけるのが一般的でしたが、UberEatsは専用のアプリだけで注文や決済ができます。またいろいろな店舗からデリバリー可能な点や、配達する人も店舗の従業員ではなくアプリに登録して動いているという点も従来までのデリバリーと異なります。
完全栄養食の開発・販売「ベースフード」
ベースフードは完全栄養主食を開発し、販売しています。サプリメントではなく、パンやパスタが代表的です。これらの食品に、通常とは異なる栄養素が入れられており、手軽に栄養価の高い食品を摂取できる製品です。添加物を使わずに長期保存できるので、非常食としても便利です。
オートトラクターで農業のロボット化「ヤンマー」
ヤンマーは農業用品や船舶で有名です。同じく農業のロボット化にも力を入れており、これもフードテックの一種として考えられます。具体的には、オートトラクターを販売中で、無人走行のロボットトラクターも実証実験中です。タブレットによる遠隔操作で操縦できるので、農業の人手不足解消につながります。
ソイルプロでたんぱく質不足も解消「ニップン」
ニップンは植物性タンパク質素材「SOYL PRO(ソイルプロ)」を開発しました。具体的には、大豆ミートなどが挙げられます。大豆はもともと高たんぱくなので、植物由来で高たんぱく、かつ肉のような食感の製品になっています。環境保護や健康の観点でメリットがあります。
フードテック領域で求められる人材のタイプとは
フードテック領域で求められるITエンジニアのタイプを紹介します。フードテック領域はITとの親和性が高いため、フードテックの知識を持たない人材であっても、一定のスキル・経験があれば転職は可能です。具体的には、次のようなタイプの人材が求められるでしょう。
自社サービス開発を行うフルスタック型のエンジニア
フードテックはITベンチャーが多数参入している領域でもあります。したがって、「少数精鋭」でサービス開発・運営を行っているケースが多いと推測されます。そのため、一人、もしくは少人数で開発した経験をもつフルスタック型のエンジニアが好まれる可能性があるといえるでしょう。
Webサービス、アプリ開発の経験が評価される
フードテックに関するサービスは、Webサービスやスマートフォン向けアプリケーションを介して活用されることが多いため、こうした領域で開発経験を持つITエンジニアが評価されるでしょう。また、プログラミングスキルは、PythonやRuby、Java、C言語など幅広い範囲で評価の対象になります。自社でアプリケーション開発も行っている企業であれば、JavaやKotlin、Swiftなどが扱えると有利かもしれません。2023年時点では、プログラミング言語の種類に強い縛りはなく、比較的門戸が広い業界だといえます。
フードテックの活用領域や理念に関心がある
これまでも紹介してきたように、フードテックには「タンパク質不足」「フードロス問題」など社会問題の解決手段として期待されているという側面があります。また、新興企業が多いためにビジネスモデルも発展途上で、エンジニア個人のアイディアや企画力が試されることもあるでしょう。
優れたアイディア・企画を生み出すためにはフードテック活用で何を成し遂げたいかという「理念」が必須です。理念を理解しているからこそ「何が問題なのか」「どう解決していくべきか」が明確になるからです。したがって、技術力もさることながら、フードテックの活用事例なども学習しておくべきかもしれません。
フードテックで誕生した最新技術

フードテックで誕生した最新技術をいくつか紹介します。
代替肉
全国に展開している大手スーパーでは、2021年から大豆由来の植物肉を使った商品を提供しています。また、植物肉を使用した春巻き、メンチカツ、がんもなども加工食品にも応用されており、今後は「豚肉や牛肉の代替品」としての地位を確立していくかもしれません。
ちなみにこうした植物肉は国内のスタートアップ企業で開発されており、さまざまな食感を持った肉に変化する製品もあるようです。従来の植物肉は脱脂大豆(油を抽出したあとの大豆)をベースにしていましたが、近年は発芽させた大豆を丸ごと使用する製法が開発されました。この製法は、大豆特有の臭みをおさえつつ、動物の肉のような筋線維を忠実に再現できるという強みを持っています。
また、発芽を経ることによりビタミンやアミノ酸などの栄養価が急激に高まるため、栄養面から見ても付加価値の高い製品と言えそうです。
昆虫加工食材
日本国内のあるスタートアップ企業では、昆虫をベースとした加工食材の開発に取り組んでいます。具体的には、コオロギの粉末から食材を生成し、レトルトカレーなどの原材料として利用しているようです。
一般的に食品加工では、「残渣(ざんさ)」と呼ばれるゴミが大量に発生します。残渣はフードロスの大部分を占めるとされ、残渣の減少や有効活用がフードロス削減につながると考えられています。
この残渣をコオロギの餌にすることで、フードロスを減らしつつ、栄養価の高い食品を生成することができるわけです。コオロギが成長するまでの餌は鳥や豚よりも圧倒的に少なく、なおかつ亜鉛や鉄分、カルシウム、マグネシウム、タンパク質などを含む栄養価の高い素材であることがわかっています。また、コオロギは「陸のエビ」とも呼ばれるほど優秀な食材です。味や風味も良く、「食材としてのおいしさ」を担保しやすいという特徴があります。
一方、現代人にはあまり馴染みがなく、見た目のイメージから抵抗を覚える方も少なくないでしょう。しかし、この企業ではコオロギを粉末にすることで見た目の抵抗感を減らし、栄養価の高い食材として提供しているようです。
フードシェアリングサービス
飲食店から発生する「廃棄」を格安、もしくは無料でシェアする「フードシェアリングサービス」が大都市圏を中心に広がりを見せています。
日本で発生するフードロスのうち、約半分が飲食店や小売店などの事業者から発生しています。ロスが発生する理由は、「予約キャンセル」「受発注のミス」「品揃え上の事情」などさまざまです。食品自体には何ら問題がないにもかかわらず、大量の食品が廃棄されているため、フードシェアリングサービスは徐々に注目を集めています。
フードシェアリングサービスはWebサービスやスマホアプリとして提供されることが多く、定額もしくは格安で食品ロスを食べることができます。また、位置情報を利用して現在地から最も近い店舗を検索する機能など、「利用希望者と食品ロスとのマッチング」を考慮したサービスが多いことも特徴です。
フードロボット
フードテックは、代替肉の開発や食品ロス削減が注目されがちですが、人手不足対策・省力化にも貢献しています。国内のあるロボティクス関連企業では、調理をサポートする人型の協働ロボットを開発。小柄な成人サイズのロボットで、二つの腕を持ち、お弁当のおかずを製造する作業を単独で行うことが可能です。
また、ディープラーニングを活用したAIを搭載しており、バラバラに積まれた食材を認識して、ピッキング・盛り付けを行う機能も備えています。
食品製造工程の中でも、盛り付け作業は特に自動化が難しいとされてきました。対象となる物体の認識が難しいことや、作業自体が煩雑になりやすいことがその理由です。そのため、人手不足対策や省力化のボトルネックになっていたと考えられます。
この協働ロボットを活用することで盛り付け作業を効率化できるほか、異物混入の防止、ウイルスや細菌への感染リスク低減など、さまざまな効果が期待できます。
冷凍食品技術
感染症対策によってテイクアウト、持ち帰りの需要が増加した背景をもとに、冷凍食品への技術も注目が集まっています。食材を急速に冷凍する特殊冷凍技術の向上や、冷凍食品を保管する機材技術、また冷凍食品を販売する冷凍自動販売機の開発も現在進んでいます。
冷凍食品そのものを生み出す技術はもちろん、注目したいのは自動調理自販機です。自動調理自販機は調理したものを冷凍して長期間保存を可能にするだけでなく、独自のスチーム技術によって解凍・調理が可能。持ち帰り調理する手間を省けることから消費者にとっては魅力的で、外食産業の人材不足を緩和する目的も達成できます。
冷凍食品技術は食材廃棄を減らし、長期間保存が可能なため流通促進効果も期待できます。今後の発展次第ではフードテックが取り組むべき問題との関わりが深くなるため、外せない最新技術事例のひとつです。
フードテックの問題点は費用面のハードルの高さ
フードテックは食糧問題を解決する救世主的な存在ですが、費用面のハードルがあります。システム開発にも費用がかかり、また食料などを使って実験するためその過程では費用がかかり、また環境への影響もあるでしょう。新規参入のハードルが高いことから、研究や実用化が進んでいない部分もあります。
フードテックに関するよくある質問
次にフードテックに関するよくある質問と回答を紹介します。
Q1.フードテックの意味を教えてください
フードテックとは最新テクノロジーで食問題を解決する技術です。フードとテクノロジーを組み合わせた造語です。金融とテクノロジーを合わせたフィンテックなどの造語と考え方は同じです。食の分野でもテクノロジーが進んでいるということです。
Q2.フードテックの代表例を教えてください
フードテックの代表例として、代替肉や昆虫加工食材が挙げられます。技術職が強いものとしては、食料配膳ロボットや食料盛り付けロボットが挙げられるでしょう。
Q3.フードテックの活用事例を教えてください
代替肉でバーガーキングと提携する「インポッシブル・フーズ」や、酪農・畜産の生産性向上と効率化を図る「ファームノート」が挙げられます。人材不足解消、食料を必要な場所に届ける、環境問題解消などにつながるサービスです。またUberEatsも実はフードテックの代表事例の一つです。
Q4.フードテックの特徴は何ですか?
フードテックには、食糧不足や飢餓問題を解消できる、フードロスを解消できる、人手不足を解消できる、食の多様化に対応できる、といった特徴があります。フードテックで解決できる問題やサービスは複数あり、食に関するあらゆる問題を解決する可能性があります。
Q5.フードテックの課題は何ですか?
フードテックには、システムの開発費用、食品の原材料などがかかります。費用がかかるため、参入障壁は高めと言えるでしょう。また先進的なサービスになる場合が多く、費用をかけてもうまく収益化できるとは限りません。こういった障壁から、可能性があっても参入しないという選択をしている企業は多いはずです。
まとめ
世界でも注目が高まるフードテック領域。ITと食産業はどちらもこれからの生活に欠かせないものであり、人間の営みに必要不可欠な分野であるために将来性も期待されています。業界に興味を持つ人は最新の事例に注目し、どのような人材が求められているかを見極めながら、市場に自分が貢献できる部分を伸ばしていきましょう。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。
「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。
「個別相談会」に申し込む
転職支援サービスに申し込む
※転職活動を強制することはございません。
レバテックキャリアのサービスについて