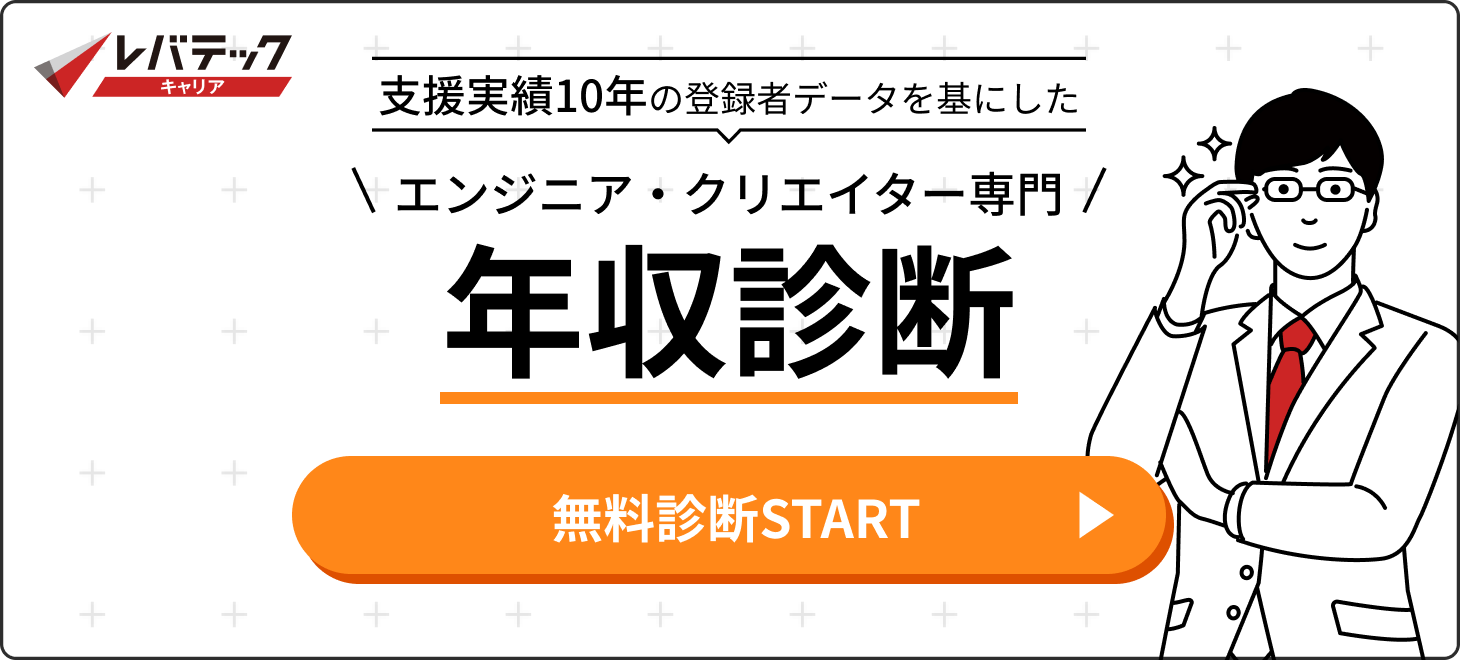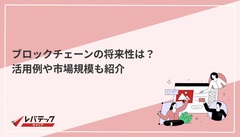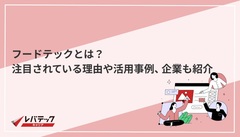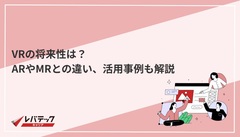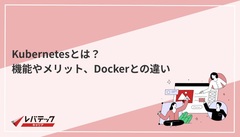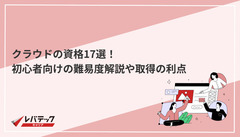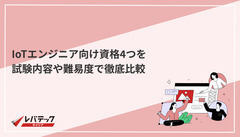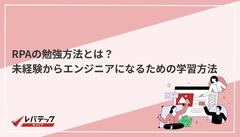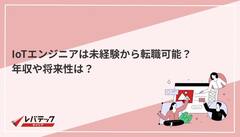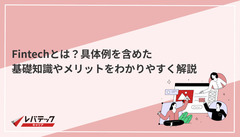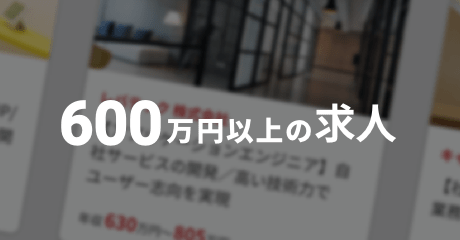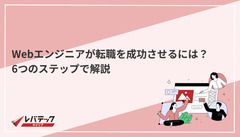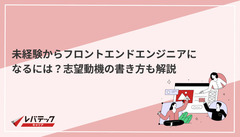- ブロックチェーンとは?
- ブロックチェーンの効率的な勉強手順
- 初心者向けのブロックチェーンの勉強方法
- ブロックチェーンエンジニア向けの勉強方法
- ブロックチェーンのおすすめの書籍
- ブロックチェーンのおすすめの学習サイト
- ブロックチェーンの勉強をする際に押さえておくべき用語
- ブロックチェーンの勉強方法に関するよくある質問
- まとめ
ブロックチェーンとは?
ブロックチェーンとは、複数のコンピュータで分散して取引情報などの機密情報を管理する仕組みです。ビットコインをはじめとした仮想通貨の盛り上がりに合わせて、ブロックチェーンをシステム開発にも適用できないか検討が進められています。
従来型のクライアントサーバシステムに代表される中央集権型での管理と比較して、ブロックチェーンによる分散管理はセキュリティレベルやシステムの継続性向上、コスト低減などのメリットがあるといわれています。
ブロックチェーンは新しい技術であり、主に実証実験などの形で検討が行われていますが、一部ではすでに実用化されています。実用化の例としては仮想通貨や電力取引、サプライチェーン管理などへの適用などです。
関連記事:ブロックチェーンの将来性は?活用例や市場規模も紹介
ブロックチェーンの効率的な勉強手順

ブロックチェーン開発に携わりたい、知識を深めたい方は多いですが「何から手をつければいいか」と悩む方は多いです。プログラミングなどと比較しても、用語自体が難しい・馴染がないこともあり、何から取り組めば良いか分からない方は多いでしょう。そこで、ブロックチェーンの勉強をスムーズに進める順番を解説します。
1.ブロックチェーン(ビットコイン)の概念
ブロックチェーンとはすなわちビットコインです。まずは基本的な概念を学習することから始めます。ブロックチェーンは改ざんできない点に価値のあるシステムですが「なぜ改ざんできないのか」を理解してからコードの学習に入るとスムーズです。
ブロックチェーンプログラミングを学ぶ場合、最初にプログラムを書くことが考えられがちですがそもそも概念の理解が不十分だと次のステップであるスマートコントラクトが理解できません。ビットコインの概念はオンライン学習サイトや書籍で入門者向けに丁寧に解説されているので、利用してみると良いでしょう。
2.イーサリアムとスマートコントラクトの概念
イーサリアムとは、「スマートコントラクト」を利用するための分散型アプリケーションを構築するプラットフォームです。スマートコントラクトは、人を介さず自動で契約を実行する仕組みです。
イーサリアムはGethというツールを使い、スマートコントラクトを書くにはSolidityという言語を用います。先に、イーサリアムの仕組みを理解しておきましょう。
おすすめしたいのが、計画書であるイーサリアムのホワイトペーパーを読むことです。内容は決して易しいものではありませんが、ビットコインをどのように応用しスマートコントラクトが構築されるのか理解できるようになるでしょう。自分に適した学習方法で、これ以降のツールの使用方法やスマートコントラクトの記述方法を理解する基礎を作ります。
3.イーサリアムノード(Geth)
1、2のステップを経て各ツールの意味が把握できたところで、イーサリアムノードを理解し動かしてみましょう。Gethとは「Go ethereum」を略したもので、Go言語で実装されたイーサリアムを指します。
Gethを学ぶ際は実際に動かしてみましょう。イーサリアム入門ではイーサリアムとは何かの基本から、実際に触れてみることまで可能です。経験者やより深い知識を知りたい方向けに、Gethの詳細なドキュメントであるGetting Started with Gethも公開されています。
4.スマートコントラクトの開発知識
Gethを理解できたら、スマートコントラクトプログラミングを始めましょう。スマートコントラクトを書くためにはSolidityという言語を使います。Solidityの学習は書籍やオンラインでも可能です。
早くて1日あればSolidityを理解し、スマートコントラクトを書けるようになるでしょう。スマートコントラクトにアクセスするためにはクライアントツールが必要で、ブラウザに埋め込むJavaScriptであるWeb3.0などの学習も始めます。
5.イーサリアム以外のブロックチェーン
スマートコントラクトの知識が深まると、開発フレームワークも理解できるようになるでしょう。イーサリアム以外のGoQuorumやCorda、Hyperledgerなど、他ブロックチェーンの学習を進めてもこれまでより深く理解できることが実感できるでしょう。もしイーサリアムではなくGoQuorumを利用しブロックチェーンの勉強をしていても、基礎であるビットコインとイーサリアムの概念を押さえておけばスムーズに理解できます。
初心者向けのブロックチェーンの勉強方法
ここからはブロックチェーンの勉強方法を紹介します。ブロックチェーンは注目の技術なので、勉強方法は多岐に渡ります。各方法の特徴をおさえて、自身に合う勉強法を選択しましょう。まずはブロックチェーンに初めて触れる入門者に向けた基礎知識の学び方を紹介します。ブロックチェーンはそのイメージから難しく感じられがちですが、これらの勉強方法なら身近に感じられるでしょう。
初心者用の書籍で基礎知識を学ぶ
ブロックチェーンは大きな話題を集めた技術であることもあり、多数の関連書籍が出版されています。
ブロックチェーン関連書籍としては、主にビジネス面での活用をテーマとしたビジネス書と、エンジニアリングの観点からの技術書に分かれます。エンジニアであったとしても、ブロックチェーン技術のビジネス活用方法について学ぶことは実務上重要なので、可能であればビジネス・技術の両面の知識を身につけると良いでしょう。
初めてブロックチェーンに触れる方には、基礎知識から丁寧に教えてくれる書籍がおすすめです。まずは基本的な部分から入ると途中でつまづくことを防ぎ、正しくブロックチェーン技術を理解できます。
勉強会やスクールを活用する
ブロックチェーンの盛り上がりに合わせて、ブロックチェーンに関する勉強会やセミナーなどが開催されているため、独学が難しいと感じる方は活用してみましょう。特にブロックチェーンに関して全く知識がなく、どのように学習を開始したら良いか分からない場合などは、一度セミナーに参加して基礎的な知識を身につけると良いです。
暗号資産のホワイトペーパーを読む
ホワイトペーパーとは、暗号資産の計画書です。仮想通貨に投資する方が判断材料として活用したり、ブロックチェーン(ビットコイン)を勉強する方が仕組みを理解するために読んだりすることもあります。ホワイトペーパーでは、各暗号資産の特徴や目的、販売方法、流通規模やロードマップなどが説明されています。
ブロックチェーンを勉強する上で参考にしたいのは、暗号資産の代表格であるビットコインのホワイトペーパーです。ここにはブロックチェーン技術の仕組みが詳しく解説されているため、ブロックチェーンの基礎学習としておすすめします。
YouTubeなどの解説動画を見て学習する
YouTubeでは、有識者がブロックチェーンを分かりやすく解説する動画を公開しています。ラジオ感覚で視聴できるので、隙間時間でブロックチェーンを学びたい方にはおすすめです。
ただし、YouTubeだけを信じるのではなく自分で学習範囲を広げ、書籍や実際のホワイトペーパーなど動画以外でも参考元を増やしておくと安心です。ほかの勉強法も組み合わせると良いでしょう。YouTubeの投稿者は実際にブロックチェーンを活用するエンジニアなのか、IT関連に専門性が高い方なのかをチェックした上で学習に役立てることをおすすめします。
書籍で開発の基礎を学ぶ
ブロックチェーン関連書籍には、基礎知識からもう一歩踏み込んだ開発知識関連のものも多数出版されています。基本的な概念が理解できたら、開発の基礎を学ぶと良いでしょう。
気をつけたいのは書籍の情報は次第に古い情報になるため、コードが動かない可能性が出てくることです。実際に動かすときの基礎動作を理解するため、全体構造の把握のために利用してみましょう。
ブロックチェーンを実際に体験してみる
ブロックチェーンの理解を深めるには、実際にプログラムを動かしてみたり、ブロックチェーンが使われているシステムに触れてみたりすることがおすすめです。実際にプログラムを動かすことによって知識の定着が見込め、使用される場面を理解することで学習効率が上がります
まずは、書籍やWeb上にあるサンプルプログラムを実際に動かしてみることから始めてみると良いでしょう。また、ブロックチェーンが日常生活においてどう役に立つかを体験できるWebアプリを公開している企業もあるので、活用すると効果的です。
資格の取得を目指す
ブロックチェーン関連資格として、現在では日本クリプトコイン協会(JCCA)が実施する暗号通貨技能検定が存在します。
暗号通貨技能検定に合格するためにはブロックチェーンや仮想通貨に関するビジネス面と技術面の両面からの知識が求められます。この資格は初級、上級といったレベル分けが存在し、資格を取得するためにはそれぞれ対応する講座を受講する必要があります。ブロックチェーンについて初めて学ぶのであれば、まずは初級検定講座を受講し、資格取得を目指すことをおすすめします。
ブロックチェーンエンジニア向けの勉強方法
すでにエンジニアとして経験がある方に向けて、ブロックチェーンエンジニアになるための勉強方法を紹介します。ブロックチェーンは人気かつ開発も活発なので技術の進化が早いです。一度勉強を終えても、すぐにブラッシュアップしていかなければ時代に置いていかれてしまうでしょう。ブロックチェーンに限らず最新技術の動向を追う方法を紹介します。
SNSなどで最新動向を情報収集する
IT業界は日々進化し続けています。次々と新しい技術が出てくるため、常に最新の情報を手に入れることが重要です。ブロックチェーンでも、Web3.0など次世代型の新しい概念が次々と登場しています。こうした最新動向は常に情報を収拾しアップデートしていく必要があるでしょう。
SNSの特徴は、一人で場所を選ばず最新の情報を手に入れられることです。SNSを活用することによって、わずかな時間でも手軽に最新の情報を収集をすることができます。また、有名なエンジニアもSNSで発信していることが多く、手軽に情報を手に入れ、直接やり取りができるチャンスもあります。
最新の情報を仕入れておき、実務に役立てましょう。ビジネス的観点も持っておくとエンジニアとしての地力向上に繋がります。ただし、情報の信頼度を確かめるためにも、自分で情報を精査できる能力が重要です。
専門的な記事を読む
専門的な記事にはブロックチェーンの基礎ではなく、開発事例や市場価値、実際に起こった問題点などが取り上げられています。より実践的なブロックチェーンの活用法を学ぶ上で、参考になるでしょう。
より専門性の高い記事を読むには、国内メディアだけでなく海外の記事も読み解く必要があります。翻訳された記事や自分で記事を読み進めてみても良いでしょう。
開発に活かせる書籍や情報で学習する
開発に活かせる書籍や情報もありますが、書籍の情報は次第に古くなる点に注意しましょう。記載されている情報が古くないか、自分の求めている情報は記載されているか確認した上で活用するのがおすすめです。
また、インターネット上にも多くの情報が公開されています。多くの有益な情報を無料で確認できるので、費用を抑えて学習したい方は活用すると良いでしょう。一方でインターネットの情報は情報元が不透明です。必ず情報が正しいか確認しましょう。
関連記事:【翻訳記事】Pythonを使ったブロックチェーンの学習
最新のGitHubの情報で開発を進める
プロジェクトでも活用されるGitHubの情報を参考に開発を進めると「古い知識」や「使えないコード」といったノイズなしにブロックチェーンを体感できます。先端IT技術は更新も早いため、可能な限り生きたログを活用するのがポイントです。
個人でもGitHubのベース部分は利用可能なので、勉強のためにダウンロードしておくと良いでしょう。
ブロックチェーンの勉強におすすめの書籍

ブロックチェーンの勉強に書籍を利用したくても、どれから見れば良いか悩む方は多いでしょう。書店やインターネットの試し読み機能で少し中身を確認しただけでは、自分に合うか分かりにくいのが実情です。
実際ブロックチェーンに関連する書籍は大量に出版されているため、適切に選ばないと時間が無駄になる可能性があります。ここからはブロックチェーンを勉強する際に役立つ書籍を3冊紹介します。
『ブロックチェーン・プログラミング仮想通貨入門』(講談社、山崎 重一郎、安土 茂亨、田中 俊太郎)
ブロックチェーンのプログラミングについて、基礎から、運用可能な実用システムの構築ができるレベルまで学習できる入門書です。言語はRubyを使ってプログラミングを解説しています。実装例を用いて解説をしているため、実際に手を動かして理解をしたい人に特におすすめです。
『ブロックチェーンアプリケーション開発の教科書』(マイナビ出版、加嵜 長門、篠原 航)
ブロックチェーン技術の理論的背景や現在の動向を解説に加え、サンプルコードを交えて開発の具体例や考え方を紹介しています。ブロックチェーン技術を、理論と実践の両面から理解するための1冊です。
初めてブロックチェーンを学ぶ人には、少し内容が難しくなっています。ブロックチェーン技術を理解したいエンジニア、ディレクターやMVCフレームワークなどでアプリケーション開発を経験したことがあるエンジニアに向けた本です。
『堅牢なスマートコントラクト開発のためのブロックチェーン[技術]入門』(技術評論社、田篭照博)
ブロックチェーンの暗号化技術のほか、サンプルも含めたスマートコントラクト開発の解説、イーサリアムのセキュリティ対策まで言及している1冊です。特にセキュリティ対策について詳しく解説しています。
スマートコントラクトでシステム開発を企画している方に特におすすめです。
ブロックチェーンのおすすめの学習サイト
書籍同様、ブロックチェーンを学習できるWebサイトは複数あります。また、提供企業は海外企業が多いですが、多くの日本語に対応しています。技術面だけでなく、語学面での不安を抱いた方も安心して利用できるでしょう。ここからは、ブロックチェーンの勉強におすすめの学習サイトを紹介します。
BinanceAcademy
仮想通貨取引所Binanceが提供する、仮想通貨・ブロックチェーン技術に関する教育プラットフォームです。ブロックチェーンの基本から高度な技術、仮想通貨の取引戦略、セキュリティの向上方法といった、さまざまな教材が用意されています。初心者から上級者まで幅広いニーズに対応しています。また、最新の情報やトレンドについてもすぐに教育コンテンツに反映し、ユーザーが常に最新の知識を獲得できるようサポートしています。
また、BinanceAcademyは日本語、英語をはじめとした多くの言語に対応していて、世界中の学習者が利用できるようになっています。
CoinbaseEarn
仮想通貨取引所Coinbaseが提供する、仮想通貨を学びながら実際に通貨を獲得できるサービスです。教材やビデオなどの学習コンテンツで仮想通貨について学習を進め、その後クイズに正解することで実際の仮想通貨をもらえます。通貨は実際にユーザーが売却したり、そのまま保有することが可能です。
サービスを受けるにはCoinbaseのアカウントが必要となり、アカウント作成には特定の地域に住んでいるなどの条件を満たなければならないので注意してください。また、2024年4月時点では日本語に対応していません。利用するには英語力が求められる点も合わせて注意してください。
CryptoZombies
Loom Network社が提供する、ブロックチェーンやスマートコントラクトの開発を学ぶためのオンラインプラットフォームです。学習コンテンツは、スマートコントラクトの基本から応用までをカバーしています。無料で使用でき、BinanceAcademy同様、日本語も含む多言語に対応しています。
ゲーム形式のプログラミングレッスンで、ユーザーは実際のコードを書きながら学び、ステップ形式でスマートコントラクトの開発スキルを磨けます。プログラミングを全く触ったことがない人も対象としているため、初心者から経験豊富な開発者まで、ブロックチェーン技術習得の助けになるでしょう。
ブロックチェーンの勉強をする際に押さえておくべき用語
ブロックチェーンを勉強すると、他業界では使用されない多くの専門用語が出てきます。ブロックチェーンに対して「難しそう」と感じるのは、この用語が影響しているともいえます。これらの単語を理解しておかないと、ブロックチェーンの勉強が非効率になるため、事前に確認しておきましょう。ここからは、ブロックチェーンを勉強する際におさえておくべき用語を紹介します。
マイニング
ブロックチェーンでは新たに行われた取引の妥当性と整合性を確保するために、ブロックチェーンに新たな電子署名(チェーン)を追加する作業を各コンピュータで行います。この作業をマイニングといいます。
マイニングの実施には報酬が与えられますが、その報酬はブロックチェーンに対して最初に電子署名を追加したコンピュータに対して支払われます。
マルチシグネチャ
ブロックチェーンでは悪意のあるコンピュータによる改ざんを防ぐために、複数の秘密鍵により合意が得られないと処理の継続を行えない仕組みとなっています。これをマルチシグネチャと呼びます。
たとえば、ブロックチェーンでの取引を実施する前にあらかじめ秘密鍵を3つ発行しているケースでは、そのうち2つの秘密鍵がないと取引を実施できないようにしておきます。これにより、万が一秘密鍵が漏洩したとしても情報が改ざんされるリスクを減らせる仕組みです。
プルーフ・オブ・ワーク
プルーフ・オブ・ワークとは、取引データをブロックチェーンに追加していく際に、そのデータの正しさを仕事量によって証明する考え方のことです。
プルーフ・オブ・ワークを採用するブロックチェーンでは、計算量が最も多いコンピュータが行った計算結果を正しいものとして認めます。計算量を判断する方法としてブロックチェーンの長さに注目し、最も長いチェーンをもった取引データが唯一正しいものだと考えます。もし悪意を持ったコンピュータが取引データを改ざんしようとしても、悪意を持った一部のコンピュータの処理より、多数の正しい処理を行うコンピュータがより早くチェーンを追加していくため、全体として悪意を持ったコンピュータの処理を除外することができます。
リレー取引
ブロックチェーンではP2P技術により、取引ネットワークに参加するコンピュータ間を経由してバケツリレーのように処理内容を送受信します。これをリレー取引といいます。リレー取引によりシステム全体での耐障害性や処理分散を実現しています。
中央に処理をつかさどるサーバが存在しないブロックチェーンでは、単体のコンピュータの耐障害性は高くありませんが、P2Pを利用することで全体としての耐障害性は高まります。
Solidity
Solidityは、Ethereumブロックチェーン上にアプリケーションを構築するために利用されるプログラミング言語のことです。構文はJavaScriptに似ており、比較的初心者でも扱いやすい言語仕様となっています。
Ethereumネットワーク上ではEthereum Virtual Machine(EVM Code)により処理を記述しますが、EVM Codeは低水準言語のバイトコードの形式であり人間の可読性は低いです。SolidityはEthereumを手軽に扱えるように高水準言語として設計されており、Solidityで記載されたプログラムをコンパイラによりEVM Codeに変換することができます。
EIP/ERC
EIPとは、Ethereum Improvement Proposalの略称であり、Ethereumのシステム全体に関する改善提案のことです。また、ERCはEthereum Request for Commentsの略称であり、Ethereum上で動作する機能の実装に関わる標準仕様の提案のことです。
EIP/ERCはGitHub上にてチケット管理されており、コミュニティ内でEthereumブロックチェーンの機能更新やアプリケーションで使われる標準規格などが提案・議論されています。コミュニティによりEIP/ERCが承認されれば、Ethereumの技術仕様として採択されます。
ブロックチェーンの勉強方法に関するよくある質問
ブロックチェーンは暗号資産(仮想通貨)での取引時に利用される技術です。不正・改ざんが防げる点で注目を浴びています。そのため、ブロックチェーンを学びたい方は増えているようです。しかし、馴染のない言葉・技術であることから、勉強の仕方が分からないなど、ブロックチェーンに対する悩みを抱える人も少なくありません。そこで、ここではブロックチェーンの勉強方法に関するよくある質問についてまとめました。
Q1. ブロックチェーンを勉強する順番を教えてください
まずはブロックチェーンの仕組みを理解した上で、イーサリアムなどのスマートコントラクトの書き方を勉強しましょう。ブロックチェーン・スマートコントラクトの理解はビットコインの理解が前提となっており、そのためにはビットコインとは何かを学ぶ必要があります。
関連記事:ブロックチェーンに関する資格を解説!取得するメリットとは
Q2. ブロックチェーンエンジニアの難易度はどれくらいですか?
ブロックチェーン開発には高度な数学の知識や専門性の高いWeb知識が必要なため、簡単になれる職種ではないといえます。ブロックチェーンエンジニアを転職で目指す場合、「未経験OK」とする企業もありますが難易度は高いです。一定以上の開発経験も必要で、何より自分のものにするまで勉強時間は相当数かかります。
Q3. ブロックチェーンプログラミングの参考書を教えてください
参考書として手元に置いておくのにおすすめしたいのは、基礎・概念を網羅している参考書です。このほか、セキュリティに興味があるなら関連した書籍を、よりビジネス面を知りたい場合はその関連書籍を選ぶと良いでしょう。書籍は発行した年や情報元を確認し、勉強に活かすのがポイントです。
Q4. 暗号通貨(仮想通貨)は何から勉強すればいいでしょうか?
何から手をつけて良いか分からない場合、まずは暗号通貨を分かりやすく解説するYouTubeなどのコンテンツから触れることをおすすめします。ブロックチェーンを活用した最初の仮想通貨はビットコインです。概念や基本を学びたい場合は、まずビットコインとは何か、活用法や問題点を知ると理解が深まるでしょう。
Q5. ブロックチェーンの欠点は何ですか?
ブロックチェーンの欠点は大まかにいうと、下記の3つが挙げられます。
-
・記録したデータの削除、修正が難しい
・処理速度が遅い
・悪意を持つユーザーが入り込む可能性もある
しかし、ブロックチェーン技術はまだ発展途上であり、今後の改善が期待されています。
まとめ
本記事では、ブロックチェーンの勉強方法を紹介しました。
ブロックチェーンは近年注目を集めている分散型の暗号化手法です。ブロックチェーンの勉強を行うことで、ブロックチェーン技術を利用するエンジニアを目指す際にはもちろんのこと、エンジニアとしての地力向上につながり、キャリアアップも期待できるでしょう。客観的なスキルを証明するために、資格を取得しておくこともおすすめです。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。
「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。
「個別相談会」に申し込む
転職支援サービスに申し込む
※転職活動を強制することはございません。
レバテックキャリアのサービスについて