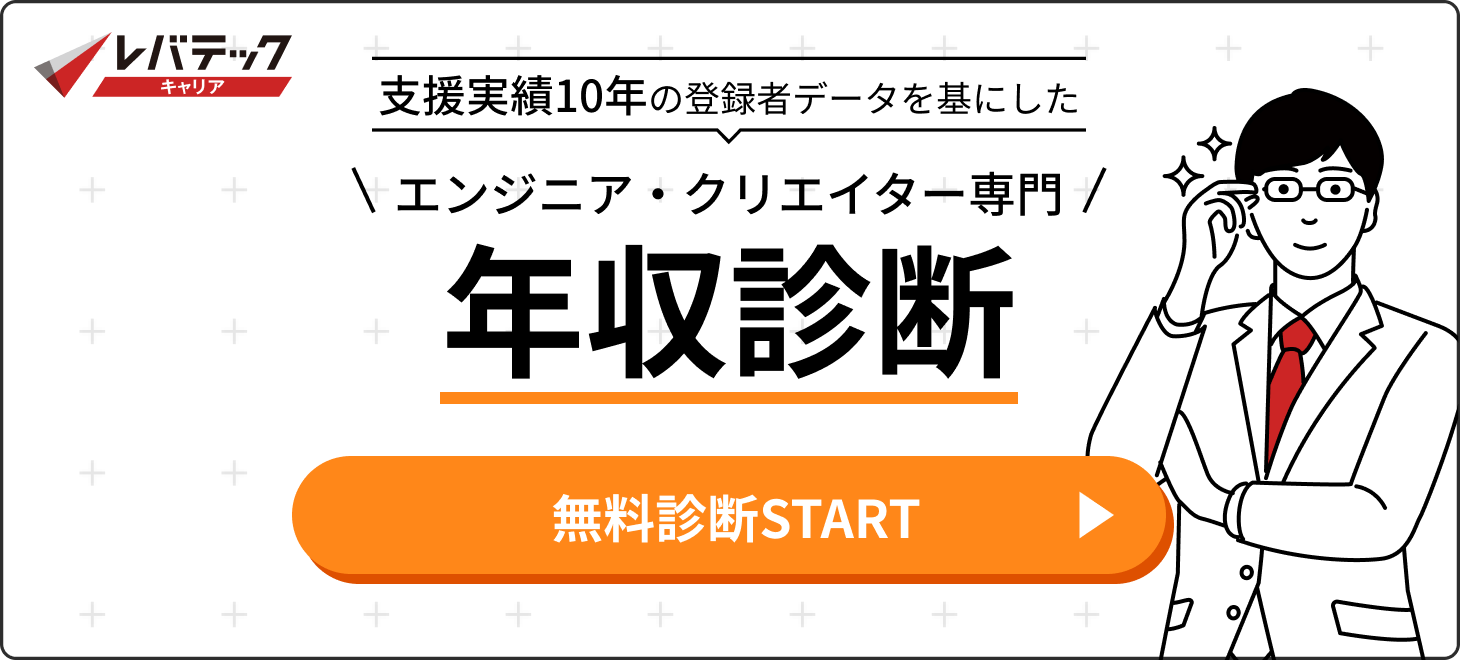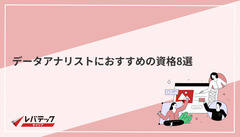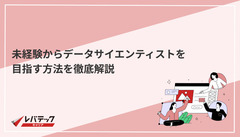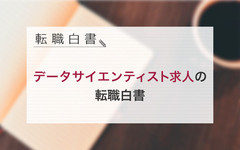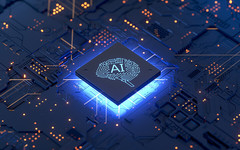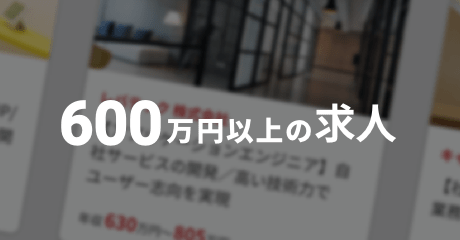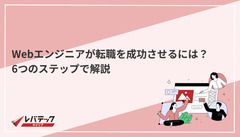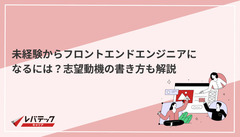- データサイエンティストが身につけるべき6つの基礎スキル
- データサイエンティストになるための勉強ロードマップ
- データサイエンティストになるための勉強手段
- データサイエンティストの業務に役立つ知識
- データサイエンティストに必要なスキル習得にかかる勉強時間
- データサイエンティストを目指す上で役立つ資格
- データサイエンティストに関するよくある質問
- まとめ
データサイエンティストが身につけるべき7つの基礎スキル

データサイエンティストが身につけるべき基礎スキルとして、「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」「ビジネス力」「プログラミングスキル」「マーケティングスキル」「コンセプチュアルスキル」が挙げられます。それぞれ、詳しく見ていきましょう。
1.データサイエンス力
データサイエンス力は、統計手法や機械学習を通してデータを分析し、ビジネスに必要な知見を抽出する力のことを指します。先に紹介した「データサイエンティストスキルリスト ver4」によると、見習いレベルではたとえば以下のようなスキルが求められています。
-
・ 得たい知見に応じてデータを集計できる
・ 予測のために単回帰分析や重回帰分析を活用できる
・ ライブラリをつかったサポートベクタマシンによる分析の実行・評価ができる
データサイエンス力の勉強方法
統計学や機械学習に取り組んだことのない方にとっては、書籍や解説サイトなどを読んでもわからないことだらけで理解が進まないことがほとんどでしょう。
勉強方法のコツとしては、わからないことがあっても深追いせずに、まずは書籍なり解説サイトなりを一通り流し読みをして全体像を掴むことです。一度目でしっかり理解できなくても、全体像を掴んでおけば、二度目三度目に読んだときに知識がつながって、すんなり理解できることも少なくありません。
2.データエンジニアリング力
データエンジニアリング力は、データサイエンスの手法をプログラムやデータ基盤構築に落とし込み、コンピュータを使って実現することができる能力を指します。「データサイエンティストスキルリスト ver4」では、見習いレベルにおいて以下のようなスキルが定義されています。
-
・ データベースから何らかの方法を使ってデータ抽出ができる
・ 対話型の開発環境を用いてデータ分析やレポートの出力ができる
・ SQLの構文を一通り活用できる
データエンジニアリング力の勉強方法
データエンジニアリング力を高めるために重要となるのは、プログラミングのスキルです。データサイエンティストが活用できるようにしておくべきプログラミングスキルは、Python、R、SQLなどがありますが、まずはPythonから取り掛かることをおすすめします。
Pythonはデータサイエンティストのあいだで最も人気があるプログラミング言語で、活用する案件も多いですし、人気があるがゆえに情報も多く習得もしやすいという特徴があります。データサイエンス力を伸ばすときに身につけた知識をPythonで実際に実装することで、並行してスキルアップを狙っていくという手法が効率が良いです。
3.ビジネス力
データを扱う仕事は、データを活用することができる事業があってはじめて成り立ちます。事業の課題を正しく理解し、それを解決するためのデータを抽出、さらには活用して意思決定につなげていくという流れが重要です。これを実現するために必要なのがビジネス力になります。「データサイエンティストスキルリスト ver4」では、見習いレベルとして以下のようなスキルが定義されています。
-
・ 与えられた分析課題について正しく情報収集をおこなうことができる
・ 分析結果の意味合いを正しく言語化することができる
・ 担当する分析プロジェクトにおけるKPIを理解している
ビジネス力の勉強方法
ビジネス力は非常に幅の広いスキルで、一朝一夕に身につけられるものではありません。日常の業務でわからないことをそのままにせずしっかり知識として吸収する、課題が生じたときにはその対策について関連書籍などから情報収集をおこない検討するといったことが総合的なビジネス力を高めるために重要となります。
とはいえとっかかりとしては、経営やマーケティングに関する書籍を読んで知識をつけたり、著名な経営者の書籍を読んで考え方を吸収したりといったことが挙げられるでしょう。
4.プログラミングスキル
データサイエンティストとしてのキャリアを追求する上で、プログラミングスキルは不可欠です。データサイエンティストはデータを探索し、洞察を得るためにプログラムを用いることが多いため、そのスキルは大きな価値を持ちます。
将来的なキャリアの階段を上る際にも、堅実なプログラミングスキルは強力な武器となるでしょう。そして、テクノロジーの世界は日々進化しており、最新の開発トレンドや実用化された新技術に対する理解も重要です。常に学び続け、自身のスキルセットをアップデートする意欲が求められるのです。
プログラミングの勉強方法
データサイエンティストとしてのプログラミングスキルを向上させる方法は、まず基本から始め、PythonやRなどの言語を学びます。オンラインコースや書籍を利用して基礎を固めたら、実際のプロジェクトに取り組むことで経験を積みます。
Kaggleなどのプラットフォームで競技や課題に挑戦することも役立ちます。さらに、データ処理ライブラリ(Pandas、NumPy)、可視化ツール(Matplotlib、Seaborn)、機械学習ライブラリ(Scikit-learn、TensorFlow)の使用法も習得します。コードの読解と書き方を繰り返し実践することで、自信をつけつつ実力を高めていくことが重要です。
5.マーケティングスキル
データサイエンティストには、マーケティングにおけるデータ分析の重要性が高まっています。したがって、マーケティング関連の知識とスキルを備えることが求められます。
Webマーケティングやコンテンツマーケティングなどの一般的な手法を理解し、習得することが重要です。また、セグメンテーションやターゲティング、ポジショニングなどの基本的なマーケティング戦略に関連する知識の習得もおすすめです。
マーケティングの勉強方法
データサイエンティストがマーケティングを学ぶ方法は、まずマーケティングの基本原則を理解し、データ分析と組み合わせて活用します。オンラインコースやブログ、書籍を通じてWebマーケティングや消費者行動の知識を得ることが重要です。
実践的なスキルとして、データ分析ツール(PythonやR)を活用して広告キャンペーンの評価や顧客セグメンテーションを行う経験を積みます。また、ABテストや効果測定の手法を学び、データ駆動型のマーケティング戦略を構築します。連携やコミュニケーションスキルも磨き、マーケティングチームとの協力を強化します。
6.ヒューマンスキル
ヒューマンスキルを一言で言い換えると「対人関係能力」です。つまり人間関係を円滑に構築する能力とも言えるでしょう。データサイエンティストは他職種と連携して業務にあたることが多いので、とても重要なスキルです。ヒューマンスキルと一言で表しても具体的には次の8つに分類されます。
-
・ネゴシエーション能力:様々な交渉や折衝を遂行する能力
・ヒアリング能力:相手の話に耳を傾け、何を課題としているのか、何を必要としているのかを引き出す能力
・リーダーシップ能力:目標を達成するためにチームを統率・まとめる能力
・プレゼンテーション能力:自分の考えやアイデアを、正しくかつ効果的に伝える能力
・コーチング能力:人材の能力を最大限引き出す能力。人材育成の力
・コミュニケーション能力:対人関係において適切な意思疎通を図り、円滑な人間関係を築き上げる能力
・ファシリテーション能力:会議やミーティングの場をスムーズに進行させる能力
・向上心:絶えず努力をし、自分の成長に向けて積極的に取り組んでいく前向きな意欲
7.コンセプチュアルスキル
データサイエンティストの役割は、データに秘められた本質を解き明かすことです。このため、情報を総合的に捉え、本質を把握する「コンセプチュアルスキル」が不可欠です。具体的なスキルは以下の通りです。
-
・ロジカルシンキング:事実や前提をもとに、論理的な手順で結論を導き出す思考方法です。因果関係や論理の鎖を追求して、論理的に正当な結論に至る能力を指します。
・ラテラルシンキング:通常の発想から外れて、新しい視点やアプローチを見つける能力です。非常識なアイディアやアナロジーを活用して問題を解決したり、創造的な解決策を見つけたりします。
・クリティカルシンキング:情報を分析し、その信頼性や妥当性を評価する能力です。主張や主題を検証し、論理的な欠陥や偏見を見抜いて正確な判断を下すことを指します。
データから得られた情報を分析する際に、多角的な視点で考える能力が求められます。異なる思考パターンを試みることで、より深い理解が得られるでしょう。
コンセプチュアルスキルの勉強方法
データサイエンティストのコンセプチュアルスキル向上の方法は、異なる分野の書籍や論文を読み、幅広い視点を養うことです。さまざまなデータセットや問題に挑戦し、データの背後に潜むパターンや洞察を把握します。チーム内でのブレインストーミングや意見交換を通じて、新たなアイディアを引き出す習慣を養いましょう。
また、データ分析結果を他人にも理解しやすく伝える練習を通じて、コミュニケーションスキルを高めます。さらに、異なる専門家との協力や学習を通じて、ラテラルシンキングを養い、非常識なアプローチも探求します。これらの方法でコンセプチュアルスキルを磨くことで、データをより深く理解し、革新的なアイディアを生み出せる能力を向上させられます。
データサイエンティストになるための勉強ロードマップ

データサイエンティストになるために身につけなければならないスキルは多岐に渡ります。多くの知識を効率的に身につけるためには、まずはデータサイエンティストに必要なスキルの全体像を把握しておきましょう。そのほうが、今自分が取り組んでいることの意味を見出しやすく、モチベーションの維持につながるためです。
また、身につけるスキルによっては、特定の知識を前もって身につけておいたほうがスムーズに学習を進められるというようなものも存在します。そのため、学習の順序もしっかり検討しておいたほうがよいです。
ここでは、データサイエンティストになるために必要な学習の全体像とその順序について、代表的なものをご紹介させていただきます。
データサイエンティストの仕事内容や必要なスキル・知識を知る
データサイエンティストの仕事内容として、以下のようなものが挙げられます。
-
・ データ分析環境の構築
・ データの分析とレポーティング
・ ビッグデータの活用と事業利益への貢献
データサイエンティストに必要なスキルや知識は幅広いですが、データサイエンティスト協会は以下のように定めています。
-
・データサイエンス力…情報処理・人工知能・統計学など、情報科学系の知識を使いこなす力
・データエンジニアリング力…データを意味のある形に整え、システムに実装し、その運用までをこなす力
・ビジネス力…ビジネス課題とその背景を理解し、整理しながら解決に導く力(※1)
関連記事:
データサイエンティストの仕事内容を解説!必要なスキル、知識、学習方法もご紹介
データサイエンティストに必要なスキル|スキルチェックの仕方も紹介
データサイエンティストに求められるプログラミング言語と学習方法
どの分野に特化したデータサイエンティストになるのか考える
データサイエンティストで重要なのは、エンジニアリングに主眼を置くか、それともビジネスに重点を置くかを選び、方向性を確定させることです。エンジニアリングに焦点を当てる場合、開発に関する知識や高度なエンジニアリングスキル、データの蓄積とパイプライン構築の能力、最新のディープラーニング手法に関する知識の習得がおすすめです。
一方、ビジネスに特化するのであれば、プロジェクトマネジメントのスキルや問題特定のコンサルティング的スキル、ウェブマーケティングの能力を学ぶことが重要です。ビジネス志向の場合、幅広いマーケティング知識や視覚化ツールの利用、フロントエンド言語(HTML・CSS・JS)の理解、SEOやMA(マーケティングオートメーション)の知識が求められます。
さらに、Moocや書籍での学習だけでなく、実務経験を積む機会を持つことも成長に不可欠です。現在の職場でそのような経験を積むことが難しい場合は、転職も視野に入れて検討することも考慮しましょう。
統計の基礎・機械学習手法を身につけPythonで実装する
データサイエンティストを目指すにあたって必要なスキルの全体像が掴めたら、活躍するにあたって必ず必要になる統計知識や機械学習手法についての学習を進めていきましょう。いずれも、書籍だけで学習していると退屈ですし感覚も掴みづらいので、学習した内容をPythonを使って実際に実装してみるという学習方法をおすすめします。
機械学習をビジネスにどのように導入するか知る
次に、身につけた機械学習の知識を、どのように実際のビジネスに活用するのかについて学んでいきます。データ分析のプロセスのフレームワークとして、「CRISP-DM」というものがありますので、まずはこれに沿って機械学習をどのようにビジネスにおいて活用するのかのイメージを持っておきましょう。CRISP-DMは、以下の6つのプロセスで構成されています。
-
1. ビジネス課題の理解
2. データの理解
3. データの準備
4. モデル作成
5. 評価
6. 展開・共有
このフレームワークを習得するには、実務で繰り返し使っていくのが近道ではあるのですが、現在の仕事でそのような機会が無い方は、NishikaやKaggleなどのデータ分析コンペを活用すると良いでしょう。
関連記事:機械学習エンジニアとは?仕事内容や必要なスキル、将来性などを解説
SQLを書けるようにする
データサイエンティストとして仕事をするようになると、データの前処理などでSQLを利用する機会が増えます。SQLはデータベースからデータを抽出したり、複数のテーブルのデータを組み合わせたりできる、データベースを操作するための言語です。
データソースとしてデータベースに存在するデータを利用することも頻繁にありますので、Pythonなどのプログラミング言語だけではなく、データベース周りの知識も身につけておきましょう。
データサイエンティストになるための勉強手段
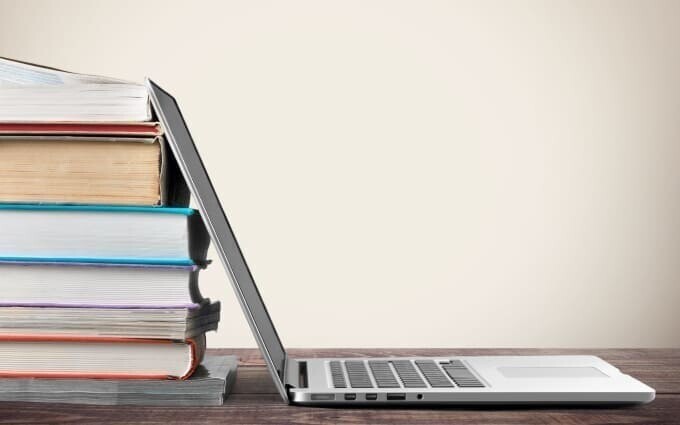
ここではデータサイエンティストになるためには具体的にどのような手段を使って勉強していくかについて解説します。学び方は大学や講座、勉強会に通って学ぶ方法と、独学する方法の大きく2通りに分けられます。以下では、それぞれのルートについて詳しく解説します。
大学・スクールに通って勉強する
体系化されたカリキュラムと講師によるサポートがある大学・スクールは、データ解析などの技術習得を効率的に進められます。
データを活用してロジカルに企業の進む先を示してくれるデータサイエンティストは産業界からの期待も高く、近年では専門スクールに加え、データサイエンティストの育成に取り組む大学も増加しつつあります。
専門の学部・学科が開設されている大学で学ぶ
日本国内においてデータサイエンス専攻の学部・学科が開設されている大学は滋賀大学、横浜市立大学、武蔵野大学など7大学です(2024年3月時点)。そのほかにも、理工学専攻で数理の知識を系統的に学ぶことで、データサイエンティストとしての素養を身につけられます。
また、データサイエンティスト協会のスキル委員は「データサイエンス力の視点では情報科学、データエンジニアリング力の視点ではコンピュータサイエンスの分野に進学することが効率的である」としている一方で、スキルの応用力を考慮した際に、物理や経済などの副専攻を履修したほうが良いと勧めています(※1)。
さらに、専攻として独立しておらず、情報系や理工学系の研究科が主体となって教育プログラムを展開している大学もあります。たとえば東京大学では、大学院情報理工学系研究科主導で「データサイエンスティスト養成講座」を開講しており、所定講義の履修(基礎課程・応用課程)や研究を遂行すること(実践課程)で、大学から修了証が授与される仕組みになっています(※2)。
※1 Data Scientist Society Journal 「DSになるために必要なこと」(2024年3月12日アクセス)
※2 東京大学「領域知識創成教育研究プログラム概要」(2024年3月12日アクセス)
データサイエンティスト向けの講座・勉強会で学ぶ
データサイエンティスト協会は、データサイエンスに関連する教育プログラム(※3)のリストを提供しています。
同リストは、統計数理研究所が「データサイエンティスト育成ネットワークの形成」の一環として国内外の教育プログラムをまとめたものであり、プログラミングスキルの習得からビジネス力の育成まで、幅広い育成コースを網羅した内容になっています。
ここでは、その中から2つの講座を抜粋してご紹介します。
・データサイエンス・オンライン講座
総務省統計局がデータサイエンス分野の人材育成のために開講しているオンライン講座です。「社会人のためのデータサイエンス入門」や「誰でも使える統計オープンデータ」といったテーマに分けられており、誰でも無料でデータサイエンスの基礎を学ぶことができます。内容も初学者向けなので、未経験者なら一度はチャレンジしておきたいオンライン講座です。
・現代統計実務講座
一般財団法人実務教育研究所が主催している文部科学省認定の通信講座です。データサイエンティストに不可欠な統計学のリテラシーを高め、仕事で使える実務統計を習得できるカリキュラム設計になっています。
また、経済産業省はIT・データ分野を中心に、今後の成長が見込まれる教育訓練講座を経済産業大臣が認定する「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」を設けており、認定獲得したプログラムを定期的にリストアップしています(※4)。
NECマネジメントパートナー株式会社が主催する「データサイエンティスト養成ブートキャンプ」や株式会社日立アカデミーが主催する「データ利活用技術者育成講座」など、クラウド、IoT、AI、データサイエンス分野の計87講座がまとめられています。ぜひ受講の参考にしてください。
※3 統計数理研究所「国内外の教育プログラム」(2024年3月アクセス)
※4 経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座一覧」(2024年3月アクセス)
独学で勉強する
データサイエンティストを目指している方の中には、学校や講座に通わず独学での勉強にチャレンジしたい方もいるでしょう。また、データサイエンティストに興味があるけれども、まずはさわりだけでも把握しておきたいという方もいるかもしれません。ここでは、そうした方に向けて、独学で勉強する方におすすめの書籍と資格をご紹介します。
データサイエンティストの勉強におすすめの本
データサイエンティストに求められる知識や技術は幅広く、単一の書籍から全てを学ぶことは困難です。幅広い知識を身につける必要があることを認識した上で、学習していくなかで自身に足りないものや目指していくべき方向性を特定しながら書籍を選んでいきましょう。
データサイエンティスト関係の書籍は多くの種類がありますが、データサイエンティスト協会がその中でも有用な書籍を推薦書籍リスト(※5)としてピックアップしてくれています。ここではその中から、特に未経験からデータサイエンティストを目指している方におすすめの本を紹介します。
『BIシステム構築実践入門 (DB Magazine Selection) 』(平井明夫著、翔泳社)
データベースに蓄積されたデータを有効活用するための「BI(ビジネス・インテリジェンス)」というシステムを構築するための技術解説書です。技術と業務の両面から、BIシステム構築に必要な知識を、実例ベースで基礎からやさしく解説しており、ビジネス・インテリジェンスに関する入門書であり、BIシステムに関わる人はまず最初に読むべき1冊だと勧めています。
『基本統計学 第4版』 (宮川公男著、有斐閣)
統計検定2級の範囲を体系立てて学習するのに適した書籍です。やや難しい箇所には印が付されており、読者の目的に合った学習ができるよう工夫されている1冊です。
『道具としてのビッグデータ』(高橋範光著、日本実業出版社)
IoT、インダストリー4.0などの流れを企業事例を交えながら解説し、ビッグデータを利活用する上でのノウハウをわかりやすく紹介している1冊です。
『実践データマイニング―金融・競馬予測の科学』(月本洋著、オーム社)
データマイニングを使って株価予測・競馬予測といった日常的なテーマを分析した内容の解説本です。具体的なINPUTデータとモデルを適用した結果についての解説もあるため、具体的なイメージが湧きやすいでしょう。
『Rによるデータサイエンス データ解析の基礎から最新手法まで』(金明哲著、森北出版)
2017年発売以来、重版を重ねている1冊です。多変量解析からデータマイニングまで豊富な情報がコンパクトにまとめられています。Rの勉強を始めたばかりの方は辞書代わりに手元に置いておくと良いでしょう。
『トップデータサイエンティストが教える データ活用実践教室』(高橋威知郎・安宅和人等著、日経BP)
価値のあるデータ分析を行う方法や、データ活用を実際にビジネスシーンに活かす方法など、データを扱う際に生じる疑問に対して、現役のデータサイエンティストが現場の視点をもって回答しています。
『わかりやすいパターン認識(第2版)』(石井健一郎・上田修功等著、オーム社)
2019年11月に第2版をリリースした機械学習を学ぶ入門書です。数理的な面から機械学習を学ぶ際、最初に読む書籍として専門家が勧めている1冊です。続編と合わせれば、機械学習の手法を一通り学べるでしょう。
※5 データサイエンティスト協会「推薦書籍一覧」(2024年3月アクセス)
データサイエンティストの勉強におすすめの学習サイト
データサイエンスの領域に期待が集まるのと比例し、従来の学習方法を発展させて効率的に学習ができるような学習サイトが充実しています。初学者の方が学習のとっかかりを掴むために有用ですし、不足している知識を補完するのにも有用です。
・Progate
プログラミング言語を実際にブラウザ上で入力し動かしながら学習を進められる学習サイトです。プログラミングの基礎的なことから手取り足取り教えてくれますので、データサイエンティストを志す方のみならず、プログラミングそのものをあまり触ったことがないという方にもおすすめの学習サイトです。データサイエンティスト関連のプログラミング言語では、PythonとSQLを学ぶことができます。
・Udemy
オンラインビデオによる講座が大量に掲載されている学習サイトです。データサイエンティストに関わるコースも多く存在していて、プログラミング言語の習得コースだけではなく、データサイエンティストを目指すために必要な知識の全体像を解説しているコースや、データのビジネス活用など実践的なコースも存在していて、どのようなレベルの学習者でも有益なコースが見つかるでしょう。
書籍や先ほど紹介したProgateと比べるとコースの料金は高価ですが、定期的にセールが実施されていますので、自分に必要なコースがセール対象となっていないか頻繁にチェックすることをおすすめします。
データサイエンティストの業務に役立つ知識
データサイエンティストとして活躍するには、ビジネス分野やデータサイエンス分野の幅広い知識も必要になります。幅広い知識を身につけることで、データサイエンティストとして業務をこなすだけでなく課題の発見や提案力アップにもつながるでしょう。
ITセキュリティに関する知識
ITセキュリティの基本となる3要素(機密性、可用性、完全性)について理解し、マルウェアなどによる深刻なリスク(消失・漏洩・サービスの停止など)の回避方法や、基本的な防御手法を心得ている必要があります。さらに、暗号化技術についての知見もあると業務で役立つでしょう。
基礎数学
データサイエンティストとして、平均(相加平均)、中央値、最頻値の算出方法や順序尺度、比率尺度といった統計手法を使いこなせるための統計数理知識は必要不可欠です。また、線形代数や微分・積分などの数学素養も求められます。
データ解析に関する基礎知識
階層クラスター分析を中心としたグルーピングに関する知識やサンプリング、データを可視化するために必要な抽出方法や加工方法に関する知識が求められます。さらに、ポアソン回帰やロジスティック回帰など、統計モデリングに使われる初歩的手法に対する理解もあると良いでしょう。
機械学習に関する知識
機械学習にあたる解析手法を複数理解し、機械学習に使われるプログラミング言語に関する知識を身につけると良いでしょう。また、教師あり学習と教師なし学習の違いを理解し、過学習に伴うリスクも把握しておく必要があります。ディープラーニングについての知見があるとなお良いでしょう。
語学力
データサイエンスの領域は非常に変化が激しいことが特徴です。最先端の知見や技術は英語や中国語の記事や論文で展開されることが多いので、新たに出た情報をすぐにキャッチするためには、語学力を身につけておくと良いでしょう。
日本は世界各国と比べるとデータサイエンス領域のリテラシーが高いとはいえず、出回っている情報も国外に目を向けたほうが豊富です。海外の情報ににアクセスできるようにしておくことで、ほかのデータサイエンティストを目指す人たちに大きな差をつけられます。
データサイエンティストに必要なスキル習得にかかる勉強時間
データサイエンティストに必要なスキルは複数あり、それぞれ勉強する必要があります。以下で各スキルの勉強時間について解説しますが、どのスキルも3ヶ月~半年程度の勉強期間が必要です。勉強を同時並行で進める場合はより時間がかかり、順次勉強を進める場合も単一スキルを身につけるよりは当然時間はかかります。
データサイエンス
データサイエンスの基礎知識を習得するには、3ヶ月~半年程度の期間が必要です。もともとの予備知識や学習能力などによっても変わってきますが、上記は完全未経験の場合の相場です。データサイエンスの基礎知識とは、AI、機械学習などが該当します。ただしこれらのプログラミングスキルではなく、概念理解のための基礎知識ということです。
統計学・数学
一般的なエンジニアにはそこまで必要ありませんが、データサイエンティストの場合は統計学や数学の知識が必須です。そしてこれらの基礎知識を身につけるのに要する期間は3ヶ月~半年程度です。数学などはもともとの知識が人によって異なりますが、たとえば高校レベルくらいまでの一般的な数学は理解している前提の期間になります。
プログラミングスキル
データサイエンティストの場合、PythonやRなどのプログラミング言語を習得する必要があります。プログラミングスキルの習得には、半年程度の期間が必要でしょう。もともと別のプログラミング言語スキルがあれば期間は短縮されます。プログラミングは知識を身につけた後に実際に手を動かして学ぶ必要があります。そのため勉強期間も長くなるということです。
勉強時間が短縮できるケース
基本的に、すでに知識や経験があれば勉強時間は短縮されます。たとえばもともと統計学の基礎の学習経験があれば、データサイエンティストに必要な統計学の知識を身につけるのも当然早くなります。エンジニアとしてAIなどでなくても本格的なプログラミング経験があれば、データサイエンティストに必要なプログラミングスキル習得期間も早まります。
データサイエンティストを目指す上で役立つ資格

データサイエンティストとしてのスキル・知識を証明するのに役立つ資格を紹介します。資格取得のための勉強は知識の習得にもつながりますので、必要に応じてチャレンジしましょう。資格を取得すれば評価アップと同時にスキルアップにもつながるということです。
基本情報処理技術者試験
基本情報技術者試験はIPAによるIT技術者のスキルを証明する資格のひとつです。出題範囲は広く、データサイエンティストに関連する分野でいうとデータベースやプログラミングなどのデータエンジニアリング力を問うものから、プロジェクトマネジメントやストラテジストなどビジネス力を問うものまで多岐に渡ります。
取得しておけば、データサイエンティストとしてのみならず、ITエンジニアとして一定のスキルを持っていることが証明でき、仕事の幅を広げられるでしょう。
応用情報技術者試験
応用情報技術者試験は上記の基本情報技術者試験の上位資格にあたる資格です。全てが選択問題だった基本情報技術者試験とは異なり、問題の一部は記述式で出題されることから、付け焼刃でないより実践的なスキルを要求される資格になります。
オラクルマスター
データベース管理ソフトウェア市場で日本において絶大なシェアを誇っているオラクルによるデータベース関係の資格になります。データベースの管理や運用、SQLの扱いなどが出題され、取得することでデータベースの扱いに習熟していることを証明できます。
データベースの扱いはデータサイエンティストとして不可欠なものになりますので、目指すのであれば取得しておいて損はありません。
データベーススペシャリスト試験
データベーススペシャリスト試験は、情報処理技術者試験のなかでも、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験のさらに上位である高度区分に属する資格です。データベースの基礎的な事項から、管理・運用の手法、SQLの読み解きやデータモデルの構築まで、データベースにまつわる事項が出題されます。
国家試験の中でも指折りの難関資格といわれていて、取得するのは簡単ではありませんが、その分取得できれば文字通りデータベースのスペシャリストとして信頼を勝ち取れるでしょう。
統計検定®
「統計検定」とは、統計に関する知識や活用力を評価する全国統一試験です。4級~1級まで5つのレベル(準1級含む)が設けられており、データ分析における基礎的な知識から、データ解析を遂行するために必要な統計専門力まで幅広く問われます。統計学で得られる知識はデータ分析に欠かせないものなので、取得しておいて損はないでしょう。
アクチュアリー資格試験
「アクチュアリー」は、「保険数理士」や「保険数理人」とも呼ばれ、保険業界の第一線で活躍できる高度専門職です。アクチュアリー試験では、第1次試験(基礎科目)の中に「数学(確率・統計・モデリング)」が含まれています。これらは、データサイエンティストの業務と共通しており、試験勉強がデータサイエンティストとしての知識・スキル習得に役立ちます。
データサイエンティストに関するよくある質問
データサイエンティストに関するよくある質問に回答していきます。データサイエンティストに関して把握しておくことで、具体的にどのような知識をどのような勉強法で身につけるべきかがわかるでしょう。自分の現状と比較し、足りない部分を補っていくことがまずは重要です。
Q1. データサイエンティストとはどんな職種?
データサイエンティストとは、購買履歴や顧客情報など企業に蓄積されたビッグデータからビジネスに活用する知見を見出し、企業の意思決定をサポートする職種です。仕事内容の詳細は「データサイエンティストの仕事内容を解説!必要なスキル、知識、学習方法もご紹介」もご参照ください。
Q2. データサイエンティストに求められるスキルは?
データサイエンティスト協会の定義では、「ビジネス力」、「データサイエンス力」、「データエンジニアリング力」の3つが挙げられています。それぞれのスキルを身につける必要があり、現状のスキルにもよりますが合計すると1年程度はかかるでしょう。
Q3. データサイエンティストに求められる知識は?
ビジネス知識やITセキュリティに関する知識に加え、データ解析、機械学習といった専門性の高い領域の知識も求められます。どの知識から身につけていくべきかは現状の知識によりますが、まずは弱点領域をカバーすることが重要でしょう。一定のスキルを身につけたら、得意分野を伸ばす選択もできます。
Q4. データサイエンティストになるにはどんな勉強法がある?
大学やスクールに通って勉強する方法と、独学で勉強する方法があります。どの勉強法でないといけないということはなく、自分の好みや得手不得手で決めると良いでしょう。たとえば複数人で学習する方が好きな人もいれば、一人で自分のペースで進めたい人もいるはずです。
まとめ
データサイエンティストを目指すために何を勉強するべきか、どのように勉強するべきかをまとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。見てきたように、データサイエンティストとして活躍するためには多種多様なスキルが求められます。自分が今何をどんな目的で学習しているのかを見失わないためにも、全体像の把握と学習順序の検討を第一に行ってください。
その人が持つスキルによって、何をどのように学ぶのが効率的かは変わってくるものですが、まずはこの記事に書かれているような手法を参考にしていただき、一歩を踏み出していただければと思います。学習していくうちに、自身に最適な学習ロードマップが見えてくるかと思います。
ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア
レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。
「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。
「個別相談会」に申し込む
転職支援サービスに申し込む
※転職活動を強制することはございません。
レバテックキャリアのサービスについて