「CTOの職務経歴書」シリーズは、レバレジーズ(現レバテック)のアナリスト兼営業マンがインタビュー取材を通して注目企業のCTOに迫る企画です。

こんにちは。レバテック営業の林です! 前回に引き続き、株式会社マネーフォワード取締役CTOの浅野千尋氏のインタビューをお届けします。起業を経験した浅野さんがマネーフォワードの創業に至るまでと、理想とするCTO像について伺いました。
マネーフォワードとは?
銀行や証券会社、クレジットカード会社のウェブサイトのアカウント情報を登録することで、各口座を一元的に管理できるアカウントアグリゲーションをベースにした家計簿・資産管理ツールやクラウド型会計ソフトなどを運営。
http://moneyforward.com/
1. 大変なシステムだからこそ、技術的な参入障壁になる
―浅野さんがトレードサイエンス社から独立し、自動運用のアルゴリズムを個人的に追及されていたときに、現在マネーフォワードCEOを務めていらっしゃる辻庸介さんと出会われたんですね。
浅野氏:そうです。もともとトレードサイエンスは、ファンドをローンチする直前にマネックス証券の100%子会社になったので、当時マネックス証券に在籍していた辻とは面識がありました。 その後、辻が留学から帰ってきて「アカウントアグリゲーションをベースにした個人向けの資産管理サービスをやりたい」と言って仲間を探していたときに、僕がエンジニアとして引っかかったんです。
―そのときに辻さんのお言葉を聞いてどう思われましたか?
浅野氏:日本でもアカウントアグリゲーションのサービス自体はあって、僕も昔に使ったことがあったんですよ。すごく便利だと思ったのですが、使い勝手が悪くて結局数か月で使わなくなってしまったんですね。 その経験があったので、辻の話す構想は絶対良いはずだという確信と、一方で、本当に使い勝手の良いサービスはまだ日本にはないということを同時に思いました。もうひとつ、日本の金融機関全部に対応するアカウントアグリゲーションシステムを作るのは大変だろうとも思いました。 でも、よくよく考えてみたら自分は今すでに似たようなことをやっているし、自分が本気を出せば今の延長線上でできなくもないかなと。大変だからこそ技術的な参入障壁にもなるので、やる価値があるんじゃないかと。いろいろなパズルのピースが一気にはまったという感じがしました。
―では、マネーフォワード創業の決断をするまでに時間はかからなかった?
浅野氏:最初にミーティングに誘われたとき、アカウントアグリゲーションの手前みたいなプログラムがすでにあったのですが、すごく効率が悪くて時間がかかるうえにデータ構造も統一されておらず、実際にサービスにするレベルにはまったく達していなかったですね。 それで、「これ、僕が直しますね」とか言って直したり、サービスに口を挟んだりしていくうちに、「立ち上げるのも当然だよね」という空気になってきて。気づけば創業メンバーになっていました。

アカウントアグリゲーションを本格的に扱うようになったきっかけは、現CEOの辻庸介氏との出会いだった
2. 経営とエンジニアの観点はそれほど離れていない
―立ち上げ当初は浅野さんがシステムを構築されていたと思うのですが、他社と比べての強みはどこだとお考えですか?
浅野氏:アカウントアグリゲーションシステムは、最初から保守がネックになるという確信があったんですよ。というのも、金融機関側は定期的にサイトをリニューアルしたり、認証方法を変えたりするので、そこに追随していかなければなりません。 つまり、新規開発よりも保守のコストのほうが膨大になると分かっていたので、いかにそこを少なくするか、低負荷で保守できるようにするかということだけを考えてアグリゲーションプラットフォームを作りました。なので、それを最初から考えていたからこそ、ここまでスケールすることができたのではないかなと思います。
―現在は、主にどのようなお仕事をされているのですか?
浅野氏:大きな経営判断やアライアンス関係のほか、エンジニアのチーム作り、採用など、人に関わることをメインにやっています。アカウントアグリゲーションの新規の実装や保守もやっているのですが、以前に比べるとだいぶ少なくなりました。
―コードを今でも書く理由って何ですか?
浅野氏:楽しいからです。やはり僕は、何かを生み出しているとき、"ゼロイチ"をしているときが一番楽しいんですね。ただ、そうは言ってもこのフェーズのCTOなのでずっと書いているわけにもいかない。なので「マネーフォワードという新しい概念を世の中に生み出している」というもっと大きな視点の"ゼロイチ"を意識し、それに注力するようにしています。
―CTOという立場的に、技術者と経営陣、あるいは営業陣の板ばさみになったりしたことはありますか?
浅野氏:全くないですね。創業当初から僕はいましたし、取締役兼エンジニアとして、技術的なビジョンを経営に取り入れるという観点で取り組んできたので、経営という観点とエンジニアという観点はあまり離れていないんですよ。 また、お客様の要望に関しても、営業やカスタマーサポートの人たちだけでなく、エンジニアも積極的に関わろうとしてくれています。全員が同じ方向を見ながら一丸となって全体としての優先順位を意識しているので、お客様のことを考えたフラットで本質的な議論を行う事ができています。
―非常に経営的な視点を身につけていらっしゃいますが、それはどのように身につけていったんですか?
浅野氏:先輩方を見て真似できるところは真似をし、わからないところはとことん話すことで身につけてきたと思っています。トレードサイエンス社の立ち上げメンバーのなかでは一番若かったですし、マネーフォワードでもCEOの辻など、いろいろな先輩方から経営陣はどうあるべきかを学び、身につけていったという感じです。僕は人のいいところをどんどん取り入れて、自分を成長させていくのが好きなんです。

経営者と技術者。2つの顔を器用に使い分ける回答からは、普段のシームレスな仕事ぶりが伺えた
3. CTOの自分も、会社の成長とともに成長していく
―実際にCTOをやっていくうえで、必要な心構えとは何ですか?
浅野氏:CTOの仕事においてベースになる部分とは経営に技術的なビジョンを組み入れることだと思っています。ただ、それを達成するために実際に行動するべきことは会社のフェーズによって変わるんですよね。会社が小さく数人規模のときですと、CTO自身がエンジニアリングにコミットしてモノを作り、サービス自体を最速でアウトプットしていくべきです。 それが今ぐらいの規模になると、組織作りやチーム作りなど人に関わる部分に視野を広げ、整えることによって、技術的なビジョンを経営に取り入れることに貢献するようになります。 同じ目的だけど、それを解決する手段がフェーズによって変わってくるので、CTOとなる人はフェーズに合わせて自分の行動すべきことが変わるということを認識しなければいけません。会社の成長に合わせて、自分自身も成長して変わっていく必要があります。
―採用においては、どういうエンジニアを求めていらっしゃいますか?
浅野氏:全体観をとらえながら行動できる人ですね。エンジニアとチームの関係は、プロサッカーチームみたいなものだと思います。エンジニアにはサッカー選手のように攻めと守りのポジションがあって、たとえばアカウントアグリゲーションの保守は守りであり、我々のコアテクノロジーとして、鉄壁のディフェンスで守ってもらわなければいけない大事な要素です。 とはいえ、怒涛のオフェンス力で新規のサービスを作る攻めのエンジニアもいないと、世の中にインパクトを与えられません。個としての能力を究極的に高めながらも、チームプレーとのバランスを取っていく必要があります。 チーム全体を考えて自分の能力をどこに生かすべきかという立ち位置をつねに調整し、さらに自らの技術も磨くことができる、エンジニアとしてのバランス感がある人が理想です。

欲しいのは、全体を見て行動できるエンジニアだと話す浅野氏。
また、チームにはサッカーのように攻守のバランスが欠かせないという
―最後に、浅野さんはCTOとしてどのような進化をしていきたいですか?
浅野氏:「CTOとは何か?」というのはよく議題に上がるテーマだと思うのですが、自分自身でもまだ解が出ていません。役割としては、経営に対して技術を持ち込むという言葉に集約されますが、決してそれだけじゃないと感じています。CTOをやっていて思うことは、この問いに対する答えは会社の数だけあるということです。 それでは「マネーフォワードにとってのCTOとは何か?」というと、その答えもまだ見つかっていません。ずっと右肩上がりで成長してきていて、そのフェーズごとに求められることが変わってきています。この先3か月後、半年後、1年後でもどんどん変わっていくと思っていて、まだまだCTO像が完成する気はしないですね。 変わっていくなかでも「CTOとは何か?」という答えを見つけられるように、会社の成長に合わせて自分も成長させていきたいと考えています。
―ますますお忙しくなるかと思いますが、それでもプログラミングには、何かしらの形で携わっていきたいですか?
浅野氏:携わっていたいですね。希望としては(笑)

インタビュー中、こちらの目を見据えてどんな質問にも丁寧に答えてくださった浅野氏。「エンジニアとしてより良いシステムを追及していく姿勢と、
経営陣の一員としてより良い会社のあり方を追及していく姿勢との間に矛盾はない」と断言された表情はとても印象的で、会社への熱い想いが強く伝わってきました。

カメラを向けると、気さくに笑顔を見せてくれる浅野氏(左)。今後も躍進を続ける同社からは、ますます目が話せない







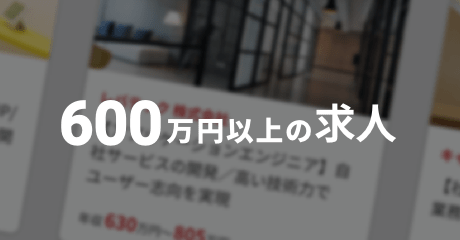




















![【CTOの職務経歴書】マナボ CTO 山下大介氏 [後編]](/files/img/guide/pickup/7/list.jpg?1481766855)
![【CTOの職務経歴書】マナボ CTO 山下大介氏 [前編]](/files/img/guide/pickup/6/list.jpg?1481766855)
![【CTOの職務経歴書】無駄を減らして、その分クリエイティブな事に時間を使った世界がどうなるかを見たい|KAIZEN platform Co-Founder & CTO 石橋利真氏[後編]](/files/img/guide/pickup/4/list.jpg?1481766855)
![【CTOの職務経歴書】効率化で人を自由にする。昔からそれが僕のモチベーション|KAIZEN platform Co-Founder & CTO 石橋利真氏[前編]](/files/img/guide/pickup/3/list.jpg?1481766855)
![【CTOの職務経歴書】お金とか指示とか関係なく「やりたい」って思えることって、かけがえのない強さ|トライフォート CO-Founder/CTO 小俣泰明氏[後編]](/files/img/guide/pickup/2/list.jpg?1481766855)










